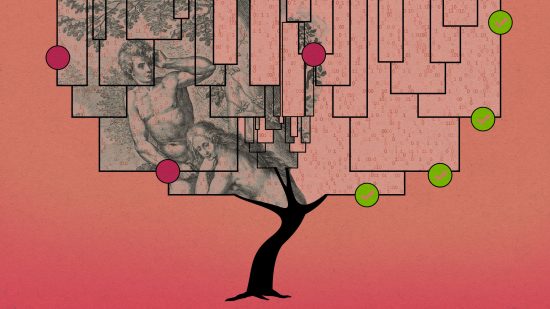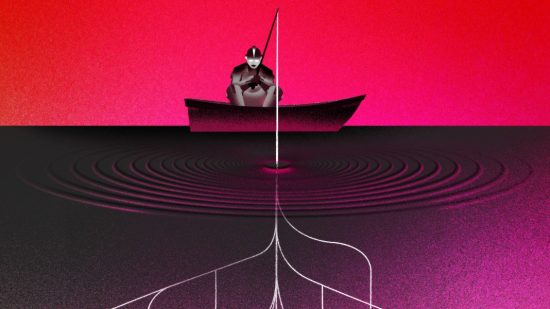誰がネットを救うのか?
最新書籍から読み解く
改革への3つの処方箋
巨大テック企業を分割すべきか、規制で抑えるべきか、それともユーザーにデータ管理権を与えるべきか。3冊の最新書籍が示す改革案は、インターネットの未来を巡る根本的な問いを投げかける。 by Nathan Smith2025.11.27
- この記事の3つのポイント
-
- ティム・ウー、ニック・クレッグ、ティム・バーナーズ=リーの3人がインターネット改革の抜本的アプローチを著書で提案
- 依存性の高いアルゴリズムや搾取的アプリなど、現在のインターネットが危険な場所となっている現状への対応策
- 反トラスト法の限界や政治情勢を踏まえ、単一解決策の困難さと包括的合意の必要性が浮き彫りに
依存性の高いアルゴリズムから搾取的なアプリ、データマイニングから誤情報まで、今日のインターネットは危険な場所になり得る。「ネットワーク中立性(特定のサービスを優遇・制限しないことを求める原則)」の原理を提唱した知識人、メタの元幹部、そしてWebそのものの発明者という3人の影響力ある人物が、それを修復するための抜本的なアプローチを著書で提案している。しかし、彼らはその任にふさわしい人物なのだろうか。3人とも信念を持ち、時に独創性すら示しているものの、提示される解決策には見落としがある。
『The Age of Extraction: How Tech Platforms Conquered the Economy and Threaten Our Future Prosperity(搾取の時代:テックプラットフォーム企業はどのように経済を支配し、私たちの将来の繁栄を脅かすのか)』(2025年刊、未邦訳)において、ティム・ウーは、少数のプラットフォーム企業に権力が過度に集中しており、解体すべきだと主張する。自由なインターネットにはすべてのオンライントラフィックを平等に扱うべきだという原則を広めた、コロンビア大学の著名な教授であるウーは、既存の法制度、特に独占禁止法こそがこの目標を実現する最善の手段だと考えている。
ウー教授は経済理論と近年のデジタル史を組み合わせて、プラットフォーム企業がユーザーに便益を提供する存在から、ユーザーから価値を搾取する存在へとどのように変貌してきたかを示している。彼は、私たちがこうした企業の力を十分に理解してこなかったことが、かえって彼らの成長を助長し、その過程で競合他社を排除する結果になったと論じている。そして、プラットフォーム企業がユーザーを囲い込むために最も多用するのが「利便性」であると指摘する。「人間が不必要な苦痛や不便を避けたいと望む気持ちは、おそらく最も強力な力かもしれない」と彼は述べている。
彼は、グーグルやアップルの「エコシステム」を例に挙げ、それらが包括的かつシームレスであるがゆえに、ユーザーがこれらのサービスに依存してしまう状況を示している。ウー教授にとって、これはそれ自体が悪ではない。アマゾンを使ってエンタメをストリーミングしたり、オンライン・ショッピングをしたり、日常生活を整理したりする利便性は明らかな恩恵をもたらしている。しかし、アマゾン、アップル、アルファベットのような巨大企業が「利便性競争」に勝ち、しかも競合他社に一切の参入余地を与えないとき、そこで生まれる「業界支配」は再検討されるべきものとなる。
ウー教授が提案する対策は、既存の法制度と経済政策に基づいており、実現可能性が最も高いと思われるものだ。それは、連邦独占禁止法、企業が消費者に課す料金を制限する「公共料金上限」、そして特定の産業分野での事業展開を禁じる「業種制限」である。
ウー教授は、独占禁止条項や反トラスト法は、私たちの手にある有効な対抗手段だと主張し、それらが過去にテック企業に対して成功裏に適用された事例があると述べている。彼が挙げる2つの代表的なケースの1つは、1960年代に米政府がIBMを訴えた反トラスト訴訟で、これによりソフトウェア市場に競争が生まれ、アップルやマイクロソフトといった企業の登場を促した。もう1つは1982年のAT&Tに対する訴訟で、これにより電話通信の巨大コングロマリットが複数の小企業に分割された。いずれの事例でも、ハードウェアやソフトウェア、その他のサービスの分離が、一般市民の利益となり、テクノロジー市場における競争と選択肢を増やす結果となった。
しかし、過去の成功が未来を保証するだろうか? こうした法律がプラットフォーム時代にも通用するかどうかは、依然として不透明である。2025年のグーグルに対する反トラスト訴訟では、米司法省が求めたChrome(クロム)ブラウザーの分離(売却)を裁判官が不要と判断し、法によるテック企業の分割の限界が明らかになった。2001年のマイクロソフトに対する訴訟も同様に、Webブラウザー部門の分離に失敗し、事業の大半はそのまま維持された。ウー教授は、最近の反トラスト訴訟を論じる中で、このマイクロソフトの事例には明確に触れていない。
最近までメタの国際渉外担当社長を務め、かつて英国の副首相でもあったニック・クレッグは、ウー教授とは大きく異なる立場を取っている。彼は、巨大テック企業を分割しようとするのは誤った方向であり、インターネットユーザーの体験を損なうことになると考えている。著書『How to Save the Internet: The Threat to Global Connection in the Age of AI and Political Conflict(インターネットを救う方法:AIと政治的対立の時代におけるグローバル接続の脅威)』(2025年刊、未邦訳)の中で、クレッグは大手テック企業によるWebの独占を認めつつも、反トラスト法のような懲罰的な法的措置は生産的ではなく、たとえばソーシャルメディア上で掲載可能なコンテンツに関するルールといった「規制」によって問題を回避できると主張している(注目すべきは、メタも現在反トラスト訴訟に直面しており、InstagramやWhatsAppの買収の妥当性が争点になっていることだ)。
クレッグはまた、改革の主導権はシリコンバレーの企業自らが握るべきだとも考えている。彼は、ソーシャルメディア企業に対し「内部情報を公開 …
- 人気の記事ランキング
-
- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」
- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」
- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?