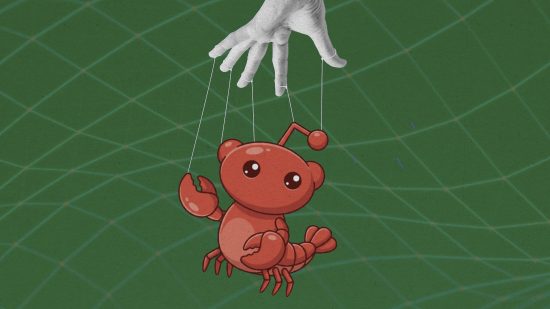フラッシュ2024年2月7日
-
気候変動/エネルギー
光合成触媒の動きの観察に成功、人工光合成へ一歩=岡山大など
by MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]岡山大学や東北大学などの共同研究チームは、光合成を担う「ゆがんだイス」型の触媒が、水分子を取り込み、酸素分子生成の準備が完了するまでの一連の動きを捉えることに成功した。光合成で水分子から水素イオンと電子を取り出す仕組みの解明だけでなく、光で水を分解するための触媒の設計に重要な指針を与える成果として、人工光合成の実現につながりそうだ。
光合成では、「光化学系II」と呼ばれる膜タンパク質複合体が光エネルギーを利用して、水分子から酸素分子を生成する。研究チームは、光化学系IIの結晶に可視光を当てて反応を開始させた後に、X線自由電子レーザー施設「SACLA」のフェムト秒X線(1フェムト秒は1000兆分の1秒)を照射。光化学系IIの「ゆがんだイス」型の触媒が水分子を取り込み、酸素分子生成の準備が完了するまでの一連の動きの立体構造をナノ秒(1ナノ秒は10億分の1秒)からミリ秒の時間スケールで捉えることに成功した。
その結果、光化学系IIの内部では、タンパク質、水分子、集光色素などがオーケストラのように協奏的に働き、水の移動や水素イオンの排出を進行させることが判明。この働きによって運動性が高まった水分子が、触媒に過渡的に結合した後、その内部へと取り込まれていく様子が初めて観測された。
研究論文は、英国科学誌ネイチャー(Nature)に、2024年1月31日付で掲載された。
(中條)
-
- 人気の記事ランキング
-
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験