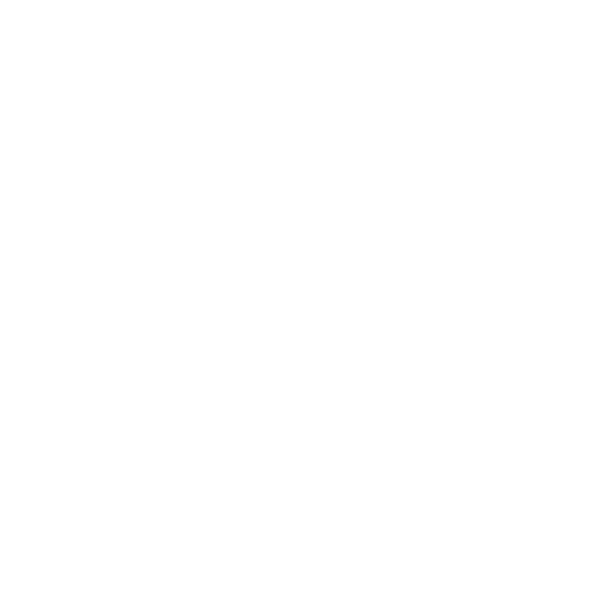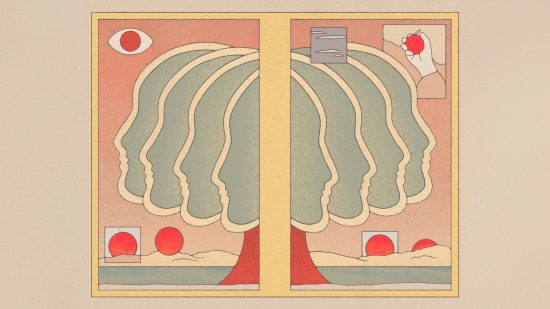ADHD(注意欠如・多動症)や認知症の患者など、多くの人が日常生活で医師などの専門家による支援を必要としているが、病院を離れると安定したサポートを受けることが難しい。カーネギーメロン大学コンピューターサイエンス学部でヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)を専攻する博士候補生の荒川 陸は、この世界的な医療課題の解決に挑んでいる。スマートウォッチなどの身近なデバイスから得られるデータを用いて日常行動をデジタル化し、患者の行動モデルを構築して、適切なタイミングで介入・支援するヘルスケアAIアシスタントの開発である。
その代表例が、認知症患者や皮膚がん患者の術後ケアなど、複雑な手順を伴う日常タスクを支援するAIアシスタント「PrISM(プリズム)」だ。スマートウォッチに搭載されたマイクとモーションセンサーが患者の行動を追跡し、あらかじめ定義されたタスクの手順を飛ばしたり、順番を誤ったりしそうなタイミングを先読みして、音声でリマインドする。AIアシスタントが能動的に介入することで、手順の誤りが深刻な事態につながるケースを防ぐ。利用者の「次に何をしたらいい?」といった質問にも、大規模言語モデル(LLM)を用いて回答することが可能だ。
特徴は、スマートウォッチをセンサーとして利用することで、カメラを使ったソリューションに比べてユビキタス性とプライバシーに配慮している点である。また、センサーがうまく機能しない場合にも、手順間の遷移確率や所要時間といった情報を用いて、ユーザーが現在どの手順にいるかを推測するアルゴリズムを搭載する。
荒川は、「センシングには必ず誤差やノイズが伴います。未来の完璧なセンシングを待つのではなく、不確実性を前提とした設計論が必要です」と語る。さらに、AIシステムが運用後に患者の行動パターンや環境に適応していく「ポストデプロイメント学習」の手法を導入。ユーザーとのインタラクションを通じてAIアシスタントが賢くなり、支援の精度が継続的に高まるシステムを実現した。「不確実性に遭遇したAIをユーザーが助け、賢くなったAIがよりユーザーを支援する、そういった協力関係を実現したいです」
荒川はこのほか、ADHDの小児の行動をスマートウォッチの姿勢追跡技術で定量化するツール「LemurDx(リーマーDx)」も開発している。診察室では観察できない日常生活での子どもの行動パターンを、医師や家族が客観的に把握して、診断や家庭内コミュニケーションの促進を目指したものだ。これらのシステムは現在、米国と欧州の複数の医療機関で導入され、実際に評価が進められている。
(畑邊康浩)
- 人気の記事ランキング
-
- This Nobel Prize–winning chemist dreams of making water from thin air 空気から水を作る技術—— ノーベル賞化学者の夢、 幼少期の水汲み体験が原点
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- The paints, coatings, and chemicals making the world a cooler place 数千年前の知恵、現代に エネルギー要らずの温暖化対策
- Quantum navigation could solve the military’s GPS jamming problem ロシアGPS妨害で注目の「量子航法」技術、その実力と課題は?