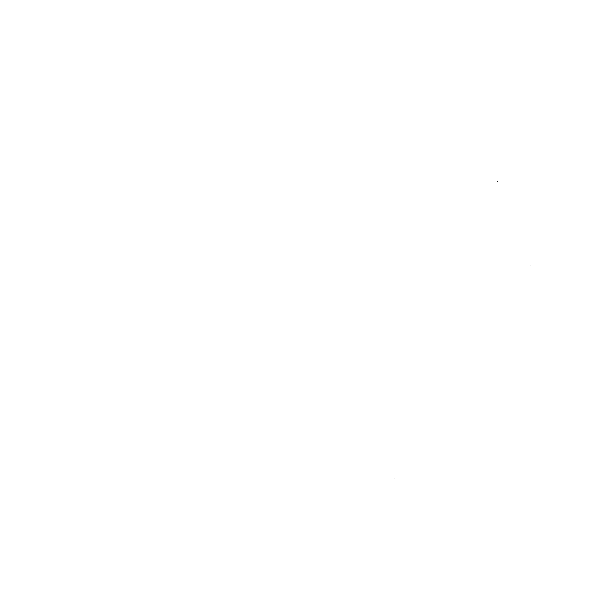Masatoshi Uehara 上原雅俊 (31)
生成AI技術を応用した革新的な分子設計アルゴリズムを開発。次世代創薬を切り拓く。
現代の薬づくり、すなわち創薬研究では、薬の候補化合物となる理想的な分子構造を設計することが重要だ。従来の分子設計は、研究者の経験や直感、単純な機械学習の結果に大きく依存していた。そのため、未知領域の分子に対する予測精度が十分でないケースや、モデルが提案する分子の 安定性、安全性、製造容易性が低いケースもあった。
AIによる人工タンパク質設計のスタートアップ企業であるチャン・ザッカーバーグ・バイオハブ(Chan Zuckerberg Biohub)の研究科学者で、ウィスコンシン大学マディソン校の助教授に着任予定の上原雅俊(Masatoshi Uehara)は、創薬向けAIの研究開発に取り組んでいる。上原が従来の課題を克服するために着目したのが、ノイズを加えてデータを再構築する生成AIの一種である「拡散モデル(diffusion model)」と、強化学習を組み合わせる手法だ。上原は、大量の分子データを学習した基盤モデルを構築し、分子同士の結合親和性や特異性、安定性、毒性といった指標を報酬関数として用いる強化学習によって最適化するアルゴリズムを開発した。
このアプローチは自然言語処理の分野では活発に研究されてきたが、創薬向けの分子設計に適用して高い成果を上げた例はほとんどなく、学術界で画期的な成果として評価されている。上原の研究はNeurIPSをはじめとする世界トップクラスの学会で採択されており、所属していたエボリューショナリー・スケール(EvolutionaryScale)は、すでに2億ドル以上を調達した有力スタートアップとして注目されている(今年11月には、その成果、先進性が認められ、同社はチャン・ザッカーバーグ・バイオハブに買収された)。上原はその中で、人工タンパク質設計を推進する中核プロジェクトを主導している。
上原の開発した分子設計アルゴリズムは、がんや神経疾患などに対する新しい抗体医薬や中分子医薬の設計に応用できる可能性がある。強化学習による最適化は、既存薬を上回る薬効をもち、副作用を抑える新薬の設計にもつながるだろう。実験コストや時間を削減し、創薬スピードを大幅に向上させる効果も期待される。上原は、「抗体医薬では難しい細胞内標的を狙える中分子など、新しいモダリティ(治療手段)への応用を通じて、既存薬では対応できなかった疾患の治療へと道を拓いていきたい」と述べている。
(島田祥輔)
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?