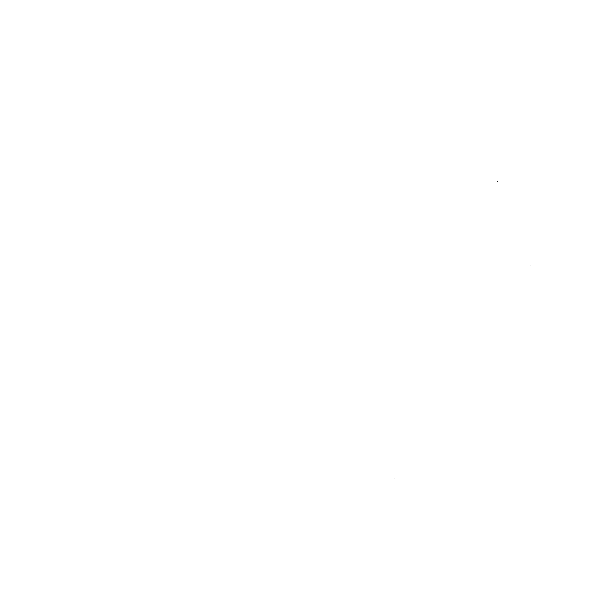ロボット大国である日本は、かつてヒューマノイド(人型ロボット)研究においても世界をリードしていた。しかし近年は勢いに陰りが見え、海外の研究機関やスタートアップが存在感を強めている。そうした中で、再び世界の注目を浴びている日本の研究者が、東京大学 次世代知能科学研究センター (AIセンター)講師の河原塚健人だ。
河原塚は、人間のように筋肉で動く筋骨格ヒューマノイドを数多く開発・発表。その複雑な身体構造をロボット自身が理解・制御する学習機構を提案し、身体を正確かつ柔軟に動かす方法論を解明してきた。具体的には、人間の伸長反射や腱反射といった反射機能の有用性、橈骨尺骨構造、靭帯、筋腱複合体といった身体構造を工学的に解析し、人間のプロポーションや重さ、機能をロボットで緻密に再現する研究である。これらの成果を、河原塚は過去10年間で主著56本、共著を含め110本以上の論文として発表してきた。ロボット工学のトップ国際会議であるICRA2024での最優秀論文賞受賞や、Humanoids2024での最年少招待講演など、河原塚の取り組みは学術界で高い評価を得ている。
具体的な河原塚の取り組みの一つが、2024年に世界で初めてオープンソースとして発表された金属製四脚ロボット「MEVIUS(メビウス)」だ。従来のオープンソースロボットは3Dプリンター製が主流で、激しい動きや屋外環境での実験に耐えられなかった。金属製ロボットであるMEVIUSは、ネット通販で入手できる既製品と、板金加工や溶接で製作する部品で構成され、個人研究者でも再現できるのが特徴だ。設計データ、製作手順、制御ソフトウェアをすべて公開した結果、多くの研究者や企業が実際に再現実装に取り組んだ。また、四脚ロボットを扱うベンチャー企業が相次いで登場し、ロボット研究コミュニティに大きな影響を与えている。2025年には、金属製のオープンソース二脚ロボット「MEVITA(メビータ)」も発表した。
河原塚は、「一度しぼんでしまった日本のヒューマノイド研究が息を吹き返し、再び世界をリードするための一手となる」と、オープンソース化の狙いを語る。ヒューマノイドへの世界的関心が高まる中、河原塚の挑戦は日本のロボット研究が再び国際舞台で存在感を取り戻すための象徴的な試みとして期待されている。
(畑邊康浩)
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?