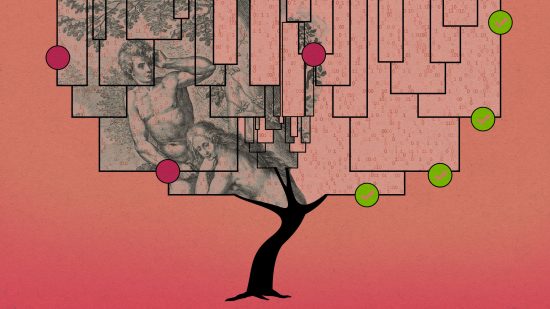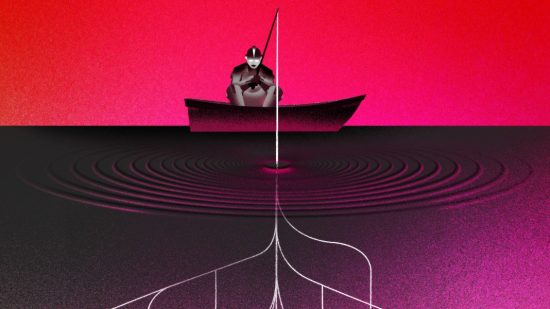機械化する「私」たち
AIロボット時代の
人間性を問う3冊
ロボットと人間の境界が曖昧になる現代。3冊の新刊から見えてくるのは、テクノロジーに寄り添うほど機械化していく私たち自身の姿だ。 by Bryan Gardiner2025.03.19
- この記事の3つのポイント
-
- 人間とロボットの関係性が変化し社会に大きな影響を及ぼす可能性がある
- ロボットの知性を過大評価し人間性を機械にたとえる風潮が広がりつつある
- AIやロボットの裏側では低賃金のデジタル労働者が働いている現実がある
自分の知る限り、私はロボットではない。それなのに、インターネット上で長時間過ごす他の人間と同様、私は自分が人間だと証明するよう繰り返し求められている。画像の中の横断歩道やオートバイをクリックしたり、歪んだ数字や文字を読み解いたり、「私はロボットではありません」のチェックボックスをチェックするなどして。これら「コンピュータと人間を見分けるための完全自動公開チューリングテスト」、いわゆるキャプチャ(CAPTCHA)は、スパムやデータスクレイピングの防止に役立つとされている。しかし今ではボットの方が人間よりもキャプチャを上手く解くようだ。これは驚きだ。
幸いなことに、現実世界で人間と機械を見分けるのはずっと簡単だ(少なくとも今のところは)。確実な違いが出やすいもののひとつは、人間に固有の技能だ。たとえば世界チャンピオンレベルでチェスを指す、途方もなく大きな数字の掛け算をするなど、成人が難しいと感じることを機械は得意とする傾向がある。一方、ボールをつかむとか、物にぶつからずに部屋の中を歩き回るなど、5歳児がたやすくこなすことを達成するのは難しい(あるいは不可能である)。
機械に抽象的思考を教えるのは比較的簡単なのに、基本的な感覚や社交術、あるいは運動を教えるのは難しいというこの矛盾は、「モラベックのパラドックス」として知られている。これはロボット工学者のハンス・モラベックが1980年代後半に観察したことにちなんで名付けられた。その内容は、人間にとって難しいこと(数学、論理学、科学的推論)は機械にとって簡単だが、機械にとって難しいこと(靴ひもを結ぶ、感情を読み取る、会話をする)は人間にとって簡単だというものだ。
サイエンスライターのイブ・ヘロルドは、最新の著書である『Robots and the People Who Love Them: Holding On to Our Humanity in an Age of Social Robots(ロボットとそれを愛する人々:社会的ロボットの時代に人間性を保ち続ける)』にて、機械学習の新しい手法と人工知能(AI)の絶え間ない進歩のおかげで、このパラドックスがようやく解明されつつあると説く。そしてその結果、個人用の社会的ロボットの新時代が幕を開けようとしているという。その時代が訪れると、私たちは友情や愛情、さらには仕事、健康管理、家庭生活に至るまで、あらゆるものの本質を再考することを迫られる。
社会的ロボットが拓く素晴らしい新世界を読者に想像してもらうため、ヘロルドは日本のソフトバンクが作ったつぶらな瞳の人型ロボット、「ペッパー(Pepper)」を紹介している。「ペッパーのようなロボットと人間との関係は、独特でかつ一人一人異なるものになる。そのため近い将来、なくてはならない存在になるだろう」とヘロルドは書いている。その後、人の胸の高さほどのお友達ロボットが、私たちの表情や感情を難なく読み取り、子供のような声で適切に応答する様子を、プレスリリースさながらの熱意で説明している。
ペッパーという名にうっすら聞き覚えがあるのなら、それは2014年の発表以来、世界初の「感情を持つロボット」としてたびたび宣伝されてきたからかもしれない。しかしそれは2021年に突然終わった。ソフトバンクが需要不足を理由にペッパーの生産を停止したのだ。2000ドルもするアンドロイドなのにほとんどのことをうまくできないのもおそらく無関係ではあるまい。本を書くには時間がかかるし、執筆中にいろいろな変化が起きることもあるだろう。しかしペッパーの生産停止は出版の3年前だったのに、その事実を見落としていたというのは筋が通らない。
人気がなく、誰も買おうとしないような過去の製品を、社会的ロボットがもたらす新たな革命のさきがけだと担ぎ上げられても、説得力に欠ける。ヘロルドはおそらく、この本の焦点はロボットそのものよりも、人間とロボットが築く新しい社会的関係に私たち人間が何をもたらすかにある、と反論するだろう。なるほど理にかなっている。
彼女は、私たちがロボットを擬人化したがる癖を丹念に解説し、深層学習や「不気味の谷」に関する基本的な研究を読者に紹介している一方、人間の性質や心理に関する結論は、単純化しすぎているか、彼女が提示する科学的根拠から飛躍しているように思える。「未来について書くための唯一の方法は、非常に謙虚な気持ちを持つことだ」と言う割には、いたく疑わしい主張(「これまでのところ私たちがアルゴリズムに対して寄 …
- 人気の記事ランキング
-
- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」
- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」
- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?