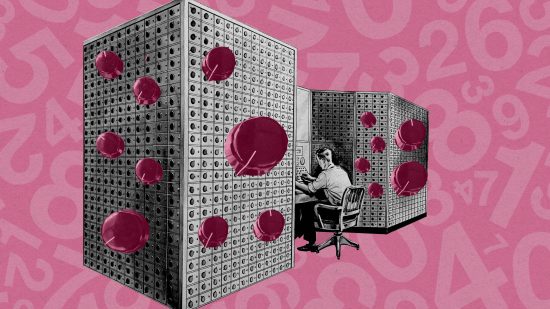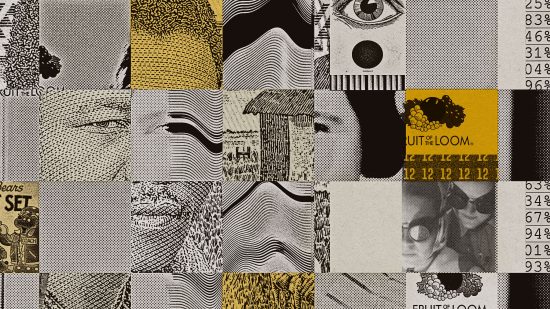マスク、ベゾスの野望
最悪の「宇宙入植論」に
徹底的に挑む3冊
「宇宙は最悪だ」——。マスク、ベゾスらが描く楽観的な宇宙入植論に、3冊の本が挑んでいる。宇宙カニバリズム、火星版優生学、小惑星兵器まで想定する批判書は、億万長者の野望の裏に潜む現実的・倫理的問題を問う。 by Becky Ferreira2025.08.29
- この記事の3つのポイント
-
- 宇宙入植推進派の楽観論に対し、3冊の批判書が現実的・倫理的問題を体系的に指摘
- 地球上の貧困や不平等を放置して宇宙開発に巨額投資することの道徳的問題を提起
- 人類は宇宙進出前にまず地球での成熟と脱植民地主義的アプローチを採用すべきと提案
イーロン・マスクとジェフ・ベゾスは、商業宇宙開発の分野で激しく競い合っているが、ある一点では意見が一致している。それは、宇宙への入植が人類の存続にとって不可欠だということだ。宇宙こそが目指すべき場所であり、最後のフロンティアである。人類が故郷の星を超えて、文明を地球外へと広げることは、私たちの運命なのだ。
この考え方自体は何十年も前から主流であったが、宇宙起業家たちが台頭するこの新たな金めっき時代において、その勢いはまさに急速に加速している。彼らは、地球を超えて人類の存在を広げることは、生まれながらの権利であり、未来に対する義務でもあると主張している。そうしなければ、核戦争や気候変動といった自らの手、あるいは巨大隕石の衝突のような宇宙規模の災厄によって、私たちの種は確実に絶滅することになるという。
だが、私たちが巨大な軌道ステーションや火星都市の光景を頭の中で夢想する一方で、人類による宇宙植民地化に反対する議論が、近年の多くの書籍の中で存在感を増してきている。その議論は、多様な根拠に基づいている。地球外コミュニティの現実的な実現可能性への疑念。誰がその費用を負担し、誰が恩恵を受けるのかという、膨大な費用に関する懸念。宇宙という過酷な環境が人間の身体に強いる深刻な負荷についての現実的な認識。そして、宇宙入植という構想を駆り立てる根底のイデオロギーや神話への不信感、などだ。
もっと露骨に言えば、「宇宙は最悪だ」という認識であり、多くの人々が「その最悪さのスケールを見誤っている」とする見方だ。これは、今年ペーパーバック版が刊行された書籍『A City on Mars: Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through?(火星の都市:私たちは宇宙入植できるか、宇宙入植すべきか、そのことを本当に熟考したか?)』(未邦訳)の中で、著者であるケリー&ザック・ワイナースミス夫妻が述べている。
ワイナースミス夫妻は、この問題について何年もかけて、しかも実に楽しく、そして現実的な細部にまでこだわって考え抜いた。『A City on Mars』は、宇宙入植がもたらす医学的・技術的・法的・倫理的、そして存続に関わる影響をシミュレーションしながら、私たちの空高く舞い上がる夢に対し、地に足のついた現実を突きつけてくる。
そしてその結論は、著者たち自身も落胆するほどグロテスクなものになっている。そこには、火星版優生学や惑星間戦争、さらには記憶に残る「宇宙カニバリズム」などのシナリオが含まれている(もちろん、それだけではないが)。
ワイナースミス夫妻は、人間をどうやって住まわせるかといった、ごく基本的な疑問を投げかけることで、宇宙都市というぼんやりした幻想に針を刺す。宇宙飛行士は宇宙で、放射線被曝や骨密度の低下など、さまざまな医学的困難に直面する。こうした問題は、親子の双方にとってのリスクを高めるだろう。妊娠中の「輝き」が宇宙放射線の副作用であるなんて、誰も望んでいない。
宇宙で子どもを産むことは、「科学的な観点だけでなく、科学倫理の観点からも極めて厄介な問題になるだろう」と、2人は書いている。「大人は実験への参加に同意することができるが、赤ちゃんにはその選択肢がない」。
火星に行くべきかどうかを深く考えなくても、この議論は成立する。サバンナ・マンデルは著書『Ground Control: An Argument for the End of Human Space Exploration(地上管制:有人宇宙開発終焉のための論拠)』(未邦訳)において、有人宇宙飛行が、地球上で最も脆弱な立場にある子どもたちに対する侮辱と捉えられてきた歴史を、年代順にたどっている。
「腹をすかせた子どもたちは、月の石を食べられない」。1969年7月、アポロ11号の打ち上げ前夜にケネディ宇宙センター前で行なわれた抗議デモのプラカードに書かれていた言葉だ。この運動を象徴する存在となったのが、ギル・スコット・ヘロンによる1970年の詩『Whitey on the Moon(月の上の白人)』だ。この詩は、今日に至るまでこう主張し続けている。人類がまず自分たちの地球という家をきちんと整えるまでは、宇宙に新しい家を築く資格などないのだ、と。
『Ground Control』は一部回想録であり、一部はマニフェストである。そしてそこには、ある問いが通奏低音のように流れている。地球上にこれほどの苦しみが存在する中で、人類を宇宙に送り出すという莫大なコストを、どう正当化できるというのか?
有人宇宙開発を支持する人々は、こうした「ゼロサム思考」に異を唱える。彼らは、有人宇宙飛行によって生まれたさまざまな波及的な恩恵を挙げて擁護する。宇宙開発は、CTスキャンや粉ミルクといった日常的な発明の触媒となってきた。また、果てしない宇宙について私たち人類が共に学び続けるという冒険そのものにも、固有の価値がある、と。
そのような恩恵が実際に存在するのは確かだが、それが公平に分配されているとは到底言えない。マンデルは、現在の商業宇宙産業の構造が、むしろ地球上の不平等をさらに悪化させることになるだろうと予測している。なぜなら、宇宙ベンチャーによって生まれた利益は、すでに法外な富を持つ人々の金庫に流れ込むことになるからだ。
ヴァージニア工科大学の宇宙人類学者であるマンデルは、著書の中で、「宇宙を夢見る者」から「地に足のついた批評家」へと至った、個人的な変化の軌跡を描いている。その転機となったのは、ニューメキシコ州の商業ロケット発射施設「スペースポート・アメリカ」でのフィールドワークだった。そこで彼女は、宇宙億万長者たちが描く眩い未来の裏側に、次第にひび割れが見え始めていることに気づく。ロンドンの路上での抗議活動から、ワシントンDCでの華美な宇宙産業の宴会へとキャリアの舞台が変わ …
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している