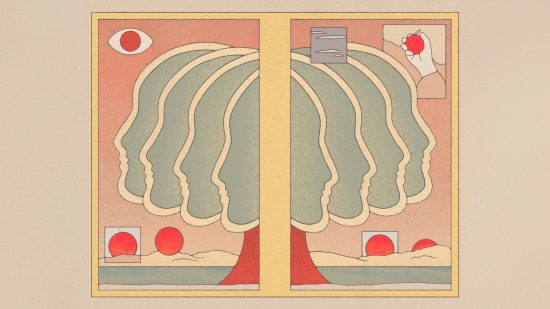危機に瀕する気候データ、地味な研究こそ継続性が重要な理由
米国の科学予算削減により、長期気候データの収集網が崩壊の危機に直面している。積雪測定からCO2濃度観測まで、地味だが継続的な研究こそが私たちの生活と未来を支える基盤となる。 by Casey Crownhart2025.05.19
- この記事の3つのポイント
-
- 米国の科学予算削減により重要な気候データが失われる危機にある
- 長年の二酸化炭素濃度測定や災害の経済的影響の追跡が中止の恐れ
- データ収集の地道な取り組みは重要で失えば気候変動対策に支障をきたす
ここ数カ月、特に直近の数週間で、米国における科学予算の削減案に関するニュースが急増している。筆者が気づいたある傾向とは、研究者や公務員たちが、それらの予算削減により、世界の理解や気候変動の影響を把握するのに役立つ重要なデータを失う可能性があると警鐘を鳴らしていることだ。
本誌のジェームス・テンプル編集者が執筆した新しい記事では、米国西部全域の山岳地帯における積雪の温度を測定しようとする研究者たちについて取り上げている。春に解ける雪は、この地域の主要な水源であり、雪の表面よりもはるか下の温度を監視することで、科学者たちは水が山を下る速度をより正確に予測できるようになる。それにより、農家や企業、住民が計画を立てやすくなるのである。
しかし、米国連邦政府による予算削減の影響で、西部全域の積雪量を監視してきた長年の政府プログラムが存続の危機にさらされている。さらに、ハワイでの二酸化炭素測定やハリケーン予測ツール、自然災害による経済的影響を追跡するデータベースも同様に危険にさらされている。こうした状況を受けて、私は考えずにはいられない。データが危機に瀕しているとき、私たちは何を失うのだろうか?
たとえば、世界最大の活火山の北側に位置するマウナロア観測所の研究を見てみよう。このハワイの施設では、1958年以来、大気中の二酸化炭素濃度が測定され続けている。
この研究の成果として得られたグラフは、研究を開始した科学者チャールズ・デービッド・キーリングにちなんで「キーリング曲線(Keeling Curve)」と呼ばれている。これは気候研究の柱であり、地球温暖化の主因である温室効果ガス・二酸化炭素の大気中濃度が、、1958年の約313 ppmから現在では420 ppmを超えるまでに上昇したことを示している。
米国海洋大気庁(NOAA)への予算削減案は、このキーリング曲線の将来を危うくするものである。現在その管理を担っているキーリングの息子、ラルフ・キーリングは、ワイアード(Wired)の新しい記事の中で「この予算削減が実現すれば、それは米国だけでなく世界にとっても、気候科学にとって悪夢のようなシナリオになる」と述べている。
この話は、現在の気候科学界全体に大きな波紋を広げている。たとえば、ハリケーン予測に使われる最先端の気候モデルを開発しているとされるプリンストン大学の研究室も、NOAAの予算削減により存続が危ぶまれている。そして先週、NOAAは米国で発生した最大規模の自然災害による経済的影響の追跡を中止すると発表した。
これらの予算削減は、最大規模の気候対策の一部に影響を及ぼすだけでなく、ジェームス編集者の記事が示すように、さまざまな専門分野にも波及する可能性がある。一見ニッチに見える研究でも、研究者だけでなく一般の人々の生活に大きな影響を及ぼすことがあるのだ。
たとえば、シエラ山脈の積雪は、カリフォルニア州の地下水のおよそ3分の1を供給し、ネバダ州北西部の都市や町の水需要の大部分を支えている。現地の研究者たちは、この地域全体における水供給のタイミングを当局がより正確に予測できるよう支援したいと考えている。
この話は、数年前に私がテキサス州エルパソを訪れた時の記憶を呼び起こした。私はそこで、リオグランデ川の水と減少しつつある地下水に頼って作物を育てている農家たちと話をした。春になると、コロラド州やニューメキシコ州の山々から水が流れ下り、エレファントビュート貯水池に蓄えられるのだ。ある農家は、自ら手書きで丁寧に写した貯水池の記録のページを何枚も見せてくれた。それらのしわくちゃのページは、公開データが彼の仕事にとって極めて重要であることの明確な証だった。
科学研究、特に粘り強くデータを収集する取り組みは、派手さに欠けることが多く、その重要性が見過ごされがちである。しかし予算削減が続く今、私たちは目を光らせている。なぜなら、データを失えば、変化する気候を追跡し、対処し、適応する能力が損なわれるからだ。
- 人気の記事ランキング
-
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- This Nobel Prize–winning chemist dreams of making water from thin air 空気から水を作る技術—— ノーベル賞化学者の夢、 幼少期の水汲み体験が原点
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- The paints, coatings, and chemicals making the world a cooler place 数千年前の知恵、現代に エネルギー要らずの温暖化対策
- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者
- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。