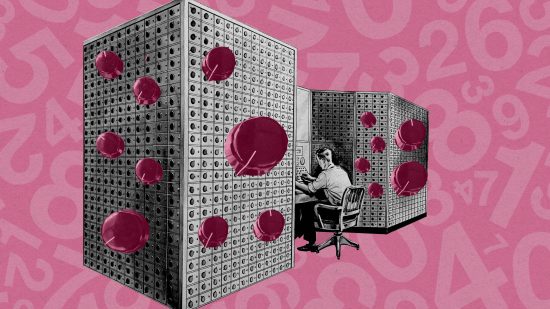マイクロソフトも賭ける
炭素除去技術「BECCS」
巨額市場に潜む「魔法」
マイクロソフトが670万トンの契約を結ぶなど、バイオマス炭素回収技術BECCSへの投資が加速している。炭素除去市場の70%を占める人気技術だが、専門家は「魔法ではない」と警告する。 by James Temple2025.10.28
- この記事の3つのポイント
-
- 大手テック企業が製紙工場での二酸化炭素回収・貯留付きバイオエネルギー(BECCS)に数百万ドル規模の投資契約を締結
- BECCSは既存インフラを活用し低コストで炭素除去を実現するが、バイオマス燃焼の炭素中立性には重大な疑問が存在
- 森林伐採促進や汚染物質排出継続のリスクがあり、真のネガティブエミッション達成には厳格な監視体制が必要
前世紀のあいだ、米国のパルプ・製紙産業の多くは、同国南東部の一角に集中していた。彼らは広大な木材林の中に工場を設置して、テーダ松、ダイオウ松、スラッシュ松の若木から繊維を剥ぎ取っていた。
現在の工場では、針葉樹を細かく砕いてパルプに加工し、残されたリグニン、使用済みの化学薬品、その他の有機物が、黒液と呼ばれる黒く粘性のある副産物を形成する。黒液は濃縮されてバイオ燃料となり、工場を稼働させる高層のボイラーを熱するために燃焼され、その過程で二酸化炭素が大気中に放出される。
マイクロソフト、JPモルガン・チェース、アルファベット、メタ(Meta)、ショッピファイ(Shopify)、ストライプ(Stripe)を含むテック企業コンソーシアムは、製紙工場の所有者に二酸化炭素除去装置の設置資金を支払うことで、少なくとも数十万トン規模の温室効果ガスを回収する数百万ドル規模の契約を最近結んだ。
回収された二酸化炭素は、地下1.6キロメートル以上の深さにある塩水帯水層にパイプで送り込まれ、そこで恒久的に隔離される予定だ。
巨大テック企業は今、炭素除去の手法である「二酸化炭素回収・貯留付きバイオエネルギー(BECCS)」に突如として大きく賭けている。この手法は、バイオマス燃料発電所、廃棄物焼却炉、バイオ燃料精製所にも適用されている。
樹木やその他の植物は光合成を通じて二酸化炭素を吸収し、これらの施設が本来大気中に放出されるはずだった排出を回収することで、理論上は放出量を上回る温室効果ガスを除去し、「ネガティブ・エミッション」を達成できる可能性がある。
二酸化炭素除去のコストを負担する企業は、その削減量を自社の排出量の相殺に利用できる。現在、BECCSは発表された炭素除去契約の約70%を占めており、その人気の理由は、既存の大規模な産業施設に追加導入できる点にある。
「コスト、市場投入までの時間、最終的な規模の可能性のバランスを考えれば、BECCSはそのすべてにおいて非常に魅力的な価値提案を示しています」。マイクロソフトのエネルギー・炭素除去担当上級部長であるブライアン・マーズは言う。マイクロソフトは、2030年までに自社の継続的な排出を相殺することを目指しており、炭素除去クレジットの最大の買い手となっている。
専門家たちは、BECCSに対するさまざまなアプローチについて多くの懸念を示している。彼らが強調する問題には、プロジェクトの気候変動対策としての効果を誇張している可能性、排出の回避と炭素除去を混同していること、そして他の形で汚染を引き起こす施設の稼働期間を延長させてしまうリスクが含まれる。また、森林伐採や農地転換に対する経済的誘因を強める可能性も指摘されている。
関係するすべての農地、森林、工場を含めて、温室効果ガスの排出源と吸収源を正確に集計すると、BECCSの多くの手法でネガティブ・エミッションを達成するのは非常に困難である——。こう指摘するのは、プリンストン大学の上級研究員ティム・サーチンガーだ。サーチンガー研究員は、こうしたプロジェクトに世界の限られた土地、作物、森林をさらに割り当てるという考え方の妥当性が揺らぐと主張している。
「私はこれを『BECCSおとり商法(BECCS and switch)』と呼んでいます」とサーチンガー研究員は語る。「ある意味では、愚行です」。
BECCSの論理
バイオマス燃料発電所において、BECCSは以下のような仕組みで機能する。
樹木は成長する過程で大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を放出しながら、炭素を樹皮、幹、枝、根に隔離する。その後、誰かがその木を伐採し、木質ペレットに加工して発電所に運ぶ。発電所ではその木材を燃やして熱や電気を生産する。
通常、このような施設では木材を燃焼する際に二酸化炭素が発生する。しかし、欧州連合(EU)および米国の規則では、木材林が持続可能な方法で管理され、関連する事業が他の規制に従っている限り、木材の燃焼は原則としてカーボンニュートラル(炭素中立)と見なされる。なぜなら、木はもともと大気中のCO₂を吸収しており、後に新たな植物が成長すれば、その排出負債は時間の経過とともに相殺されると考えられているからだ。
仮に同じ発電所が、木材燃焼によって発生する温室効果ガスの大部分を回収し、それを地下に圧入するようになれば、そのプロセスはカーボンニュートラルからカーボンネガティブへと移行する可能性がある。
しかしサーチンガー研究員によれば、バイオマスをカーボンニュートラルと見なすそもそもの前提には重大な欠陥がある。それは、このプロセス全体で他の手段によって排出される温室効果ガスが十分に考慮されていないためである。
とりわけ、正確な分析には、以下のような問いを立てなければならない。植物が取り除かれた後、林床に残された根や枝が分解されてどれだけの炭素が放出されるのか? バイオマスの伐採・収集・輸送の過程で、どれだけの化石燃料が使用されたのか? 木材を木質ペレットに加工し、それを別の場所に輸送する過程で、どれだけの温室効果ガスが排出されたのか? そして、伐採されなければ炭素を吸収し続けていたであろう植物が、再び成長するまでにどれだけの時間がかかるのか?
「木を伐採しているかぎり、ネガティブ・エミッションの実現は基本的に不可能です」とサーチンガー研究員は指摘する。
バイオマスやそれを原料とするバイオ燃料の燃焼によっては、粒子状物質、揮発性有機化合物、二酸化硫黄、一酸化炭素など、人の健康に有害な他の汚染物質も発生する可能性がある。
ある施設で二酸化炭素の排出を抑えるには、とりわけ二酸化硫黄など、他の汚染物質も捕集する必要があるかもしれない。しかし、ノートルダム大学で持続可能なエネルギー政策を研究するエミリー・グルバート准教授は、煙突から排出される他の汚染物質すべてが除去されるとは限らないと指摘する。グルバート准教授は、炭素管理と化石燃料からの脱却に関する専門家である。
需要を促進する
バイオマスによってエネルギーを生成し、炭素を吸収できるかもしれないという考えが生まれたのは、数十年前にさかのぼる。しかし、地球の気温と排出量の双方が上昇し続けるなかで、気候モデルの研究者たちは、地球がより深刻な温暖化の閾値を超えてしまうのを防ぐには、BECCSや他のタイプの炭素除去手法の利用拡大が必要になることを明らかにした。
2022年の国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によれば、産業革命前からの気温上昇を2℃以内に抑えるには、大幅な排出削減に加えて、2050年までに年間110億トン、2100年までには年間200億トンの二酸化炭素を回収する必要がある可能性がある。そして、私たちがこの閾値を超えてしまう可能性はますます高まっている。
こうした気候危機に関する重大な警鐘が、大気中から二酸化炭素を除去する技術への関心と投資を加速させた。企業が次々と現れ、海藻を沈める、バイオマスを地中に埋設する、二酸化炭素を直接回収する施設(DAC)を開発する …
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している