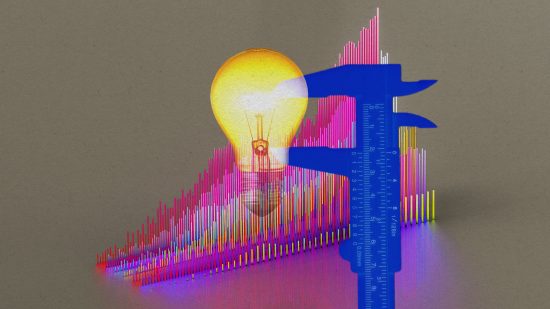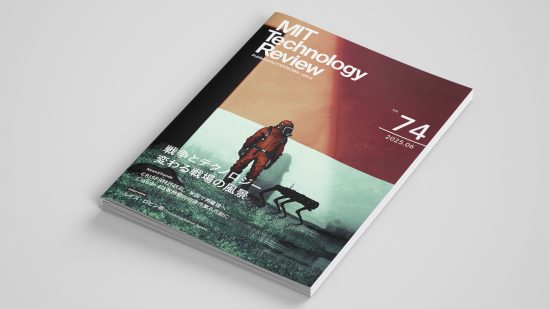フラッシュ2022年9月8日
-
「人工気象室」で気候変動に強い農作物を開発へ=農研機構
by MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の研究チームが、気温をはじめとする気候変動に伴うさまざま環境の変化が農作物に与える影響を再現して解析できる「ロボティクス人工気象室」を開発した。人工知能(AI)やスーパーコンピューターといった最先端技術を活用したのが特徴で、気候変動に強い新たな品種や栽培方法の開発につなげたいとしている。
ロボティクス人工気象室は、作物の栽培環境を精密に再現あるいは模擬できる「栽培環境エミュレーター」と呼ばれる人工気象室本体と、作物の大きさや色などの形質情報を収集できる「ロボット計測装置」で構成される。人工気象室本体は縦横約1.7メートル、高さ約1.9メートル。上部に設置した高出力のLEDで光や紫外線量を調節し、温度は5~35℃、湿度は最大90%まで上げることが可能で、二酸化炭素濃度を高めることもできる。ロボット計測装置は、複数のカメラを作物に平行に移動させて撮影し、作物の形質情報を自動収集する。
ロボティクス人工気象室で取得したデータは高速ネットワークを通じて農研機構が保有するスパコン「紫峰」に転送。さまざまな気候変動による生育環境の変化が及ぼす熟成度や成長過程への影響をAIにより解析することで、任意の環境における作物の性能(収穫時期、収量、品質など)を精密に推定し、適切な栽培方法や品種育成に関する情報を得られるという。ロボティクス人工気象室は外部からの遠隔操作による使用も可能で、民間企業や大学などの研究機関との共同研究の基盤としても利用できる。
(中條)
-
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット
- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差