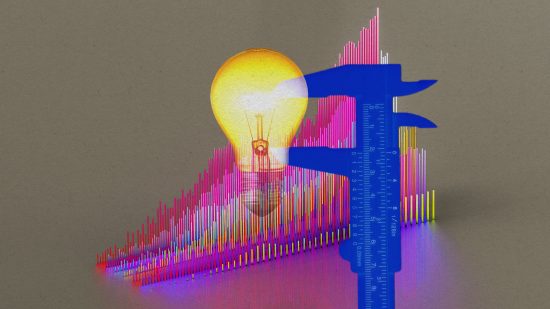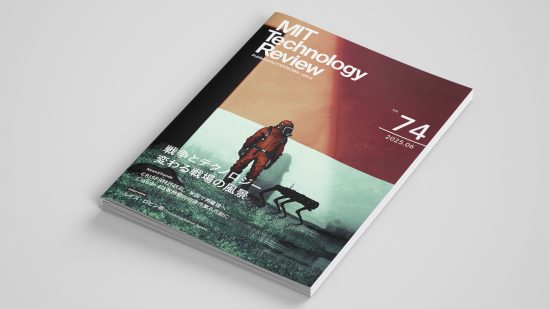フラッシュ2022年10月6日
-
太平洋・大西洋の大気微粒子分布をモデルで再現、名大が初
by MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]名古屋大学の研究チームは、大気微粒子が生成・成長するプロセスを扱う気候モデルにおいて、大気微粒子の数濃度・粒径分布の推定精度を大きく向上させることに成功。雲凝結核(雲粒の核となる大気微粒子)数の推定で、多くの気候モデルでは十分に考慮されていない大気微粒子の生成・成長プロセスを考慮する重要性を解明した。
同チームは、雲凝結核の数濃度を推定するにあたり、「新粒子生成」と呼ばれる、数ナノメートル程度の非常に小さな粒子が大気生成するプロセスや、「二次有機エアロゾル」の生成によってエアロゾルの粒径が大きくなるプロセスの両方を詳細にシミュレーションできるモデルを作成。太平洋上・大西洋などの陸から離れた遠隔域で実施された広域航空機観測で得られたエアロゾルのエアロゾルの数濃度と粒径分布、雲凝結核数、有機エアロゾルの質量濃度の空間分布を、世界で初めてシミュレーションで再現した。
さらに、これらの結果から、大気中で数ナノメートル程度の非常に小さい粒子が生成され、二次有機エアロゾル生成プロセスによって雲凝結核にまで成長する過程が、遠隔域における雲凝結核数の推定において、極めて重要な役割を果たすことを明らかにした。
大気微粒子が雲凝結核として働いて雲の特性を変化させる効果は、気候変動予測において特に不確実性が大きい。今回の成果は、気候の将来変化や地球温暖化の予測の高精度化につながる重要な知見となることが期待される。研究成果は、地球物理学分野の国際学術誌ジオフィジカル・リサーチ・レターズ(Geophysical Research Letters)に2022年9月28日付けで掲載された。
(中條)
-
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット
- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差