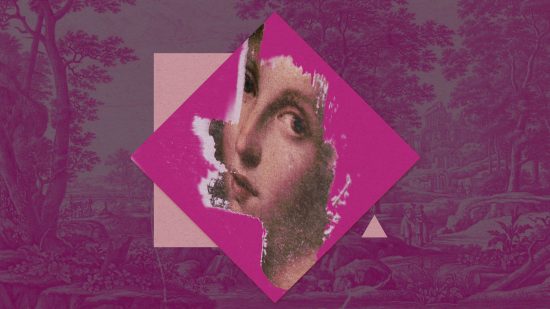フラッシュ2023年6月18日
-
NEDO、全固体リチウムイオン電池実用化へ材料評価基盤に投資
by MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、全固体リチウムイオン電池の早期実用化に向けて、「次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発」事業を始動した。事業期間は2023年度から2027年度の5年間の予定で、2023年度の予算は18億円を用意する。これまでの研究開発事業の成果を基に、全固体リチウムイオン電池を早期に実用化し、日本国内の蓄電池、蓄電池素材産業の競争力強化を狙う。
NEDOはこれまで、「先進・革新蓄電池材料評価技術開発(第1期)」(2013年度から2017年度)と同第2期(2018年度から2022年度)の2つの事業で全固体リチウムイオン電池の開発に向けて投資してきた。上述の事業の第1期では、全固体リチウムイオン電池の基軸材料となる硫化物固体電解質などの特性評価に使用する研究室レベルの標準電池モデルのプロトタイプを開発し、第2期では、硫化物系全固体リチウムイオン電池の標準電池モデルを開発、材料評価の基礎的基盤を構築した。さらに、一般的なリチウムイオン電池に迫るエネルギー密度(450Wh/L)を中型セルサイズで実現した。
今回の事業では、固体電解質や活物質との界面(固固界面)形成と維持を技術課題として掲げ、「材料評価基盤技術開発」「全固体LIB特有の現象・機構解明」「電極・セル要素技術開発」に取り組む。材料評価基盤技術開発では、標準電池モデルなど、次世代全固体リチウムイオン電池材料の評価基盤技術を開発する。新材料の特質を的確に評価し、その結果を要素技術開発に詳細にフィードバックすることで、材料開発の促進と適用までの期間短縮を目指す。
今回の事業には、自動車、蓄電池、材料メーカーなど33法人が組合員として参加する技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センターのほか、産業技術総合研究所や物質・材料研究機構などが参加する。
(笹田)
-
- 人気の記事ランキング
-
- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- Don’t let hype about AI agents get ahead of reality 期待先行のAIエージェント、誇大宣伝で「バブル崩壊」のリスク