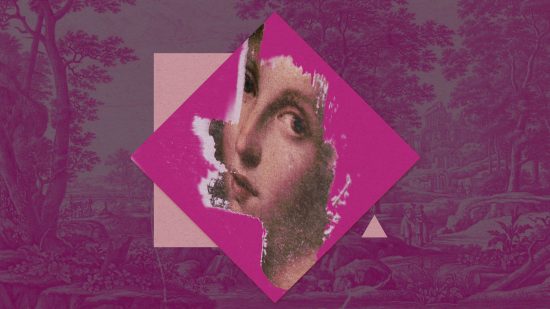宇宙の手前で漂流し続ける
米軍の次世代「成層圏気球」
米軍の研究開発機関であるDARPAが成層圏気球(高高度気球)を開発中だ。新センサーを使って宇宙空間手前の定点で無期限に漂えるこの気球は、本来の軍事目的以外にも応用できそうだ。 by David Hambling2018.12.04
気球を地球の空高く、無期限に漂わせ続けるというアイデアは魅力的だ。こうした成層圏気球は太陽光発電のおかげで、まるで低コストの人工衛星のように、宇宙との境界線上で遠隔地や被災地に通信手段を提供したり、ハリケーンを追跡したり、海上の汚染を監視したりできるようになるだろう。さらに将来、成層圏気球が宇宙の手前まで観光客を案内し、地球の丸いカーブを見せられる日が来るかもしれない。
成層圏気球は決して目新しいアイデアではない。実際、初期の成層圏気球は1950年代に米国航空宇宙局(NASA)が飛ばしており、今でも科学的任務に使用されている。また、グーグルの親会社アルファベットが所有する「プロジェクト・ルーン(Project Loon)」 は、ハリケーン「マリア」で被災したプエルトリコに気球を飛ばし、モバイル通信の提供に成功している。
しかし、成層圏気球には大きな問題がある。現行の気球は風と共に移動し、定点に留まれるのが1回の飛行につき数日間だけなのだ。成層圏の高度、地上から約1万8300メートル地点では、風が様々な高度で異なる向きに吹く。理論上は、単に高度を上下すれば、望ましい方向に吹く風を見つけられるはずだ。しかし、機械学習とより良質なデータを使って改善が進められているにも関わらず、その進捗は依然としてゆるやかなのだ。
米軍の研究部門である米国国防先端研究計画局(DARPA)は、この問題を解決する可能性があると考えている。現在、DARPAは風センサーをテストしているところだ。DARPAが開発中の「ALTA(Adaptable Lighter-Than-Air balloon:調整可能な空気より軽い気球)」プログラムのデバイスは、センサーを使って遠距離から風速と風向を検知でき、定点に留ま …
- 人気の記事ランキング
-
- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- Don’t let hype about AI agents get ahead of reality 期待先行のAIエージェント、誇大宣伝で「バブル崩壊」のリスク