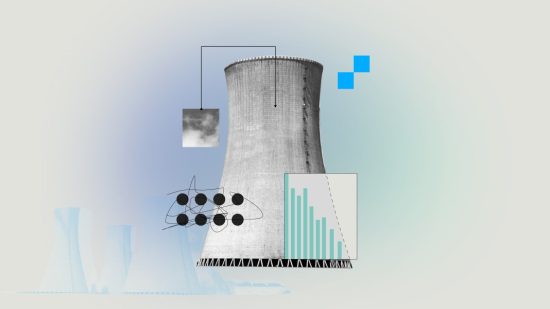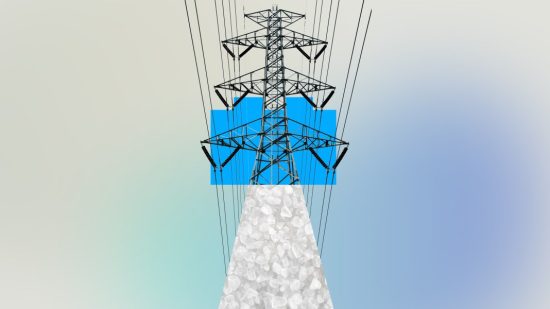「洋上風力で死ぬ」根拠なし
クジラ検死の専門家、
死因調査の現場を語る
米国東海岸で相次ぐクジラの死。トランプ政権は洋上風力を犯人視するが、「エビデンスはひとつもない」と反論するのは、実際に検死にあたっている野生動物専門の研究者だ。 by Casey Crownhart2025.11.18
- この記事の3つのポイント
-
- 米国東海岸でクジラの大量死が発生し、トランプ政権が洋上風力発電を原因とする政治的主張を展開している
- 科学者らの詳細な検死調査では船舶衝突や漁具絡まり等が主因で、風力発電との関連は確認されていない
- 研究資金削減と誤情報拡散により、クジラ死因究明の科学的取り組みは困難に直面している
クジラは死ぬと、急速に腐敗が進行することが多い。岸に打ち上げられると、数時間以内に腐敗プロセスが始まる。種によっては脂肪層が15センチを超えることもあり、この脂肪が断熱層として内部の熱を閉じ込めるため、内臓がドロドロに崩れてしまうのだ。
それは、ジェニファー・ブラッドグッドの仕事を非常に困難にすることもある。ニューヨーク州とコーネル大学野生動物健康研究所(Cornell Wildlife Health Lab)の野生動物専門獣医師であるブラッドグッド教授は、クジラの「ネクロプシー(動物の検死)」の専門家だ。彼女は、この巨大な哺乳類の死因を示す重要な手がかりを逃さないためには、できるだけ早く検査を開始することが最善であると知っている。
クジラの死は現在、重大な影響をもたらす政治的争点の火種にもなっており、こうした死因調査の重要性が増している。現在、大西洋では大量のクジラが相次いで死亡する「異常死亡事象」が3例発生し、専門家が通常とは異なる死亡の集中を確認している。これについて、米国の共和党議員、有力な保守系シンクタンク、さらには風力発電の長年の批判者であるドナルド・トランプ大統領が、洋上風力発電所がその原因であるという疑わしい主張を展開している。
こうした一連の主張の根拠となっているのが、半ば陰謀論的な風力発電批判である。反風力発電を掲げる一部の団体は、風力発電所の建設予定地を測量する際に使用される調査技術がクジラの健康を害している可能性があると主張している。また、稼働中の風力タービンが発する騒音が、クジラのコミュニケーションや回遊のための位置感覚を妨げているという説もある。トランプ大統領は1月に「あの風車がクジラを狂わせているのは明らか」と発言している。
この1年、ワシントンは、かつて国内で成長を続けていたクリーンエネルギー・インフラの重要な一角を占める洋上風力発電に対して攻撃を強めてきた。そして、その正当化のための公式な理由のひとつとして、風力タービンがもたらす脅威が挙げられている。トランプ政権は、新規プロジェクトのリースや許可を停止し、完成間近だった大規模風力発電所の工事中止を命じ、さらに業界支援のための港湾整備資金6億ドル超の拠出を取りやめた。
しかし、クジラの死は風力タービンが原因だとするいかなる主張も、巨大な風力タービンが海上に設置されるずっと以前からクジラが浜辺に打ち上げられていたという事実を無視している。クジラの座礁はこれまでも常に起こってきた自然現象である。そして、科学者たちのコンセンサスは明確だ。洋上風力発電所が近年のクジラの死亡増加の原因であるというエビデンスは存在しない。
クジラの生態や死に関しては、まだ多くの点が未解明である。しかし専門家たちは、米国東海岸だけでも毎年数十件におよぶ詳細な(そして時に残酷な)調査を実施している。これらの異常死亡事象に関するデータを見ると、ザトウクジラやタイセイヨウセミクジラの多くは船舶との衝突や漁具への絡まりといった人間活動によって命を落としていることがわかる。実際、ブラッドグッド教授の経験では、ネクロプシーが可能な状態にあるザトウクジラの約半数に、船舶衝突やその他の人間の活動の関わりの痕跡が見られるという。また、ミンククジラはブルセラ症と呼ばれる一般的な感染症によって死亡しているケースが多く、ブラッドグッド教授も実際にそれを確認している。
「クジラが座礁すると、その対応と死因の究明には膨大な労力が必要になります」とブラッドグッド教授は語る。「多くの人が現場に赴き、何が起こって …
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?