MITテクノロジーレビュー[日本版]が2019年11月29日に開催した「Future of Society Conference 2019」。「宇宙ビジネスの時代」をテーマに開催された本カンファレンスでは、東京大学大学院工学系研究科准教授/JAXA宇宙科学研究所教授の宇宙工学者・船瀬龍氏が登壇した。船瀬氏は東京大学在学中から超小型人工衛星の研究・開発に携わり、2003年6月に重量わずか1キログラムの超小型衛星であるキューブサットの打ち上げを世界で初めて成功させた。16年経った現在も衛星は運用中で、地球を周回している。また2012年には、これも世界初となる50キログラム級の深宇宙探査機PROCYON(プロキオン)のプロジェクトに携わった。
現在では大企業からベンチャーまで、多くの民間企業が人工衛星を打ち上げるようになり、衛星利用ビジネスが活発化している。この流れの1つの鍵となっているのが、超小型衛星の誕生と進化にある。
▼【有料会員限定】有料会員(Insider Online)としてログインすると、本講演(約30分間)の動画を視聴できます。
人工衛星の大型化の流れを超小型衛星が変えた
「従来、人工衛星といえば、重さ何トンという規模感でした。対して超小型衛星がどれくらい小さいかというと、もっとも小さいものだと1辺が10センチメートル程度の立方体で、手のひらに乗るサイズです」と船瀬氏は話す。
もともと宇宙開発初期の人工衛星は100キログラムにも満たない小さく軽いものだった。しかし1990年代に入ると、衛星は高機能な機能を搭載するため急速に大型化し、2000年頃には4トン級の衛星も出てきた。衛星の開発製造コストは1基あたり数百億円規模に達し、1つのプロジェクトに5年から10年の歳月を要するようになった。
「そうすると失敗が許されなくなります。設計が保守的になり、この機器が壊れると困るから予備を載せて打ち上げよう、といった冗長化によりますます衛星が重くなる。そして重くなると、さらに打ち上げのコストが高くなる。しかも、一度プロジェクトが成功すると、次はより高機能に、より高度なミッションを──ということになるわけです」(船瀬氏)。
大型化もいずれ限界を迎える。それでも、大型化の悪循環を抜け出そうという技術的な試みはなされるわけだが、5年から10年というスパンでは新しい技術を開発して宇宙で試すサイクルも遅々として回せない。そこへ登場したのが超小型衛星だった。
「超小型衛星は、登場した当初はいわゆる低スペック・低性能でした。私が手がけているのは50キログラム以下の規模のもので、超小型、超軽量。衛星1基あたりの開発コストは数億〜数十億円でつくれるようになりました」(船瀬氏)。
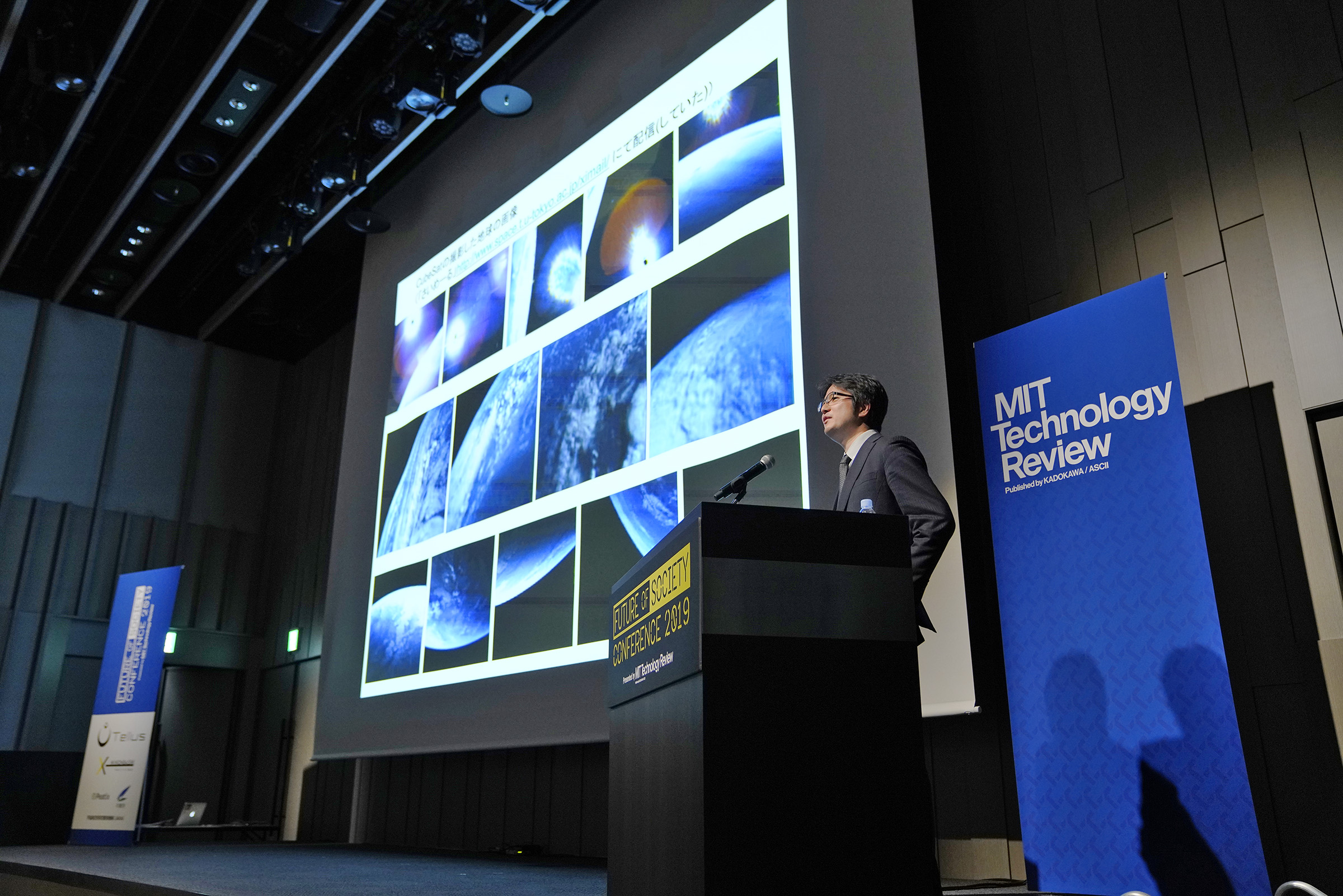
「失敗してもいい」というパラダイムシフト
超小型衛星は、人工衛星に対する考え方の転換の産物だともいえる。
たとえば、部品の品質・信頼性。従来は、宇宙の厳しい環境でも確実に動くもの、よく試験されたものを組み合わせ、試作品を丁寧につくり上げていた。その後も入念に試験をしてから打ち上げていたものだった。しかしその結果、衛星は大きく高価なものになっていた。一方、超小型衛星は、一般に流通している「普通の」部品をいかに使うかという観点で開発された結果、低コストで済むようになる。
もう一つ、発想の転換として大きなポイントとなるのが、「壊れてもいい」という考え方だ。数百億円もかけてつくる大きな衛星は、高価だからこそ「絶対に壊れてはいけない」ことが求められる。そのため、よく試験された部品を使わなくてはいけなくなる。しかし、超小型衛星であれば、たとえば大きな衛星を1基打ち上げる代わりに10機打ち上げることも可能で、「信頼性」をあきらめることができる。一品モノの試作品を時間をかけて磨くのではなく、早く、安くつくることで頻度高く打ち上げ、試行錯誤のサイクルを早く回すことが可能になる。
「超小型衛星は、1回のミッションで得られる成果は小さくなりますが、それ以上に低コスト化の効果が上回ります。そうすると、代わりに回数をこなすことによって、成果の総量で1回の大きな衛星の打ち上げの成果を上回ろうという発想ができる」。
超小型衛星の新たなフロンティア
船瀬氏ら東大の研究チームが世界初の超小型衛星打ち上げを成功させて以降、世界でも数多く超小型衛星が打ち上げられているが、超小型衛星の将来に目を向けた時、「深宇宙探査が1つの新しいフロンティアになる」という。
深宇宙探査機が、地球を周回する衛星と異なる点の1つに通信の問題がある。地球を遠く離れるからだ。また、軌道決定の技術も課題となる。地球の周りではGPSを利用できるため、自機の位置を把握することは比較的簡単だが、深宇宙探査となるとそうはいかない。場所を把握し、目的地へ到達するための軌道を制御する必要がある。
「これを実証しようとしたのが、東京大学とJAXAで取り組んだPROCYON(プロキオン)のプロジェクトです。2014年にはやぶさ2と一緒に打ち上げ、通信系では世界最高性能の技術を実証しました。また、深宇宙に行かなくては見えない地球の周りの水素大気の観測、彗星から吹き出す水の観測にも成功しました。何より重要なのは、50キログラム級の超小型衛星で深宇宙探査にトライしてこれだけの成果をあげたこと。地球の周りに留まっていた超小型衛星が、深宇宙へ一歩踏み出したことが大きな成果です」と船瀬氏は話す。
現在、この試みは世界に広がり、2020年にはアメリカが開発中のスペース・ローンチ・システム(SLS)によって、13機の超小型衛星が月に向かって打ち上げられる予定だ。ほかにも、火星を目指すもの、小惑星に向かうもの、惑星間の空間でバイオ実験を行なうものなど、さまざまな超小型衛星が深宇宙を目指している。
「将来、人が月面に行って活動するようになった時は、月へ物資を運ぶために中継地点がつくられることになるでしょう。そうすると、専用のロケットを使わずとも、物資と一緒に超小型衛星を運べば、その中継地点を起点にさらなるミッションが展開できるようになる。今はアカデミックベースでの研究開発の段階ですが、いろいろな使い方が見いだされて、深宇宙空間もビジネスの場になっていくと面白い時代になる」と船瀬氏は語った。
- 人気の記事ランキング
-
- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- Don’t let hype about AI agents get ahead of reality 期待先行のAIエージェント、誇大宣伝で「バブル崩壊」のリスク
| タグ |
|---|
- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者
- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。







