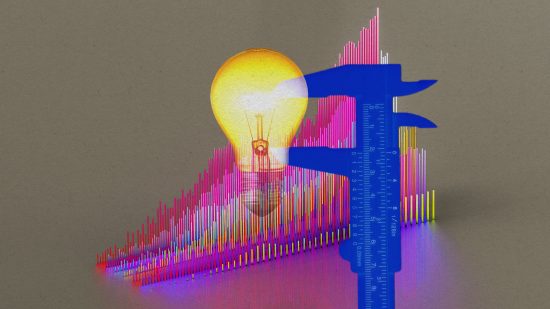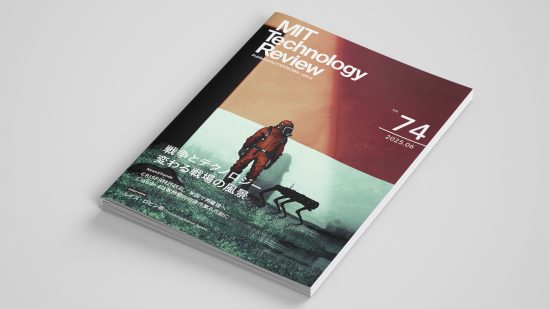宇井吉美:AIセンサーで「誰もが介護したくなる」社会を目指す起業家
「誰もが介護したくなる社会」。「排泄」をにおいで検知するデバイスを開発したアバ(aba)の創業者、宇井吉美が目指すのは、そんな未来だ。 by Noriko Egashira2022.03.18
2018年に経済産業省が公表した試算によれば、2015年に620万人だった要介護認定者数は、2035年には960万人に増え、対して介護職員は68万人も不足すると見込まれている。介護職員の不足は、世界一の高齢社会である日本が、世界に先駆けて直面している難題だ。

- この記事はマガジン「世界を変えるイノベーター50人」に収録されています。 マガジンの紹介
背景には「介護職は大変」というイメージがつきまとっていることが一因にある。そうした中、「誰もが介護したくなる」社会の実現を目指し、テクノロジーの力で介護職員の負担を減らして、「かっこいい仕事」にアップデートしようと奮闘しているのがアバ(aba)の創業者・最高経営責任者(CEO)の宇井吉美である。
宇井は、3大介護(食事・入浴・排泄の介助)の中でも、最も負担が重いとされる「排泄」をセンサーで検知するデバイスを開発。大学時代にアバを起業し、大手介護ベッドメーカーのパラマウントベッドと共同研究を重ね、「ヘルプパッド(Helppad)」として8年越しで製品化にこぎつけた。ヘルプパッドはシーツのようにベッドに敷いて、その上で寝ている要介護者が排泄すると、センサーがにおいを検知して介護職員に通知するシステムだ。おむつを開けずに排泄したことが分かるため、介護職員の負担が減り、要介護者もより良い介護が受けられるようになる。さらに、記録されたデータを分析することで排泄パターンを導き出し、排泄の予測も可能だ。これまで約80施設に100台ほどを納入し、「おむつ交換回数が減った」「トイレの誘導に成功した」といった声が寄せられている。
「おむつは1日に何度も交換する必要があるうえ、後始末に手間がかかります。漏れていたらさらに大変で、介護職員にとってはかなりの重労働。でも、おむつを開けてみたら排泄されていない“空振り”の場合も多く、徒労感に襲われることもあります。そんな介護職員の精神的・肉体的な負担を減らしたかったのです」
実は従来から、排泄を検知するにおいセンサーは製品化されていた。ただ、それらはおむつに貼るタイプのものばかり。宇井が開発した排泄センサーが画期的なのは、おむつに貼るのではなくベッドに敷くシートタイプであるため、要介護者がセンサーを“装着”しなくて済むことだった。
「普通に考えれば、おむつに貼るほうがにおいを感知しやすいです。ただ、介護が生活支援の場であることを考えると、“からだに機械を付けたくない”という思いが、現場の介護職員さんには強くあります。また、そもそもおむつ交換時、汚れたおむつから外したセンサーをどこに置くか、といった現場のオペレーション上の困難さもあります」
介護職員の思いやオペレーションを考えたとき、おむつに貼るタイプの製品はそぐわない――現場で介護する人々の声に耳を傾けた宇井だからこそ、導き出せた結論だった。「最後の最後まで、現場のラストワンマイルを詰める。それが私たちの強み」と宇井は言う。現場に寄り添う姿勢は、価格設定にもうかがえる。センサー自体は、エアコンや空気清浄機などに使われる汎用品を採用し、それにより安価に提供できるようにしている。「ハードウェア自体は革新的ではないんです」と宇井はさらりと言う。では、技術的な強みはどこにあるのか。
「“排泄物のにおい”を検知するアルゴリズムを開発したことです。汎用センサーでは排泄だけでなく、食品や消臭剤など排泄以外のにおいにも反応してしまいます。そこを切り分けるために、排泄時のセンサーの反応データを大量に取り、時系列で変化を見てパターンを解析し、アルゴリズムのパラメーターをチューニングし続けました。逆に言うと、排泄物のにおいに反応するよう、センサー側を開発してもいいわけですが、そうするとコストがどんどん上がってしまう。それを避けるためアルゴリズムを磨き上げました」
…
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット
- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差