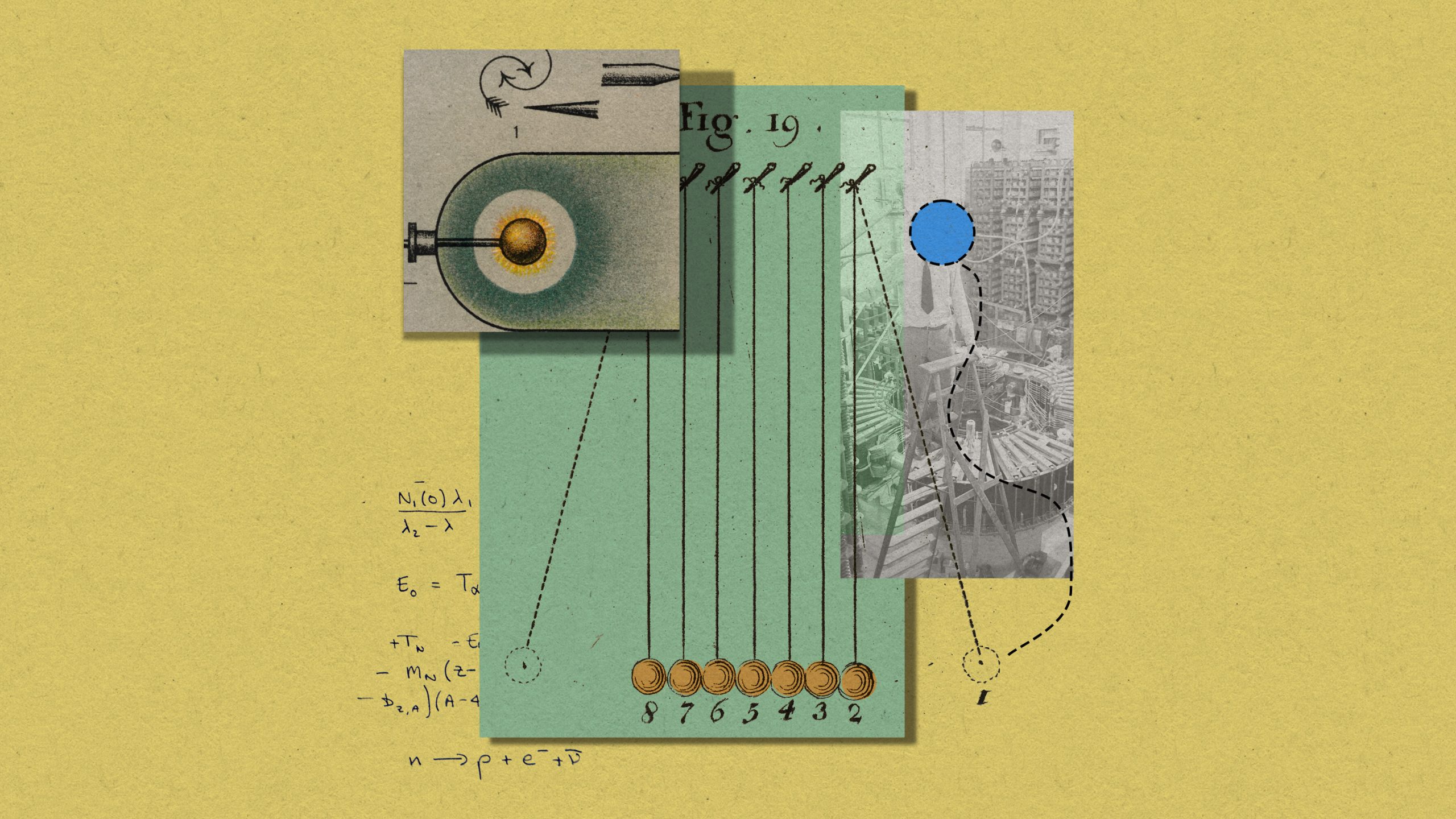物理学界で繰り返される研究不正、再発防止には何が必要か
悪質な研究不正事件を受けて、米国の物理学界はこの20年の間、再発防止に取り組んできた。だが繰り返される不正に対し、まだやるべきことが残っている。 by Michael Marder2024.08.21
- この記事の3つのポイント
-
- 物理学界では捏造や不正などの倫理的問題が後を絶たない
- 米国物理学会は倫理教育の充実化や声明の強化などの対策を進めてきた
- 不安を打ち明けられる「信頼ネットワーク」が倫理問題の解決には重要である
2024年4月、ネイチャー誌はロチェスター大学助教授である物理学者ランガ・ディアスの主張に関する詳細な調査結果を発表した。ディアス助教授は同誌に掲載され話題を呼んだ2本の論文で、室温超伝導を発見したと主張していた。しかし、これら2本の論文は捏造データに基づいていたことが判明し、のちに撤回された。ディアス助教授の研究グループは他にも関連する物理現象について記した論文を公表していたが、これらの論文もフィジカル・レビュー・レターズ(Physical Review Letters)誌に掲載された分と合わせて、同様に撤回となった。
この研究がトップ・ジャーナルに掲ってしまった理由はいくつか考えられる。まず査読者は、論文に載っているデータは信頼できるものであり、全面的に操作されたものではないという前提で査読する。そして、ディアス助教授の論文に記してあった実験では、非常に高い圧力をかける必要があるが、ほかのラボでは容易に再現できなかった。物理学コミュニティが当然のように示した反応の中には、「どうしてこんなことを見過ごしてしまったんだ?」というものがあった。だが、こうも考えるべきだった。「またか!」
残念なことに、物理学者のこのようなふるまいは、少なくとも20年前から知られていたのだ。数々の不正を受けて、米国物理学会(APS:American Physical Society)は捏造、改ざん、盗用、嫌がらせが発生する背景を調査し、問題解決のための体制づくりに取り組んできた。APSの取り組みは、物理学界における行動指針の確立に役立ったが、倫理規定違反はいまだに重大な問題として残っている。
2003年、物理学における悪名高い2件の計画的な不正を受けて(1件は驚くほど今回の例に酷似していた)、APSは倫理タスクフォースを設立した。タスクフォースは物理学研究者が受けている倫理研修の内容や、物理学界におけるさまざまな倫理問題への意識について調査した。調査結果の中でも最も衝撃的だったのは、APSの「ジュニア・メンバー」、すなわち過去3年以内に博士号を取得した会員を対象とした調査の結果だった。ジュニア・メンバーのおよそ半分が、自身が目撃した、または加担を強いられた数々の倫理規定違反について、重大な懸念を示していると回答したのだ。この調査結果を報じた2004年のフィジクス・トゥデイ(Physics Today)誌の記事には、データの改ざん、不正、盗用など、さまざまな倫理規定違反(連邦政府が定める研究不正行為)が挙げられている。また、いじめやセクシャル・ハラスメントの重大な告発も白日のもとにさらされた。調査結果によれば、物理学界での倫理教育はうわべを取り繕うだけのものといった状況だった。
公表された調査結果、また物理学界内部での多くの議論を受けて、APSは部下に敬意を持って接するように求める倫理 …
- 人気の記事ランキング
-
- Inside the race to find GPS alternatives GPSに代わる選択肢を、 地球低軌道で100倍強い 次世代測位システム
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Trajectory of U35 Innovators: Yoichi Ochiai 落合陽一:「デジタルネイチャー」の表現者が万博に込めた思い
- Cybersecurity’s global alarm system is breaking down 脆弱性データベースの危機、 「米国頼み」の脆弱性が露呈
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機