
勝又秀一:量子時代の安全を守る「耐量子計算機暗号」研究の開拓者
PQシールド(PQShield)の暗号研究者、勝又秀一は、耐量子計算機暗号を開発を進めると時に社会実装への道筋を構想し、量子コンピューター時代の情報セキュリティインフラを築こうとしている。 by Yasuhiro Hatabe2025.03.12
暗号研究者の勝又秀一は、セキュア・メッセージング・プロトコル(SMP)「Signal(シグナル)プロトコル」の耐量子計算機安全化に成功したとして、2022年に「Innovators Under 35 Japan (35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。
当時は、産業技術総合研究所(産総研)での研究を主としつつ、英国のサイバーセキュリティ企業「PQシールド」でもコンサルタント契約で働いていた。現在は産総研を退職し、PQシールドの暗号技術主任研究員として働く。「スタートアップらしい、社会的にインパクトが強い研究にシフトしています」と勝又は近況を語る。
U35に選出されてからの約2年間でSignalプロトコルの研究開発は大きく進展し、「2025年夏頃には新方式をデプロイするところまで来ている」という。Signalプロトコルはオープンソースであり、メッセージング・アプリのSignalだけでなく、グーグルの音声通信やメタのMessenger(メッセンジャー)、WhatsApp(ワッツアップ)でもサブプロトコルとして使われている。勝又が開発した暗号技術が今後、それらに組み込まれる可能性は高く、影響する範囲は非常に大きい。
耐量子計算機暗号への移行は世界で加速
量子コンピューターの実用化へ向けた研究開発が世界的に加速する中、現在広く使われている暗号方式の危殆(きたい)化が懸念されている。従来のコンピューターでは解読に膨大な時間がかかるため安全だとみなされてきた現行の暗号が、量子コンピューターによって破られてしまう恐れがあるからだ。
「アカデミアでは以前から言われていたことですが、2020年頃から一般にも少しずつ知られるにようになってきました。背景には、NIST(米国国立標準技術研究所)が耐量子計算機暗号アルゴリズムを公募し、コンペティションを段階的に進めていたこと、米国の国家安全保障システムや重要インフラを保護するため、連邦政府機関に対して耐量子計算機暗号技術への移行準備を指示する大統領令が出されたことなどがあります」。
そして2022年7月、NISTは耐量子計算機暗号の標準化方式を決定し、2024年8月には連邦情報処理規格(FIPS)に沿って書き直した「最終版」を公開した。「こうした背景から、海外ではようやく耐量子計算機暗号への移行が本格化しようとしています」。
量子コンピューターの実用化は社会に便益をもたらす点で期待されているものの、情報セキュリティの観点で言えば“脅威”である。「いつ来るか、何が起きるか分からない大地震のようなものです。備えは早めに進めておく必要があります」と勝又は話す。量子コンピューターの実現時期は専門家の間でも意見が分かれるが、「現在使われている暗号が、今後5~10年というスパンで安全でなくなるということはないと、我々の中で信じられています」。
とはいえ悠長に構えるわけにはいかない。今のうちに暗号化されたデータを収集しておいて、将来、量子コンピューターが実現したときに解読しようとする「Harvest now, decrypt later」の恐れがあるからだ。政府機関が取り扱うような機密性が高い情報は、数十年単位で安全性を担保しなければならない。そのため、2030年までには耐量子計算機暗号で安全性を高めようという動きが進んでいるわけだ。
ひらめきと問題を解く“突破力”
中高生の頃から数学が好きで、誰に教わるでもなく図書館で数学の専門書をよく読んでいたという勝又。1つの問題を2〜3時間ただ眺めていると、“ひらめき”が起こる瞬間があるという。「難問になると1カ月くらい解けないこともあります。いったん寝かせて、また問題に戻りということを繰り返して、最終的に問題が解ける。そうやって問題を解く力を、私は勝手に“突破力”と呼んでいます」。
将来は数学者になりたいと思い、東京大学工学部計数工学科に進んだが、「純粋数学の世界は尋常ではない“突破力”が必要。自分にはやり切る力はない」と気づき、応用数学へシフトした。修士課程では人工知能(AI)、機械学習を研究するも「プログラミングが性に合わない」。博士課程では数学の中でも最も好きな「行列」が多く使われているという理由で、暗号の分野を選んだ。
現在広く使われている暗号方式である「RSA暗号」は、桁数が大きい合成数の素因数分解が従来のコンピューターでは現実的な時間で解けないことが安全性の根拠になっている。耐量子計算機暗号も理屈は同じで、「量子コンピューターをもってしても」解くのに膨大な時間がかかるという事実が、安全性を担保する。そこで使われる数学的な問題はいくつかあるが、代表格である「格子問題」には行列が多く使われる。
「修士の頃は、量子コンピューターも暗号もよく知らなかった」という勝又だが、博士課程時代に留学したオックスフォード大学でのワークショップで、当時まだ起業前だった現PQシールドのCEOであるアリ・エル・カーファラーニと出会った。交流を深める中で起業の意思を聞き、そこで初めて耐量子計算機暗号の可能性に気づいたのだという。
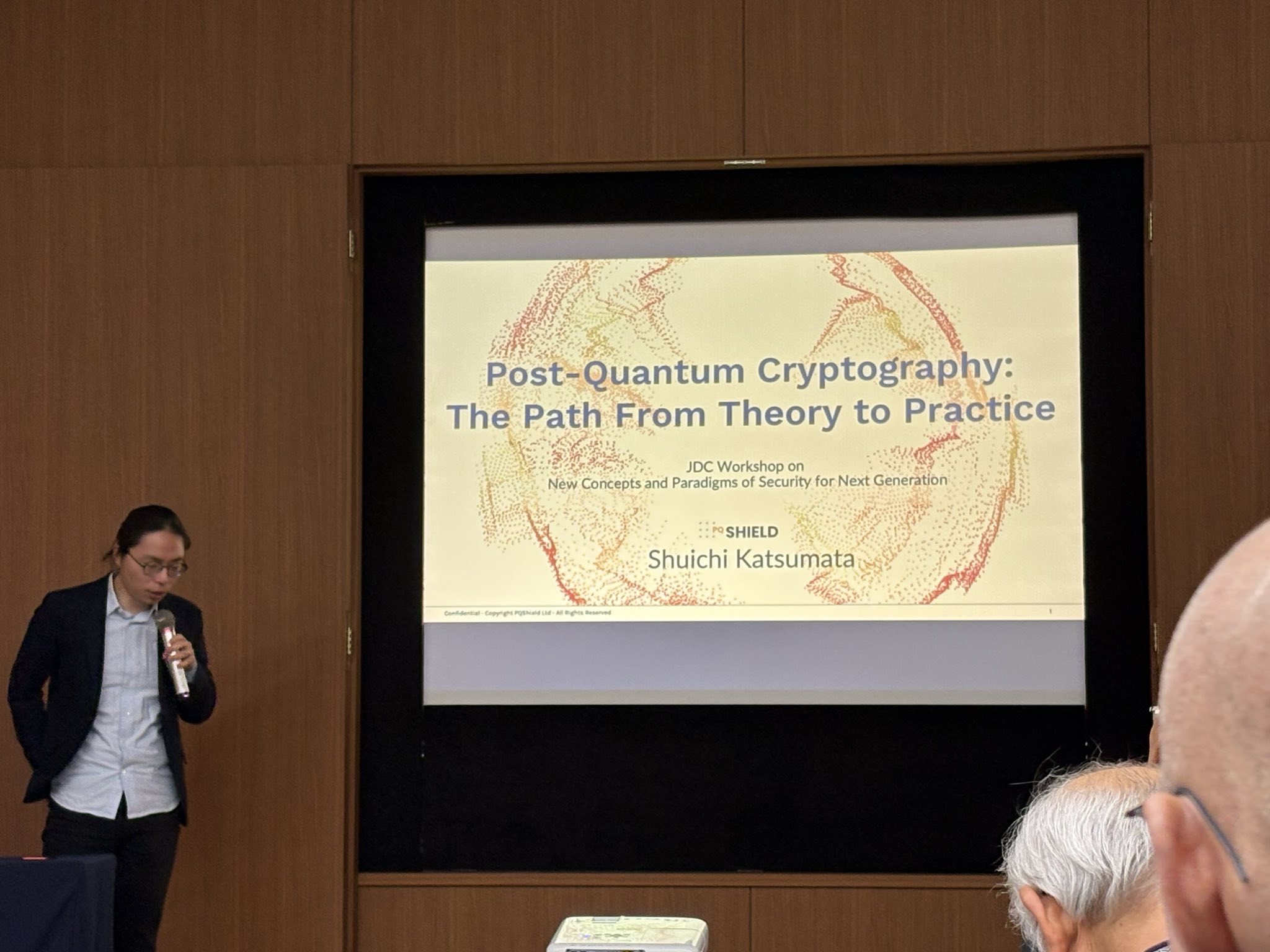
暗号技術を社会に届ける
最初は面白い問題に挑むことや純粋な数学的興味で研究に取り組んでいたが、キャリアを重ね、より責任あるポジションに就くにつれて重視する点が変わってきた。
「耐量子計算機暗号がどれだけ社会からニーズがあるのかに関心が向くようになりました。耐量子計算機暗号が社会に広く実装されるには、政府や大企業が移行しようとするモメンタムが必要ですが、自分では動かせないピースが多い。自分たちだけで迅速にデプロイできるシグナルとのプロジェクトのような世の中に到達するスピードが速い取り組みに、今は意識的に注力しています」。
ただ、重視するポイントはこの先1〜2年でまた変わってくるだろうとも予想している。
耐量子計算機暗号はしばしばインフラに例えられる。従来の暗号技術は古い橋や道路のように老朽化していつ壊れるかも分からないようなものだが、新しいインフラができるまでは使い続けなければならない。できるだけ早い対応が求められる一方で、立法機関や行政機関、標準化団体や企業などさまざまなステークホルダーが動いていく必要がある。
日本が海外、特に欧米諸国と足並みを揃えながら耐量子計算機暗号を普及させ、安全なインフラを築くまでの道筋を確立することが、目下の大きな課題だ。
純粋な研究者から推進者へ
米国では政府調達案件に耐量子計算機暗号の使用が義務付けられ、コンプライアンス上の要請からも一気に耐量子計算機暗号への移行準備が進む。対して日本では企業や業界によって対応の進み具合が異なる。チップ出荷後のアップデートが難しい自動車や半導体産業では比較的早くから対応が進む一方、後れを取る業界や企業も少なくない。「対応が必要だ」と理解はしていても直ちに着手できるとは限らない。
そうした中、PQシールドは2025年1月、耐量子計算機暗号の全国的な実装を目指すNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)プログラムへの参画を発表した。NEDOが助成するサイバーリサーチコンソーシアム(CRC)の一員として、日本の量子サイバー攻撃に対する防御力を強化していく。CRCの業務については、日本に拠点を置く勝又が指揮をとる。
「技術的に必要な要素は、実は意外と揃い始めています。効率化など小さな部分での課題はありますが、“突破”できる課題の方が多い。ただ、完成した技術1つ1つをどのように共有し、実際にインフラに組み込んでいくかの過程そのものが課題です」。
今後は、標準化団体の議論にも直接関与したり、産総研とのパイプを通じて業界団体や個別企業とも対話を重ねたりしながら、社会実装の道を進んでいくことになる。「個人としてできることは、小さな活動を積み重ねていくこと」と話す勝又は、純粋に暗号を研究開発するだけでなく、理論を実践に結びつける推進者として新たな挑戦に踏み出そうとしている。
◆
この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。
- 人気の記事ランキング
-
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機
- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ
| タグ |
|---|
- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者
- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。










