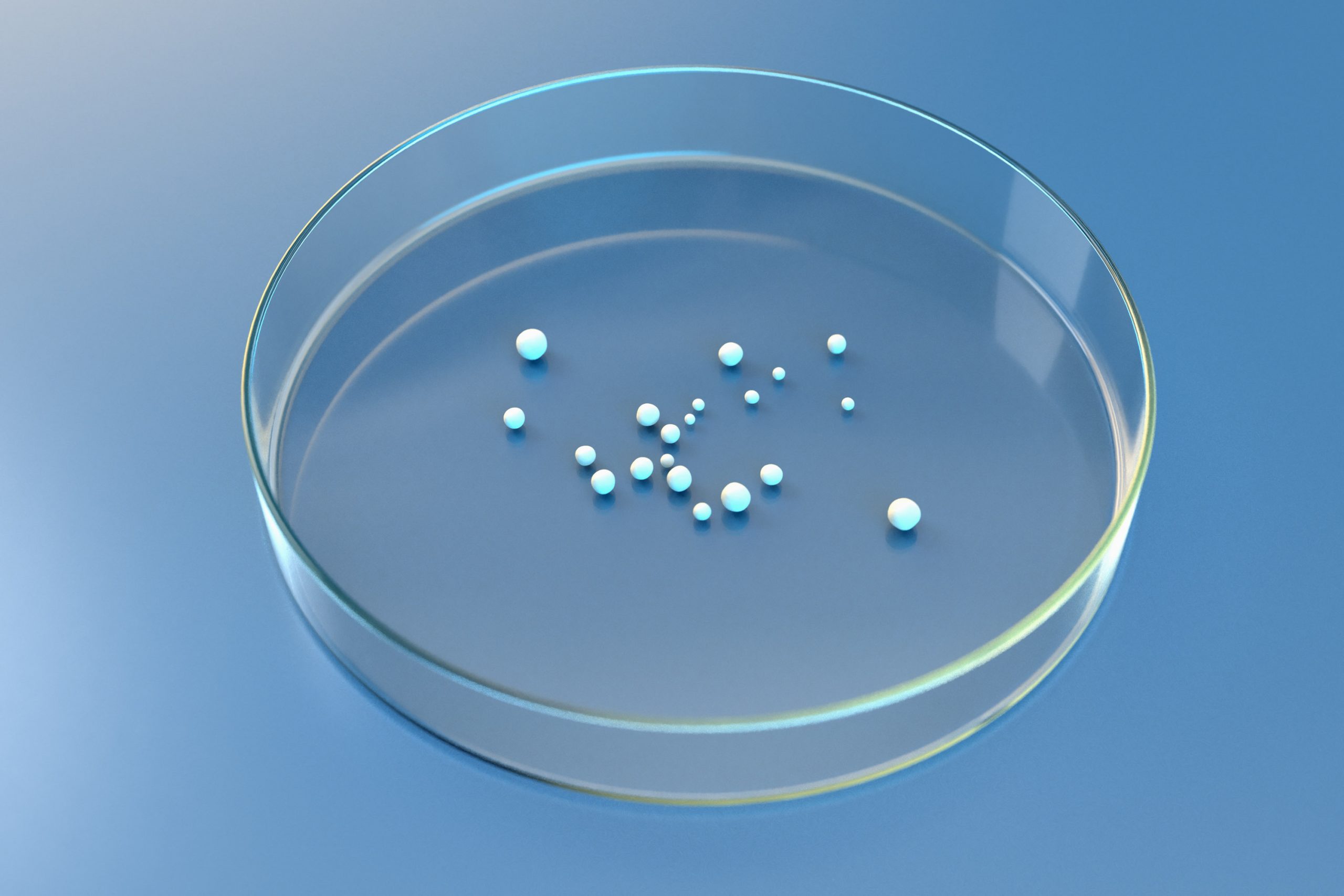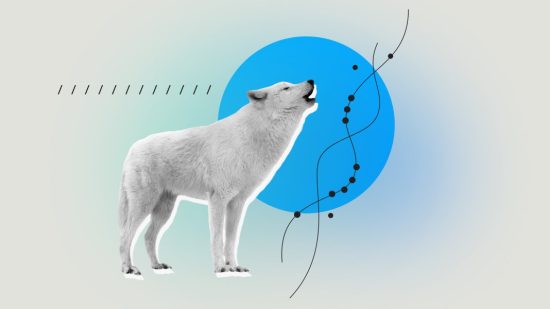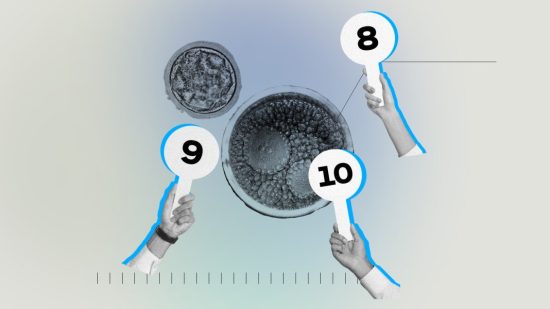人間の脳細胞を移植されたラットはただのラットと呼べるのか?
「人間の脳細胞を移植された動物は、人間に近い存在になり、より道徳上保護されるべき存在になるかもしれない」。このように予測する科学者もいる。考えを進めると、人間のクローンを作るという話にまで到達してしまう可能性がある難しい問題だ。 by Jessica Hamzelou2022.11.02
この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。
先日、人間の脳細胞をラットの脳に移植するという驚くべき実験についての記事を私は執筆した。移植すると、人間の脳細胞とラットの脳細胞が接続を形成し、共に機能することができた。つまり、人間の脳細胞がラットの脳の一部になっていたのだ。
この実験の意図とは、生きている人間の脳の中で何が起きているかをより的確に把握することであり、これは非常に難しいことで悪名高いテーマだ。ここ10年ほどの間、科学者たちは実験室で脳細胞の塊を培養して、研究を進めてきた。この塊は、オルガノイドと呼ばれている。今回の新たな研究では、オルガノイドを生まれたばかりのラットの脳に移植すると、オルガノイド単体で培養するよりも人間の脳細胞にはるかに似た形で機能し始めることが示された。
移植後数カ月経つと、人間の脳細胞はラットの脳の約6分の1ほどを占めるようになっており、ラットの行動をコントロールする中で役割を担っているように思われた。すると、必然的に浮かぶ疑問がある。これらのラットは、それでも100%ラットだといえるのだろうか。
これは難しい疑問だ。今回の研究に従事した科学者たちは、こうしたラットには、実際のところ人間らしい点はないという。チームは、研究を通して、人間の脳細胞を移植されたラットの方が、オルガノイドを移植されなかったラットと比べて、少しでも知能が高いか、またはより多くの苦痛を経験する能力を持っているのかを調査した。その結果、人間らしい特徴または行動の兆候は見受けられなかった。
しかし、そもそも人間の脳細胞を移植した目的は、人間の脳の中で起こることに関して、何らかの知見を得るためであったはずだ。そのため、人間らしいラットを作ることにはトレードオフがあるのだ。簡単にいうと、ラットは、それ自体で過度に人間らしくなることなく、人間の脳内で起きていることを再現してくれる必要があるということだ。それに、ラットが人間らしい行動を一切示さないのに、人間の病気について多くを教えてくれるということは本当にあり得るのだろうか?
「問題は、脳の中の細胞の割合を何%まで変えれば、ラットらしい行動を抑えて、ほかのタイプの行動を進めさせることができるのか、ということです」。ハーバード大学医科大学院講師で、同大学ヴィース研究所(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering)で哲学を研究している倫理学者のジャンティーヌ・ルンスホフは問いかける。
すると、さらにもう1つの疑問が湧きあがってくる。ある動物が、もはやその種の典型的な個体ではないと判断するには、どのような基準を満たさなければならないのだろうか、という問いだ。この分野の議論の多くでは、動物が道徳上保護されるべき存在であるか否か、という点が焦点となっている。ほとんどの人は、人間はその他の動物と比較して、より道徳上保護されるべき存在であり、研究目的であれその他の状況下であれ、動物を扱うのと同じ方法で人間を扱うことは受け入れられない、という考え方に同意するだろう。
人間を特別に道徳上保護されるべき存在たらしめている所以を明確に挙げることは難しいかもしれない。しかし、人間にはその他の動物より大きくて複雑な脳があり、これがその所以と関連しているという考え方が、共通認識となっている。私たちが、何かを思ったり、感じたり、夢を見たり、理性的に考えたり、社会的な絆を形成したり、将来を計画したり、より一般的に意識や自己認識を経験できるのは、私たちの脳のおかげだ。人間の脳細胞を移植された齧歯類は、同じような経験をできるのだろうか。
これは、オーストラリアのビクトリア州に位置するモナシュ大学で講師を務めるジュリアン・コプリンなどの生物倫理学者にとっては、重要な疑問だ。コプリン講師は、「人間以外の動物の脳を人間の脳に近づけるために(中略)、人間の脳のオルガノイドを移植して動物の脳と統合させるなら、その実験動物が道徳上どれほど保護されるべき存在であるのかという点にも何らかの影響が及ぶのではないか考え始める必要があると思います」と話す。
今回の研究では、影響は及んでいないように見受けられる。しかし、だからといって、将来「人間に近づけられた」または「脳機能が向上した」ラットが出てくることはないとは言えないと、コプリン講師やこの分野を専門とするその他の生物倫理学者は話している。慎重に進めていかなければならないのだ。
今回の研究では、科学者らは人間の脳細胞のオルガノイドを、ラットの脳の中で周囲の環境を感知する際に用いられる部位に移植した。しかし、科学者らは、やろうと思えば同じオルガノイドを認識や意識において役割を担う脳の部位に移植することもできたはずだ。そうしていれば、認識能力が向上していた可能性がより高くなっていたかもしれない。
それに、ラットの脳のうちどれほどの割合を人間の脳細胞が占めているのか、という問題もある。より大きなオルガノイドを移植すれば、そのラットは分子レベルでは「より人間らしい」といえるのかもしれないが、重要なのはその点ではない。重要なのは、それによってラットの精神状態が少しでも変化するのか、そして変化するならどのように変化するのか、という点だ。
また、精神状態の変化を考える上では、どれほど「人間らしく」なったかという点だけを考えていればいいわけでもない。コプリン講師は、「私たちとは全く違う形で考える動物であっても、苦痛を非常に敏感に感じたり、私たち人間にはなじみのない形で高い知能を有しているという可能性もあります」と言う。
これまでのところ、ラットに焦点を絞ってきたが、オルガノイドを生まれたばかりのサルの脳に移植すればどうなるのだろうか。人間以外の霊長類の脳は、ラットの脳と比べて、形態も機能も人間の脳にはるかに類似している。そのため、人間の病気を研究する上では、人間以外の霊長類の方がはるかに優れたモデルとなる。しかし、シンガポール国立大学の生物倫理学者であるジュリアン・サヴァレスキュ教授は、「人間に近づけた霊長類を生み出してしまう可能性が生じます」と話す。
サヴァレスキュ教授は、クローニングという観点からも懸念を抱いている。オルガノイドを構成する細胞には、ある個人のDNAが含まれる。サルの脳のかなりの部分が個人の遺伝情報を持つ細胞で占められていたら、どうなるのだろうか。
サヴァレスキュ教授は、「高度なオルガノイドを成長中の霊長類に移植すれば、実質的には実在の人物のクローンを作成していることになるかもしれません」という。「その霊長類は、単に人間に近づけられたというだけではなく、すでに実在している誰かのクローンということになるのです」。サヴァレスキュ教授は、そうなれば倫理面でこの上なく危うい状況になるという。
この問題に関しては多くの難問が残っており、はっきりとした答えはほとんど出されていない。動物が道徳上保護されるべき存在であるか否かをどう測定すべきかや、人間の脳細胞を移植された動物はどの時点で特別な存在、さらには何らかの新たな種とすべき存在になるのかは、実際のところ誰にもわからない。
ただ、いろいろと考えを巡らせるに値する問題であるのは確かだ。MITテクノロジーレビューの過去の特集(リンク先は米国版)も読んでみてほしい。2016年のこの記事では、アントニオ・レガラード上級編集者が、ヒトの臓器をブタやヒツジの体内で育てようとする試みについて書いている。臓器移植を必要としている人たちのために、新しい臓器を作り出すことを狙った試みだ。スペイン出身の幹細胞生物学者は、ローマ教皇フランシスコがこの種の試みに賛同していると記者に語った。しかしローマ教皇庁は後に、教皇が賛同しているということを否定し、この種の取り組みを「根拠をまったく欠いている」と批判している。
数年後、同じ科学者がヒトとサルに由来する胚を作り出したと、スペインのエル・パイス紙が報じた。そしてアントニオ上級編集者は、なぜこの研究が議論を巻き起こすのかをまとめた記事を書いている。
最近では、ハンナ・トーマシーが、人間の脳の不思議や、私たちがどのようにして記憶を作り出しているのかを理解するのに役立つ8つの研究を紹介している。人間の脳がどのようにして意識を作り出しているのかということについてさらに詳しく知りたい方は、リサ・フェルドマン・バレットによるこの記事を参照してほしい。
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?
- ジェシカ・ヘンゼロー [Jessica Hamzelou]米国版 生物医学担当上級記者
- 生物医学と生物工学を担当する上級記者。MITテクノロジーレビュー入社以前は、ニューサイエンティスト(New Scientist)誌で健康・医療科学担当記者を務めた。