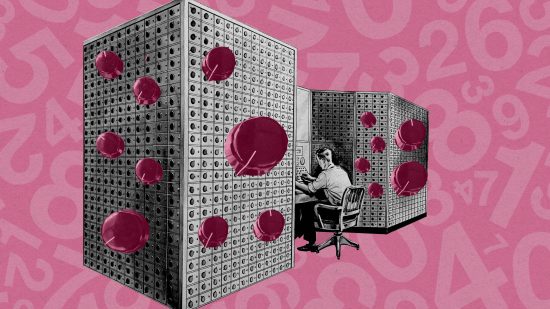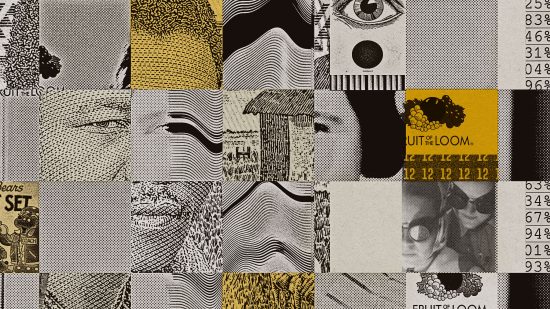バイブコーディングの衝撃——AI駆動開発が迫るIT業界の大転換
音声や簡単なテキスト指示だけでAIがソフトウェアを自動生成する「バイブコーディング」が、プログラミングの常識を覆そうとしている。すでにAIが生成するコードの比率が9割を超える企業も現れ、エンジニアの役割は「実装者」から「監督者」へと急速に変わりつつある。この変化は単なる開発手法の進歩なのか。それともIT産業全体を根底から変える大転換の始まりなのか。 by MIT Technology Review Japan2025.08.04
キーボードでコードを一行一行書いていくプログラミングから、AIエージェントに自然言語で「ノリ」よく指示を出すだけでソフトウェアを開発する時代へ——。「バイブ(Vibe)コーディング」という概念がいま、ソフトウェア業界で大きな注目を浴びている。
2025年7月30日に開催された「Emerging Technology Nite #33」では、ボストン コンサルティング グループ BCG X プリンシパルAIエンジニアの高柳慎一氏が登壇。「バイブコーディングの正体——AIエージェントはソフトウェア開発を変えるか?」と題して、バイブコーディングの現状と今後の可能性について詳しく解説した。
バイブコーディングとは何か?
「AIエージェントはソフトウェア開発を変えるか? 結論から申し上げると、答えはイエスです。明らかに変えるでしょう」。高柳氏は冒頭でこう断言した。

ボストン コンサルティング グループ BCG X プリンシパルAIエンジニア。博士(統計科学)。 リクルートコミュニケーションズ、LINE、ユーザベースなどを経て現在に至る。デジタル専門組織BCG Xにおける、AIを含む生成AIと統計科学のエキスパート。
バイブコーディングは、オープンAI(OpenAI)共同創設者であるアンドレイ・カルパシーが2025年2月に提唱した新しいプログラミング手法で、「開発者がAIと自然言語で対話し、AIが書いたものを“Accept All” alwaysの原理で受け入れ、エラーメッセージはそのままコピーしてAIに修正を依頼する」という極めてシンプルな原則に基づいている。「LLM(大規模言語モデル)が書くものに、なすがままに身を委ねるのがバイブコーディング」(高柳氏)。
高柳氏によれば、バイブコーディングの最大の特徴は「HowからWhatへの転換」だという。「今まで『どうやって実装するか』を考えていたのが、『何を作るか』に集中できるようになります。実装の詳細はAIに任せて、人間はその前段となるアイデアや上流の部分に集中できるようになるわけです」(高柳氏)。

講演の合間には、実際にパズルゲームをバイブコーディングで作成するデモも披露された。高柳氏が音声入力で、「TypeScript(タイプスクリプト)でテトリスっぽい落ちゲー作って」と指示すると、AIが自動的にコードを生成し、実行する。途中、期待どおりに動かないこともあったが、何度か簡単な追加指示を出すことで、最終的にWebブラウザー上で動くパズルゲームが完成した。
「AIがコードを書き始めたところを確認して、例えばトイレに行ったり飲み物を買いに行ったりする。戻ってきたら進捗を確認してまた指示を出せばいい。この間は別のことができるので、生産性が驚くほど上がるわけです」(高柳氏)。
アシスタントからエージェントに進化したAIコーディングの現在
バイブコーディングは従来のAIを使ったコーディングとはどう違うのか。高柳氏は、AIコーディングを大きく第1世代と第2世代に分けて整理した。広義のバイブコーディングを含む「AI駆動開発」は、この第2世代に該当する。
第1世代は、「アシスタント」の時代で、2023年末のChatGPT(チャットGPT)の登場から2024年前半にかけて普及した。「GitHub Copilot(ギットハブ・コパイロット)などのコーディング・アシスタントツールが導入され、単純なバグの修正やコードの補完ができるようになった。コードの断片を入力すると続きをAIが書いてくれるといった、お手伝いをしてくれるイメージです」(高柳氏)。
これに対して2025年に入って本格化した第2世代は、「エージェント」が主導する。「頭脳であるLLMと開発ツールが繋がって、開発がどんどん進んでいく。自律的な開発プロセスを機械が意のままに回すようになったのが第2世代です」(高柳氏)。
第2世代では、実行に必要なライブラリーをAIエージェントがインターネットから自律的に取得し、エラーが発生すれば自動的に修正するなど、人間の介入なしに開発プロセス全体が進行する。「今までは人間の補完だったものが、AIエージェントが自律的にものを考えて動き出している」(高柳氏)。このAIエージェントが、バイブコーディングの技術的な基盤となっている。
違いは、コードの量にもすでに現れている。現在、グーグルやアンソロピック(Anthropic)といった大手AI企業の社内では、コードの40〜95%がAIによって生成されているという。第1世代のAIでは25%だったことを踏まえると、AIによるコードの生成がかなり進んでいる印象だ。開発時間も大幅に短縮されており、第1世代では50%、第2世代では最大90%にまで短縮されているという。アンソロピックのダリオ・アモデイ共同創業者の「1年後にはほぼすべてのコードを生成するようになるだろう」という発言も、単なるセールストークとして受け流せないほど、状況は急速に変わりつつあるようだ。
大規模システム開発でも使えるか?
バイブコーディングでは開発プロセスも根本的に変わる。従来の「要件定義→設計→実装→テスト→デプロイ」という流れが、究極的には「生成→検証」の2ステップに簡素化される。「人間の頭の中にある要件を自然言語で指示すれば、あとは人間に残された仕事は検証だけになる」と高柳氏は言う。
とはいえ、複雑かつ大規模なシステム開発をバイブコーディングに完全に置き換えるのは現時点では難しそうだ。ただ、範囲を絞って部分的に適用する「AI駆動開発」を「広義のバイブコーディング」として捉えると、すでに「十分可能で、できている」状況だという。実際、国内の大手IT企業がClaude Codeを導入して開発期間を79%短縮するなど、大規模システムを扱う国内外の大企業でも成功事例が出始めている。
高柳氏は大規模システム開発における広義のバイブコーディングの課題について、①開発、②セキュリティ、③保守性の3つの論点で整理した。
①の開発における課題としては、全体設計の一貫性の維持、品質の不安定化、複雑な業務ロジックの理解、文脈理解の限界などがある。「AIは確率的に動くので、1+1でも1.99999と答えることがある。同じコードを書いてくれと言っても、毎回違うものが出てくる」(高柳氏)という特性が、企業システムには向かない場合もある。そこで、「人間が命名ルールを決めたり、テスト駆動でやるからテストを必ず始めに書く、1つのプルリクエストは必ず1つのコミットで終わらせるなどのルールを叩き込む」(高柳氏)必要があるという。
②のセキュリティ面では、「AI生成コードの25〜70%には脆弱性があると言われています」と警鐘を鳴らし、SQLインジェクション対策の不備やデータベースパスワードの平文記載など、具体的なリスクを指摘。対策として、「セキュリティツールを使う」「人間によるレビューを徹底する」「AIに与える権限自体を絞る(最小権限の原則)」の3点を挙げた。
③の保守性の問題については、「自動ドキュメントの生成もAIは得意なので、人間が読むためのドキュメントとAIが実行するコードで分ける」「人間のレビューで保守性を担保する」「設定ファイルで徹底的にしつける」といった解決策を示した。「結局、最後に責任を持つのは人間。それはAIがコードを書く場合でも同じです」(高柳氏)。

では、現時点でバイブコーディングが特に威力を発揮するのはどのような用途だろうか。高柳氏は、「品質よりも速度を優先するケースや低リスクなケースが向いています」と話す。具体的には、PoC(概念実証)、MVP(実用最小限の製品)、プロトタイプ開発などだ。従来はパワーポイントやデザインツールで作っていたモックアップに代わり、バイブコーディングを使えば実際に動くデモをすばやく作ることができる。実際、有名ベンチャーキャピタルのYコンビネーターの投資先企業は、デモプロダクトをほぼAIで作らせているという。
一方で製品レベルでは「使い捨てではなく長期運用、品質重視、監視系の充実」が求められるため、人間とのコラボレーションが必須になる。高柳氏は「テスト駆動開発」「ガイドライン作成」「コードレビュー」の3つを重要な対策として挙げた。例えばテスト駆動開発では、テストを作成し、テストをパスするようにコードを書き、検証まで実行するようAIに指示することで、一定の品質を担保できるという。
IT産業のビジネスモデルにも影響
広義のバイブコーディング、すなわちAI駆動開発がIT産業全体に与える影響はどう捉えるべきだろうか。ここまでに述べてきた開発プロセスの簡素化や人間の役割の変化などを踏まえて、高柳氏が指摘したのが、ビジネスモデルの大変化だ。これまでのIT導入では、システムに合わせて業務プロセスを標準化するのが普通だった。ところが、バイブコーディングが進むことで、「ソフトウェアが驚くほど安く作れるようになり、業務を変える必要がなくなる」(高柳氏)。ビジネスアイデアがより重要になり、ソフトウェアをオンデマンド生成するような新たなビジネスモデルが現れる可能性もあるという。
組織面では、「今までのピラミッド構造から鉛筆型になる」と予測。シニアエンジニアとジュニアエンジニアの比率が逆転し、シニア主体の組織になると分析した。エンジニアの役割については、ドメイン知識とユーザー理解に強みを持ち、AIを使いこなす「プロダクトエンジニア」が9割を占め、AIによる自動化が難しい超高度な専門性を持つ「エキスパートエンジニア」が1〜10%程度になると予想。「人は仕事をAIに奪われるのではなく、AIに精通した人に奪われる」というエヌビディアCEOのジェンセン・ファン氏の言葉を引用し、AI活用スキルを磨く重要性を強調した。
高柳氏は最後に、バイブコーディングを実際に導入するための段階的なアプローチを提示した。「まず小さく始めてみることをおすすめします。Lovable(ラバブル)やReplit(レピット)など気軽に使えるツールでWebサイトを作ってみるなど、5分〜10分程度の体験から始めてみてください」(高柳氏)。
個人レベルでの体験を積んだ後は、組織レベルで展開する。「その経験を活かして、3カ月くらいで意味のあるインパクトがある成果と、残された課題を明確にした上で、社内でプロジェクトを作る。そこから半年、1年くらいで組織全体にAI活用のプロジェクトを進めていけるとよいでしょう」(高柳氏)。
プログラミングのやり方だけでなく、ソフトウェア開発のプロセスやエンジニアの役割、さらにはIT業界のビジネスモデルまで大きく変える可能性を持つバイブコーディング。高柳氏が最後に述べた「大きな流れには逆らわず、使う側に回る」という助言が、変化の激しい時代を生き抜く鍵となるかもしれない。
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している
| タグ |
|---|
- MITテクノロジーレビュー編集部 [MIT Technology Review Japan]日本版 編集部
- MITテクノロジーレビュー(日本版)編集部