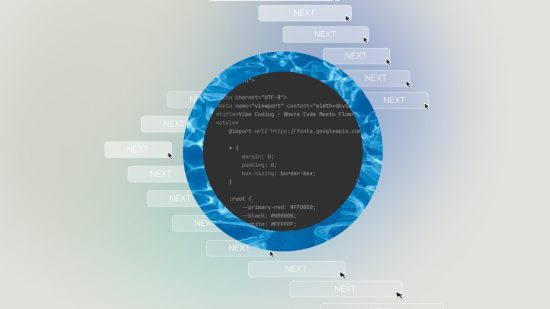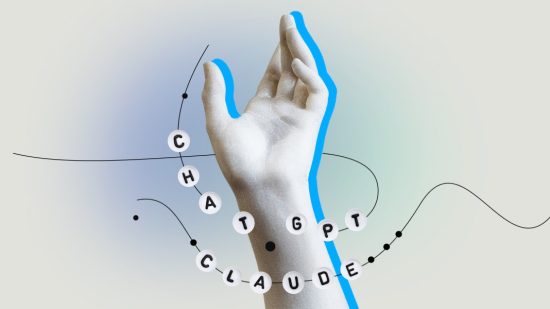GPT-5、消えた驚き——スマホに似てきたAIモデルの発表会
オープンAIが先日リリースした最新のAIモデル「GTP-5」は、洗練されたユーザー体験を提供するが、画期的な進歩とは言い難いものだった。AI企業は誇大宣伝サイクルに陥りつつある。 by Mat Honan2025.08.14
- この記事の3つのポイント
-
- オープンAIのGPT-5は革命的ではなく洗練された製品である
- アルトマンCEOらAI企業経営者が誇大宣伝を繰り返している
- AI分野の本当の革新はチャットボット以外で起こっている
オープンAI(OpenAI)がリリースしたGPT-5について、本誌のグレース・ハッキンズ記者が優れた記事を書いている。GPT-5は長らく待望されていた、オープンAIの新しいフラッグシップ・モデルである。ただし、記事の要点の一つは、GPT-5が以前のバージョンよりも優れた体験を提供する可能性があるものの、革命的なものではないということである。「GPT-5は何よりもまず洗練された製品である」とグレースは結論付けている。
この見解は、人工知能(AI)の最新モデルのリリースがスマートフォンのリリースと似てきた、という本誌のウィル・ダグラス・ヘブン( AI担当上級編集者)の主張ともほぼ一致している。つまり、私たちが目にしているのは、ユーザー体験を向上させるための段階的な改善である(8月7日付けのプラットフォーマー=Platformerでケーシー・ニュートンも同様の指摘をしている)。GPT-5のリリース当日、オープンAIのサム・アルトマンCEO自身が、アップルが初めてRetina(レティナ)ディスプレイ搭載のiPhoneをリリースした時にたとえていた。なるほど、確かにそうかもしれない。
では、BlackBerry(ブラックベリー)のキーボードからタッチスクリーンのiPhoneへの劇的な移行のような変化はどこにあるのだろうか? リアルタイムの道案内を可能にし、ウーバー(Uber)やグラインダー(Grindr)のような企業を生み出し、ブリトーのためにタクシーを呼べるようにした支援GPSや位置情報APIのような革新は? 真のブレークスルーはどこにあるのだろう?
実際、GPT-5のリリース後、オープンAIは「ユーザーの反乱」ともいえる事態に直面した。GPT-4oの個性を惜しむ顧客たちは、同社に働きかけて、プラス(Plus)ユーザー向けのオプションとしてGTP-4oを復活させることに成功した。このことは、GPT-5のリリースが目に見える性能の飛躍よりも、むしろユーザー体験に関するものであった、ということを示している。
それでも、GPT-5の発表の数時間前、アルトマンCEOは宇宙に浮かぶ新たなデス・スター(Death Star)の画像を添付して、’もったいぶった予告をSNSに投稿していた。「博士号レベルの知能」を誇ると豪語し、その後出演した『モーニングス・ウィズ・マリア(Mornings with Maria)』という番組では、「多くの命を救うでしょう」と主張した(この手の主張に対する私の極度の懐疑心をお許しいただきたいが、間違いなく以前にも似たような話を見聞きしてきた)。
誇大宣伝が多すぎるとはいえ、ここで大げさに話を盛っているのはアルトマンCEOだけではない。7月30日にはメタのマーク・ザッカーバーグCEOが、私たちがAI超知能に近づいているという長いメモを発表した。アンソロピック(Anthropic)のダリオ・アモデイCEOは2025年5月に、AIがおそらく1年以内にエントリーレベルの仕事の半分を奪うであろうという予測をして、人々を震え上がらせた。
これらの企業の経営者は、自分たちが開発している技術が世界を支配し、人類を滅ぼす可能性について文字通り語っている。その一方でGPT-5は、いまだに「blueberry(ブルーベリー)」という単語に「b」がいくつあるかを正確に答えられない。
とはいえ、オープンAIやアンソロピックがリリースしている製品が印象的でないということではない。確かに目を見張るものだし、明らかに高い実用性を備えている。しかし、モデルのリリースを巡る誇大宣伝のサイクルは、もはや手に負えない状況に達している。
私はChatGPT(チャットGPT)やGoogle Gemini(グーグル・ジェミニ)をほぼ毎日、しばしば1日に何度も使う。例えば先日、妻がサーフィンをしていた時、クジラが水面で尻尾を繰り返し叩いている様子に遭遇したことがあった。これまで非常に多くのクジラを、しばしば至近距離で見てきたにもかかわらず、このような行動を見たのは初めてだった。妻は私に動画を送ってきて、私も興味をそそられた。そこで私はChatGPTに「なぜクジラは水面で尻尾を繰り返し叩くのですか?」と尋ねた。するとすぐに、「それは『ロブテイリング』(日本版注:テールスラップとも呼ばれる)と呼ばれる行動です」と自信たっぷりに説明し、クジラがロブテイリングをする理由を書き出してくれた。実にすばらしいことだ。
しかし冷静に考えてみると、普通のグーグル検索でも同様にロブテイリングに関する情報に私は到達できたはずだ。ChatGPTの回答は、私にとって答えを得るまでの行動を短縮してくれたが、その回答はあまりにも断定的すぎた。現実には、専門家は多くの仮説を持っているものの、いまだにこの奇妙な動物の行動を本当に理解することはできていない。
私がロブテイリングが謎めいた行動であると認識しているのは、実際に検索結果を深堀りして調べたからである。そこで私はエミリー・ボーリングによる美しく哀愁に満ちたエッセーに出会った。彼女は海上での体験を描写し、ザトウクジラが水面に尾を叩きつける様子を観察し、この行動をめぐる科学的不確実性について論じている。これは捕食技術なのだろうか? コミュニケーションの一形態なのだろうか? 威嚇行動なのだろうか? ボーリングが指摘するように、この行動は多くのエネルギーを消耗する。クジラにとって多大な労力を要する行動なのだ。それなのに、なぜクジラはこのような行動を取るのだろうか。
私は特にある一節に心を打たれた。ボーリングは他の生物学者の研究を引用し、次のような結論に至っている。
驚くべきことに、テールスラップのような行動に必要なエネルギーの大きさそのものが、それが使われる理由である可能性がある。生物学者のハル・ホワイトヘッドは次のように指摘している。「ブリーチングやロブテイリングは、非常に多くのエネルギーを要するからこそ、メッセージの重要性や発信者の体力を示す優れた信号となるのです」。テールスラップは、クジラが健康で、ほぼ最大速度で移動でき、強力な行動を持続する能力を持ち、しかも1日の大半のエネルギーを費やしてでも伝える価値のある重要なメッセージを持っていることを意味するのだ。「注目してください!」とクジラは訴えているかのようだ。「私は重要です! 私に気づいてください!」
ある意味では、AIの誇大宣伝サイクルは手に負えない状態にならざるを得ない。企業は膨大な投資額、つまり数十億ドルの埋没費用(サンクコスト)を正当化しなければならない。環境への多大な影響を与える大規模データセンターが莫大な費用をかけて作られ、それが見かけ上は経済を支えており、同時に経済を破綻させる脅威ともなっている。とにかく、実に多くの資金が危険にさらされているのだ。
だからといって、AI分野において本当にワクワクするようなことが起こっていない、ということではない。私自身、新しいAI製品のリリースに度肝を抜かれた瞬間が何度もあった。GPT-3.5もその1つだし、DALL-E(ダリー)やNotebookLM(ノートブックLM)、Veo(ベオ)3、Synthesia(シンセシア)にも驚嘆した。実際、先日リリースされたAI製品で、少しぶっ飛んだものがあった。グーグル・ディープマインド(Google DeepMind)の「Genie(ジーニー)3」は、テキスト・プロンプトを没入感のあるナビゲート可能な3D世界に変換できるものだ。ぜひチェックしてみてほしい。本当に驚異的である。同時に、Genie 3は、現在AIで起こっている最も興味深いことは、チャットボットではないという事実を示しているとも言える。
現時点において、新しい大規模言語モデル(LLM)チャットボットの新機能に定期的に驚嘆している人々の大部分は、LLMチャットボットの宣伝によって利益を得る立場にある人たちであると、私は主張したい。
皮肉っぽく聞こえるかもしれないが、実のところそうではない。デス・スターを約束しておきながら、実際に提供されたのは、モデルを自動的に選択してくれることが魅力のチャットボットだという事実。これこそが、よほど皮肉的である。超知能を約束しておきながら、出てくるのは「シュリンプ・ジーザス」。これらはすべて単なるロブテイリングに過ぎないのかもしれない。「注目してください! 私は重要です! 私に気づいてください!」と叫んでいるだけなのだ。
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?
- マット・ホーナン [Mat Honan]米国版 編集長
- MITテクノロジーレビューのグローバル編集長。前職のバズフィード・ニュースでは責任編集者を務め、テクノロジー取材班を立ち上げた。同チームはジョージ・ポルク賞、リビングストン賞、ピューリッツァー賞を受賞している。バズフィード以前は、ワイアード誌のコラムニスト/上級ライターとして、20年以上にわたってテック業界を取材してきた。