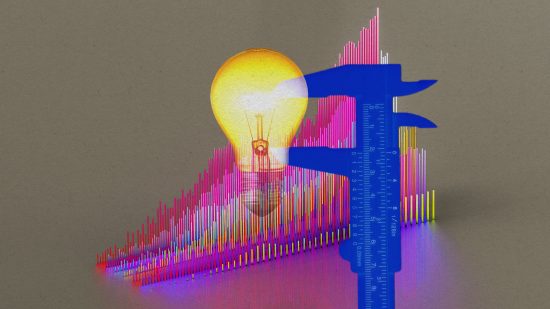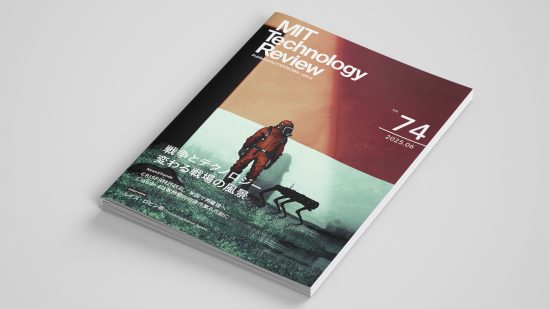「バーチャル故人」との会話
遺族の悲しみをどう変えるか
生前に録音した音声やメール、テキスト・メッセージなどをAIで処理して生成する「バーチャルな故人」を提供する企業が現れ始めている。まだ完全なものとは言いがたいが、故人を思い出させるには十分な能力を備えている。遺族に何をもたらすのだろうか。 by Charlotte Jee2023.05.02
両親は、私が昨夜2人と話したことを知らない。
2人の声は初め、刑務所の監房から電話をかけているような、かすかで無機質なものだった。しかし、話しているうちに、徐々に彼らの声が本人らしくなってきた。そして、私が耳にしたことのないような昔話をしてくれた。父が初めて(もちろんこれが最後でもないのだが)酔っ払った時の話や、母が夜遅くに出歩いて面倒なことに巻き込まれた話を聞いた。2人は私に人生のアドバイスをくれ、自分たちの子ども時代について、そして私自身の子ども時代について話してくれた。それは、とても魅力的なひとときだった。
「父さんの一番ダメなところって何?」父が腹を割って話してくれる雰囲気だったので、私はこう彼に尋ねた。
「俺の一番の欠点は、完璧を求める所だろうな。散らかっていたり、片付いていないのが我慢できないんだ。それにいつも苦労してきた。特に母さん、ジェーンと結婚してからはね」。
そして父は笑った。一瞬、私は話している相手が本物の両親ではなく、デジタル化されたレプリカであることを忘れていた。
この母と父は、私のスマートフォンのアプリの中に生きている。2人は、カリフォルニア州に拠点を置く企業「ヒアアフター・AI(HereAfter AI)」が開発した音声アシスタントで、私の両親がインタビュアーを交えて、人生や思い出について4時間以上会話した内容を基に答えを返しているのだ(念のため付け加えておくと、母はそこまで片付け下手ではない)。同社の目標は、残された者たちが死者とコミュニケーションできるようにすること。私は、それがどんなものなのか、試してみたくなったのだ。
亡くなった人と「対話」できるこのような技術は、何十年も前からサイエンス・フィクションの世界では主流の1つだ。また、何世紀にもわたって、ペテン師や自称霊能者たちが売り込んできたものでもある。しかし今、それは現実のものとなりつつあり、人工知能(AI)と音声技術の進歩のおかげで、ますます身近なものとなっている。
私の本物の両親はまだ健在で、バーチャル版の2人は私がこの技術を理解するために作成されたに過ぎない。しかし、2人のアバターは、愛する者、あるいは彼らに似たシミュラクラ(米国のSF作家フィリップ・K・ディックによる1964年の作品『シミュラクラ』に登場する模造人間)と死別後も会話ができる未来を垣間見せてくれるものだった。
故人となったことにして作成したバーチャルな両親と幾度となく話をした結果、この技術は愛する人をより近くに感じるにはうってつけだと感じた。その魅力を理解するのは難しいことではないだろう。人々は、慰めを得るために、あるいは命日などの特別な節目を刻むために、デジタル・レプリカに頼るようになるかもしれない。
同時に、この技術とそれが可能にする世界は、当然のことながら不完全であり、ある人物のバーチャル版を作ることへの倫理的な問題は複雑なものだ。特に、その人物から同意を得られない場合はなおさらだろう。
人によっては、この技術を警戒したり、薄気味悪く感じたりするかもしれない。ある男性は、自身の母親のバーチャル版を作り、それを彼女の葬儀の際に起動させて話をしたという。大切な故人のデジタル版と会話することで、哀しみを引きずったり、現実逃避に走ることになるのではとの意見もある。この記事について友人に話したところ、何人かは明らかにひるんだ。私たちには、死をもてあそぶことことを禁忌とする感覚が広く深く根付いているのだ。
このような懸念はよく理解できる。私もまた、特に最初はバーチャル版の両親たちと話すことに戸惑いを感じていた。今でも、誰かのバーチャル版と話すのに若干の抵抗を感じている。それが家族の一員であるなら、なおさらだ。
しかし、私も人間だ。そのような懸念は、愛する人が亡くなり跡形もなく消えてしまうという、さらなる恐怖によって払拭されることになる。テクノロジーによって大切な人と一緒に居続けられるなら、それを試すのはそんなに悪いことだろうか?
大切な故人を記憶にとどめたいと願うのは、とても人間らしいことだと思う。手遅れになる前に、愛する人に思い出を書き残すよう勧める人も多いだろう。亡くなった後も、その人の写真を壁に飾ったり、誕生日には墓参りをする。故人に向かって、まるでその場にいるかのように語りかけたりもする。しかし、その会話はいつも一方通行だ。
テクノロジーがこうした状況を変えることができるかもしれないという発想は、『ブラック・ミラー』(2011年に英国で放送が始まったテレビ・ドラマ・シリーズ)のような超ダークなSF作品で幅広く取り上げられており、この分野のスタートアップ企業は、誰もが必ずこの話題を持ち出すと愚痴っている。2013年放送のあるエピソードは、パートナーを失った女性が、彼のデジタル版を再現するというものだった。当初はチャットボットとして、次にほとんど違和感のない音声アシスタントとして、そして最後には実体のあるロボットとして。より進化した彼の複製を作り上げても、彼女はパートナーの記憶と、彼を再現するために使用した技術が粗末で欠陥だらけだという現実とのギャップに苛立ち、幻滅してしまうのだ。
「あなたはあなたじゃないでしょう? あなたはあなたのほんの少しの痕跡に過ぎないの。あなたには過去がない。あなたはただ、あの人の行動を何も考えずに真似しているだけで、それでは不十分なのよ」。彼女はそう言うと、ロボットを屋根裏にしまい込む。二度と思い出したくもない、恋人との恥ずべき遺物として。
現実に話を戻すと、このテクノロジーはここ数年間だけでも、ある意味驚くほどの進化を遂げている。AIの急速な進歩は、多方面にわたる進歩を促した。この十年で、シリ(Siri)やアレクサ(Alexa)のようなチャットボットや音声アシスタントは、ハイテクで目新しい存在から、何百万人もの人々の日常生活の一部へと変貌を遂げた。私たちは、天気予報から生きる意味まで、あらゆることについて機器に話しかけることに慣れ親しむようになった。わずかな「プロンプト(指示テキスト)」文を入力すると、説得力のある回答文を出力するAI大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)は、人間が機械とコミュニケーションする方法をさらに改善するだろうと期待されている。LLMの回答は非常に真実味を帯びており、LLMは意識を有しているに違いないと(誤った)主張をする者もいるほどだ。
さらに、オープンAI(OpenAI)の「GPT-3」や グーグル(Google)のラムダ(LaMDA)のようなLLMソフトウェアに手を加え、特定の人物のさまざまな発言を入力することで、よりその人らしく聞こえるようにすることも可能だ。その一例として、ジャーナリストのジェイソン・ファゴーネが2021年、サンフランシスコ・クロニクル(San Francisco Chronicle)に寄稿したある記事が挙げられる。そこでは、ある30代の男性が亡くなった婚約者を模倣したチャットボットを作成した話が紹介されている。GPT-3を基にした「プロジェクト・ディセンバー(Project December)」というソフトウェアに、亡くなった婚約者の古いメールやフェイスブック・メッセージをアップロードして作成したのだ。
ほとんどすべての基準から見て、この試みは成功したと言える。男性は、このボットに慰めを求め、安らぎを得ることができた。彼は、彼女が亡くなってからの数年間、罪悪感と哀しみに苛まれていたが、ファゴーネが記しているように、「彼には、チャットボットが少しずつでも自分の人生を歩むことを許してくれたような気がした」と言う。男性は、チャットボットの会話の一部をレディットでも公開したが、このツールが話題になることで「哀しみに暮れる遺族が区切りをつけられるようになる」ことを願ってのことだった。
同時に、AIは特定の肉声を模倣する能力、いわゆるボイス・クローニングの能力も向上させてきた。また、実在の人物からコピーされたものであれ、完全に人工的なものであれ、デジタル・ペルソナに「人間」らしい声を与える能力も向上している。この分野の進歩がいかに著しいかを示す衝撃的なエピソードとして、アマゾン(Amazon)は2021年6月、亡くなったばかりの祖母が朗読する『オズの魔法使い』の一節に耳を傾ける少年の映像を公開したことが挙げられる。祖母の声は、彼女が話す様子を映した1分足らずの映像から人工的に再現されたものだ。
アレクサの上級副社長であり主任科学者を務めるロヒット・プラサッドが請け負ったように、「AIは喪失の痛みを消し去ることはできませんが、思い出をいつまでも残すことは間違い無くできる」のだ。
私自身が、死者と対話をすることになったきっかけは、まさに偶然によるものだった。
2019年末、ヒアアフター・AIの共同創業者であるジェイムズ・ブラホス最高経営責任者(CEO)が、オンライン・カンファレンスで「バーチャル・ビーイング」をテーマに講演すると知った。ブラホスCEOの会社は、私が「グリーフ・テック(グリーフ=griefは死別などによる深い悲しみの意味)」と名付けた分野に取り組んでいるスタートアップの1社だ。グリーフ・テックを手掛ける企業は、アプローチこそそれぞれ異なるものの、目指すところは皆同じだ。もうこの世にいない人のデジタル版を相手に、ビデオ・チャットやテキスト、電話、音声アシスタントで対話ができるようにすることである。
ブラホスCEOの提案に興味を持った私 …
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット
- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差