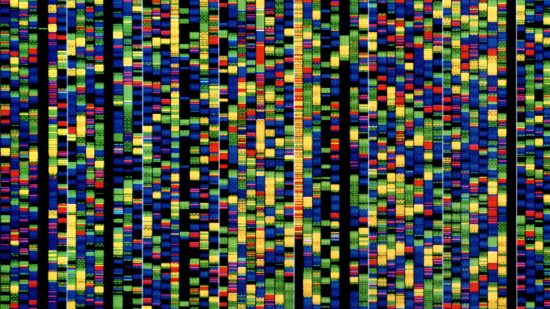ボディ・ファームに横たわる
遺体が教えてくれるもの
自身の死後に遺体を研究機関などに寄贈する「献体」という制度がある。この制度を通して受け取った遺体を、研究者や学生がどのようなことに使っているのか。そして、どのように扱っているのか。実態を知るために、「ボディ・ファーム(死体農場)」と解剖学研究室を訪れた。 by Abby Ohlheiser2023.02.03
レベッカ・ジョージはそこにいたハゲワシのことを迷惑だと思ったりはしなかった。ジョージはある7月の早朝にウェスタン・カロライナ大学の「ボディ・ファーム」(死体農場)の門を開けた。そこにいたハゲワシたちは、いらだった様子でバサバサと羽音を立てたが、ジョージにはハゲワシたちが子どものように思えた。彼女がやって来たことで、ハゲワシたちは朝食を邪魔されたのだった。ジョージは人体の腐敗について研究している。人体が腐敗するということは、他の生物の食料になることでもある。そんなジョージにとって、腐敗した人体を食料とする生物たちはありがたい存在なのだ。
法人類学者であるジョージがその日の主な仕事に取り掛かると、ハゲワシたちはボディ・ファーム周囲にある木々から不満げに鳴き始めた。ジョージの仕事とは、新たな遺体(この提供者は以降「提供者X」と記す)を法医骨学研究所(Forensic Osteology Research Station)、通称「FOREST」のボディ・ファームに安置することだった。ノースカロライナ州のとある温帯雨林に入り、急な斜面を登っていくと、提供者Xの遺体が置かれたボディ・ファームに辿り着ける。周囲には防犯用のフェンスが二重に張り巡らされている。このフェンスで囲まれたボディ・ファームは「エンクロージャー1」と呼ばれている。寄付された遺体を地面の上に安置して、自然に腐敗させるための場所だ。その真向いにあるのが「エンクロージャー2」。ここでは研究者たちが地中に埋められた遺体を調べている。ジョージはFORESTの管理者である。ここでジョージは、法人類学者や大学生から成る小規模なチームの一員として、遺体が完全に白骨化するまでの過程を観察している。時にその観察は数年間にも及ぶことがある。
ジョージはボディ・ファームに入ってすぐの場所で、提供者Xの遺体を仰向けにして置き、気を付けの姿勢にした。衣類の着用が必要となる特定の研究でない限り、提供者の遺体は「生まれたままの姿」で横たえられる。衣類を身に付けていると、腐敗が遅くなるためだ。ジョージは遺体のすぐ横に、ID番号と日付が記された小さな黄色い旗を立てた。近くには別の遺体もあった。白骨化した片手はそっと小さな石の上に乗っており、頭部は右へと傾いていた。まるで眠っているように見えた。
提供者Xの近親者は、死亡時に遺体をFORESTのボディ・ファームに置いておくことを選んだ。米国では、毎年およそ2万名の死者あるいはその家族が、遺体を研究および教育目的のために寄付している。その死を有意義なものにしたいという願いから献体する者もいれば、死者にまつわる従来の産業に幻滅をしたからという者もいる。米国では免許証にあるチェック欄に記入をしておけば臓器ドナーになれる。そうすれば、死亡時に移植に適した臓器を患者に提供できる。しかし、遺体をまるごと寄付するという行為に関しては、米国ではあまり話題にならない。
献体すると、一般的な火葬や埋葬よりも安い費用で済む場合もある。献体プログラムの中には、一定の距離内であれば遺体の輸送料を負担してくれるものもある。また、最終的に家族へと遺体を返却することがプログラムに含まれる場合、火葬のための費用も負担してくれる。FORESTの場合、寄付された遺体は大学にある法医学保管所で永久に保管されることになる。
献体の理由がどのようなものであれ、その遺体は非常に貴重なものだ。医療において、遺体を扱うことは避けられない。死者の遺体は長年、医療従事者たちが訓練や学習のために使っている。寄付された遺体の多くは医学校へ送られ、学生たちが解剖学を学んだり、手術の練習をしたりするのに使われる。提供者Xのようなその他の遺体は、大学の研究施設に送られる。また、米国には献体を受け付ける民間企業がいくつかあり、そのような企業へ送られることもある。ウェスタン・カロライナ大学のFORESTは2003年に創設されており、米国では2番目に古いボディ・ファームだ。ノックスビル市にあるテネシー大学はFORESTよりもずっと大規模なボディ・ファームを保有している。創設は1981年で、米国で最も古い歴史を持つ。このようなボディ・ファームでは、管理者たちが遺体を入念に管理している。管理者たちは、死者と生者が深く繋がっていること、死者への態度は生者への態度を反映するものだということを知っているのだ。
私はFORESTだけでなく、メリーランド大学医学部の解剖学研究室も訪れた。寄付された遺体が正しく用いられるとはどのようなことなのかを理解するためである。
アダム・プシェ教授は私をメリーランド大学医学部にある解剖学研究室へと案内してくれた。プシェ教授は同大学の教授であり、解剖学・神経生物学科の副学科長を務めている。私とプシェ教授が研究室に入っていくと、ちょうどクラスが終了するところだった。2人の学生が静かに作業台を清掃しており、寄付された遺体を収めた袋のファスナーを閉じていた。それから学生たちは台の上に淡い青色の布をかけた。
メリーランド大学は献体を受け付ける際の手順を厳しく定めている。この手順はメリーランド州保険局の中央解剖学委員会が定めたものであり、プシェ教授は同委員会の委員長を務めている。メリーランド大学の解剖学研究室では、年間4000体の遺体を取り扱っている。研究室では、提供された遺体は研修医たちにとっての患者の役割を果たしてくれる。遺体が解剖学委員会へと届けられると、追跡番号が発行される。それから、遺体は左右どちらかの肩にRFIDチップを埋め込まれる。この手順はメリーランド州独自のものである。
メリーランド大学の研究室は、個人認証用のバッジと、プシェ教授自身が定めた厳格な規則の両方によって守られている。私の訪問時間も、学生への影響を最小限に抑えるように注意深く設定されたものだ。私は研究室内にあった棚の写真を参考のために撮らせてくれないかとプシェ教授に頼んでみた。その棚には、肝臓や胆のうなどといった臓器の検体が新鮮な状態で陳列してあったのだ。これらの検体は特定の病気を持った遺体提供者から摘出されたのだという。しかし、プシェ教授は丁重に私の依頼を断った。遺体提供者の尊厳は守られなければならないのだ。博物館で展示されている1世紀も前の遺体であっても、例外ではない。このように、いずれは医者となる学生たちに、プシェ教授は遺体提供者の尊厳を守ることの大切さを教えようとしている。学生たちは生きた患者の体と同じように、提供者の遺体を扱うことを求められる。メリーランド大学の学生たちは、問診表だけでなく、遺体のカルテをつけることも求められている。嚢胞や、骨折の跡、生前に受けた手術など、遺体の既往歴に関わるものが見つかるたびに、それを記録するのである。学生たちが提供された遺体について研究室の外で話をするときは、「HIPAA法(医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律)」に定められた諸規則に従わなければならない。
「学生たちは初日から医者となるのです」と、プシェ教授は言う。「学生たちには適切な言葉遣い、適切な振る舞いをしてもらう必要があるのです。死者の尊厳を尊重させることこそが、学生たちに医者として適切な言動を教える正しい方法だと私は強く信じています。それだけでなく、全ての教員が常に一貫して死者を尊重し、学生たちの手本になることも重要です」 。
プシェ教授の研究室は間もなく改装される予定だ。プシェ教授の構想では、未来の医者たちの置かれる労働環境を再現した空間に生まれ変わるという。研究室では現在、70年代風の蛍光灯を照明として用いている。改装後は、手術室で見られるのと同じLEDの照明装置やデータを表示するパネルが加わる。拡張現実(AR)技術は手術や他の医療行為へとますます導入されてきている。近い将来、遺体の上に必要な図や指示などがすべて仮想的に表示され、学生たちの助けとなるのではないかと、プシェ教授は期待している。
技術の進化によって、将来的に献体は必要なくなるだろうかと、私はプシェ教授に尋ねた。プシェ教授は技術には医療を改善する可能性があると考えており、医学生に仮想現実(VR)で訓練を提供するという実験もしたことがある。しかし、新しい技術はい …
- 人気の記事ランキング
-
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機
- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ