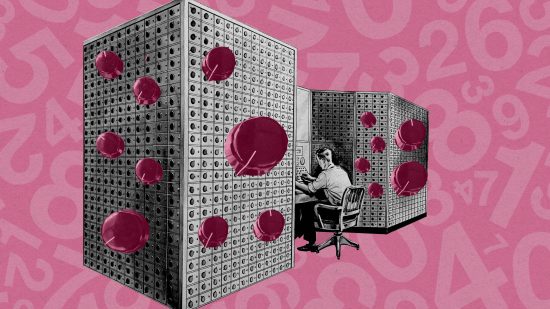アップル・ウォッチの
「緑の葉」の向こう側——
ブラジルの疑惑の森を訪ねた
「カーボンニュートラル」を掲げるアップル・ウォッチのパッケージに印刷された小さな緑の葉。その背後には、同社が設立した2億ドル規模の環境基金が投資するブラジルの巨大ユーカリ植林事業があった。「緑の砂漠」とも呼ばれる現地を訪ねると見えてきたものとは。 by Gregory Barber2025.09.08
- この記事の3つのポイント
-
- テック企業が気候目標達成のため、従来の森林保護から新たな植林による「炭素除去」へ投資戦略を転換している
- ユーカリ植林は速い成長と確実性で炭素クレジット市場を席巻するが、「緑の砂漠」との批判も根強く残る
- アップルが27万ヘクタール規模で進める「50対50」混合プロジェクトは、木材業界の経済論理を変える可能性を秘めている
日が暮れ始め、幹線道路から20キロメートルほど離れた地点で、私たちの車は揺れ、やがて止まってしまった。そこは、奇妙な森の外れだった。
この森は、植物学の暗黙のルールを意に介さないかのように生い茂っていた。下草は一切なく、前景も背景も存在しない。ただむき出しの木の幹が壁のように並び立ち、30メートルほどの高さでようやく葉を広げていた。木々の列はニューヨーク市の1街区分ほど続き、その両端は、土と草が入り混じる乱雑な野原へと唐突に途切れていた。その光景は、資金難で頓挫し、最初の建物だけが取り残されたマンション開発地の廃墟を思わせた。
沈む夕日を背に佇む木々は、奇妙だが目を見張るような眺めだった。私たちはブラジル南西部の人里離れた自然保護区を出たばかりの通信圏外にいたが、私は写真を撮ろうとスマートフォンを取り出した。一緒に旅をしていた、近隣育ちで地理学者兼翻訳家のクラリアナ・ヴィレラ・ボルゾーネの不安そうな顔に、パッとおもしろがるような表情が浮かんだ。私のカメラロールはすでにユーカリの写真でいっぱいだったのだ。
あらゆる丘や道沿いにユーカリの木が生えており、進めば進むほど次々と現れるようだった。車が止まった未舗装道路の向かい側では、別の牧草地が伐採されて植林の準備が進んでいた。かつて放牧牛のために日陰を提供していたまばらな低木や木々はすでに切り倒され、積み上げられており、それはまるで更新世の墓場のような光景だった。
ボルゾーネの友人や隣人の間では、このようなユーカリ植林地の美しさについて意見が分かれていた。ブラジル中央部を斜めに横切る広大な熱帯サバンナ「セラード」にもたらされた秩序と常緑を好む人もいた。本来のセラードは、ねじれた低木が点在し、年の大半が茶色く乾燥した景観だった。そして、その植物の多くは数十年前に牛の牧草地にするために伐採され、さらに背の低い植物しか残らない、より乾いた風景となっていた。その土地に木々が戻り、美しいと感じられるようになっていたのだ。
一方で、その美しさは幻想に過ぎないと考える人たちもいた。そのような人々は、このユーカリ植林地を「緑の砂漠」と呼んでいた。遠目には自然の豊かさを連想させるが、実際は土と静寂しかないという意味だ。彼らは、これらは動物が生息し、下草が生い茂る「森林」ではなく、せいぜい将来の大規模火災の燃料に過ぎないと批判した。ユーカリの旺盛な成長によって土地はさらに乾燥しており、このような懸念はラテンアメリカ全体に共通するものだった。チリでは、整然と並ぶユーカリの列が「緑の兵士」と呼ばれていた。見渡す限りびっしりと並ぶ木の幹の中で、迷子になるのは容易に想像できた。
ユーカリを植林した木材企業は、こうした批判を、世界中で悪者扱いされているユーカリ属に対する風刺だと反論する。そして、持続可能な森林認証を取得していることや、防火対策に多額の投資をしていること、さらには鳥の鳴き声を録音するマイクを設置しており、植林地が不毛の地ではないことを示していると主張する。人々がこの木々の見た目を好むかどうかは別として、ユーカリは人類の需要を満たしており、世界中の紙やパルプ製品への飽くなき需要に応えている。世界のトイレットペーパーやティッシュペーパーの原料の多くはブラジルで栽培されており、木材企業はそれを「良いことだ」と主張する。「ここで責任を持って、猛烈な勢いでユーカリを育てることで、他の場所の木を守ることができる」という理屈だ。
しかし、私がこの地を訪れた理由は、アップルだった。そして、マイクロソフト、メタ(Meta)、TSMC、さらに数多くの中小テック企業も同様だった。気候変動への対応目標の達成期限が迫り、新たなデバイスやAIデータセンターへの需要が高まる中、テック企業の幹部たちは本社から何千キロも離れた場所にあるこの地に向かって奔走し、時につまずきながらもたどり着いていた。まさにこの近くで、彼らは史上最大規模の炭素クレジット取引を締結したばかりだった。テック企業は今、この木に新たな問いを投げかけている。すなわち、ラテンアメリカのユーカリは、気候問題へのスケール可能な解決策となり得るのか? という問いだ。
実務的な観点では、その問いへの答えは明らかに思えた。熱帯地方でユーカリがいかに速く、確実に育つかについて、異を唱える者はいなかった。この知見は、木材や紙のバイオマスに関する数十年にわたる科学的研究とデータ蓄積の成果だった。一本の木の約47%は炭素で構成されており、つまり植林地1ヘクタールあたりに数トンの炭素が蓄積され得るということだ。その様子は、道沿いの木々を見れば、リアルタイムで観察できる。明日またこの若木を見に来れば、数ミリ単位で新たに固定された炭素、そしてリグニンによって固められたセルロースの連鎖が確認できるだろう。
同時に、アップルをはじめとするテック企業は、ブラジルのセラードや他の地域で長年論争の的となってきた産業、そして木そのものに対しても投資していた。彼らはその豊富な資金と技術力を活かし、木材生産をより持続可能なものに変え、在来植物の保全を進め、水の使用量も減らそうとしていた。だが、この地でその取り組みを受け入れるのは容易ではなかった。すでに数十万ヘクタールの牧草地で植林の準備が進められている中、干ばつや火災に見舞われるこの土地でさらに植林を増やすことに、将来への明るい展望を抱くのは難しかった。批評家たちは、こうした取り組み自体が、結局は利益を目的としたさらなる植林を正当化する口実にすぎないと非難していた。
ボルゾーネと私は、ユーカリの成長をただ眺めているつもりはなかった。庭なのか、森なのか、砂漠なのか。味方なのか、敵なのか。それはもはや重要ではなかった。南十字星が夜空に浮かび上がり、私たちのガソリンタンクが空になった今、私たちは荷物をまとめ、ユーカリの林を縫うように走る未舗装の道を歩き出した。
大きな約束
私のセラードへの旅が始まったのは、その数カ月前——2023年の秋のことだった。きっかけは、女優オクタヴィア・スペンサーが「母なる自然(Mother Nature)」役としてアップルのティム・クックCEOと共演した広告だった。アップルは2020年に、2030年までに「実質ゼロ」を達成するという目標を掲げた。つまり、その時点で同社のノートパソコン、プロセッサー、スマートフォン、イヤホンといったすべての製品が、大気中の二酸化炭素濃度を増加させることなく製造されることになる。「最初に私を失望させるのは誰?」と、母なる自然は狡猾な笑みを浮かべて問いかけた。産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑えるという国連目標に向けて、多くの企業が2030年までの行動を掲げている。すでにその3分の1の時間が過ぎているが、進捗状況はどうだろうか。
クックCEOは、アップル・ウォッチがこの取り組みの先頭を切っていると報告した。リサイクル素材の使用や、工場間の部品輸送に航空便ではなく船便を用いたといった工夫により、一部の製品はすでにカーボンニュートラル(炭素中立)を実現している。この特別なアップル・ウォッチには、アップルの象徴的ななめらかな白い箱に緑の葉のラベルが付いていた。
批評家たちはすぐに、アップルが依然として排出を続けている中で個別製品に「カーボンニュートラル」とラベルを貼るのは、都合のよい会計処理に基づく早すぎる勝利宣言ではないかと批判した。しかし、アップル・ウォッチの事例は、同社が抱く壮大な野心を物語っていた。同社によれば、再生可能エネルギーの導入やリサイクル素材の活用などによって、2015年以降の排出量を75%削減したという。発表直後、アップルの環境イニシアチブ部門を率いるクリス・ブッシュ部長は、「私たちは常に排出削減を最優先に考えています。そこから始めなければならないのです」と語った。
同社は、排出量を100%相殺する方法をすべて見つけられたわけではないことも認めていた。しかし、そこには新たな取り組みが始まっていた。
1990年代以降、企業は主に排出の「回避」を根拠に炭素クレジットを購入してきた。例えば、伐採される予定だった森林を保護することで、失われなかった炭素をクレジットに換算するという手法だ。しかし炭素市場の拡大とともに、「炭素の算定」への懐疑も強まった。詐欺やずさんな科学的根拠に加え、森林伐採の回避が別の場所での伐採を引き起こす場合もあり、回避策の効果が相殺されることも多かった。かつては「回避された排出量」によるクレジットに依存していた企業も、もはやそれを信頼できなくなっている(消費者の多くも同様で、中には過去の炭素プロジェクトをもとにアップルがアップル・ウォッチを「カーボンニュートラル」と主張したことに対して、訴訟を起こした者もいる)。
とはいえ、二酸化炭素排出を「相殺したい」という需要そのものが消えたわけではない。むしろ、AIによる電力消費で排出が増え、企業が気候目標の達成から遠ざかっている今、そのニーズはさらに高まっている(そして排出量削減を主張する手法にも疑問が生じている)。アップルにとっては、最も楽観的な見通しを立てた場合ですら、その差は大きい。同社は2024年に70万トンのCO₂を相殺したと報告しているが、2030年の …
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している