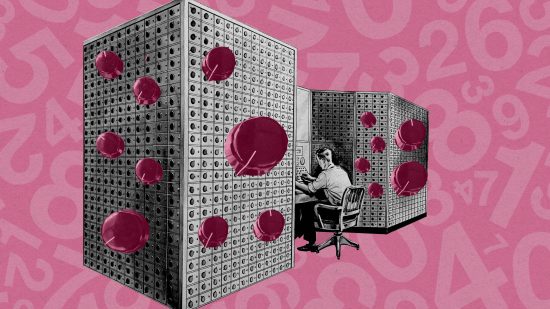「Manus」が火付け役、
中国発AIエージェントは
世界を席巻するか?
中国のスタートアップが開発した「Manus(マヌス)」はAIエージェントブームを巻き起こした。これを皮切りに中国では汎用AIエージェント開発ラッシュが始まり、海外進出を狙う動きが活発化している。 by Caiwei Chen2025.06.16
- この記事の3つのポイント
-
- 中国でAIエージェントブームが到来し多くのスタートアップ企業が参入
- AIエージェントはLLMを基盤とし物事を自律的に遂行するよう設計されている
- 大手テック企業も独自のAIエージェントを開発、アプリ群と連携する構想も
中国では昨年、人工知能(AI)革命を支える基盤モデルがブームになった。つまり、あらゆる用途に対応できる大規模言語モデル(LLM)である。今年はそのブームの焦点がAIエージェントへと移っている。AIエージェントは、ユーザーの問いに答えることよりも、ユーザーのために自律的に物事を遂行することに重きを置いたシステムである。
現在、中国では多くのスタートアップ企業が、電子メールの返信、休暇の計画のためのインターネット閲覧、さらにはインタラクティブなWebサイトのデザインまで可能な、汎用デジタルツールの開発に取り組んでいる。多くは、汎用AIエージェント「Manus(マヌス)」の登場に続いて、ここ2カ月の間に次々と現れたものだ。Manusが3月上旬に限定公開されると、招待コードを求めるユーザーが殺到し、ソーシャルメディアでは数週間にわたって熱狂が巻き起こった。
これらの新興AIエージェントは、大規模言語モデルそのものではない。むしろ、大規模言語モデルを基盤として構築され、物事を実行するために設計されたワークフロー型の構造を備えている。また、多くのシステムはAIとの対話方法にも変化を取り入れている。単にユーザーと会話するのではなく、外部ツールを活用し、指示を記憶することで、航空券の予約、スケジュール管理、調査といった複雑なタスクを管理・遂行するよう最適化されている。
この種のAIエージェントの開発において、中国は主導的な役割を果たす可能性がある。アプリが密接に統合されたエコシステム、迅速な製品開発サイクル、そしてデジタル技術に精通したユーザー層が、AIの生活への浸透を後押しするからである。
現在、中国の有力なAIエージェント系スタートアップの多くは、グローバル市場をターゲットにしている。これは、欧米の最高性能のAIモデルが中国国内で利用できないためだが、この状況もすぐに変わる可能性がある。バイドゥ(Baidu)やテンセント(Tencent)などのテック大手は、独自のAIエージェントを準備中であり、自社の膨大なアプリ群からデータを引き出し、国産スーパーアプリにタスク自動化を組み込む構想を持つ。
有用なAIエージェントのあり方を定義する競争が進む中、野心的なスタートアップ企業と既存の大手テック企業が混在し、実際にどのようにこれらのツールが機能し、どのようなユーザーを対象とするのかを検証している状況だ。
汎用エージェントの基準になったManus
武漢に拠点を置くスタートアップ企業のバタフライ・エフェクト(Butterfly Effect)が開発したManusにとって、この数カ月はまさにつむじ風のような展開だった。同社は、米国のベンチャーキャピタルであるベンチマーク(Benchmark)が主導する資金調達ラウンドで7500万ドルを調達。製品を世界規模で展開する大規模なロードショーを実施し、新たに数十人の従業員を雇用した。
Manusは、5月の一般登録が始まる前から、幅広い消費者向けAIエージェントが目指すべき目標の基準点として認識されていた。この「汎用」エージェントは、企業向けに限定的な雑務を処理するのではなく、旅行の計画、株の比較、子どもの学校の課題支援など、日常的なタスクを手助けできるよう設計されている。
従来のAIエージェントと異なり、Manusはブラウザーベースのサンドボックスを採用しており、ユーザーはまるでインターンを監督するかのように、Webページをスクロールしたり記事を読んだり、アクションをコーディングしたりする様子をリアルタイムで見守ることができる。さらにManusは、明確化のための積極的な質問を投げかけ、将来のタスクのコンテキストとして機能する長期記憶も備えている。
「Manusは、優れた製品体験を提供するAIエージェントの代表例です」。こう話すのは、米国カリフォルニア州パロアルトに拠点を置くスタートアップ企業シミュラー(Simular)のアン・リー共同創業者兼CEOである。同社はバーチャル・コンピューターを操作するタイプのAIエージェントである、コンピューター・ユース・エージェントを開発している。「中国のスタートアップ企業は、消費者向け製品の設計において非常に大きな優位性を持っていると考えています。国内の熾烈な競争が、迅速な実行力と製品の細部への徹底した配慮を促しているからです」。
Manusの場合、競争のスピードは非常に速い。例えば、話題の後続製品である「Genspark(ジェンスパーク)」と「Flowith(フローウィス)」は、すでにManusと同等かそれ以上のベンチマークスコアを誇っている。
バイドゥ(Baidu)の元幹部であるエリック・ジンとケイ・ジューが率いるジェンスパーク(Genspark)は、同社が「マルチコンポーネント・プロンプティング」と呼ぶ手法により、多数の小規模な「スーパーエージェント」を連携させている。これらのエージェントは複数の大規模言語モデルを切り替えて使用することができ、画像とテキストの両方に対応し、スライド資料の作成から電話の発信まで幅広いタスクをこなす。Manusが、エージェントがバーチャル・ウィンドウ内のWebブラウザーを人間のように操作できるようにする、オープンソースの人気製品であるBrowser Use(ブラウザー・ユース)に大きく依存しているのに対し、Gensparkは …
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している