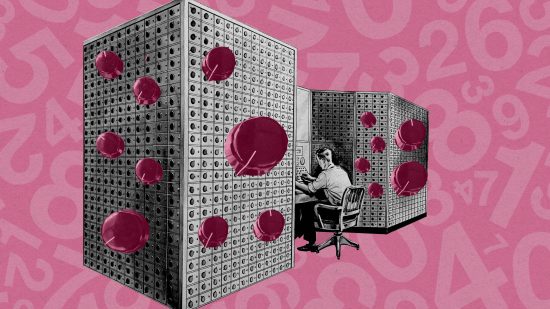巨大テック企業が飛びつく炭素除去技術「BECCS」の落とし穴
マイクロソフトなどの企業が、CO₂排出を相殺する技術として二酸化炭素回収・貯留付きバイオエネルギー(BECCS)に投資している。だが、BECCSの計算は複雑であり、実際に排出量実質ゼロあるいはカーボンネガティブを実現できるかどうかは疑問が残る。 by Casey Crownhart2025.10.31
- この記事の3つのポイント
-
- BECCSが炭素除去契約の約70%を占め、マイクロソフトなど大企業が大きく投資している
- 企業の排出量相殺需要が高まる中、BECCSは既存施設活用で低コスト実現が可能とされる
- 一方、炭素計算の複雑さや廃棄物の他用途転用リスクなど技術的課題が山積している
大気中から二酸化炭素を回収することが大きなビジネスになりつつある。企業は自社の排出量を相殺できる技術に高額を支払っている。
現在、発表された炭素除去契約の約70%が1つの技術に集中している。「二酸化炭素回収・貯留付きバイオエネルギー(BECCS)」である。基本的なアイデアは、樹木やその他の種類のバイオマスをエネルギーに利用し、それを燃焼する際に排出される二酸化炭素を回収するというものだ。
マイクロソフトなどの巨大テック企業を含む大企業がこの技術に大きく賭けているが、BECCSにはいくつかの潜在的な問題がある。本誌のジェームス・テンプル編集者が先日の記事で詳述したとおりである。そして、これらの懸念の一部は、私たちが取り上げる炭素オフセットや代替ジェット燃料などの他の気候技術と似たような問題を反映している。
炭素計算は複雑になり得る
BECCSの最大の問題の1つを説明するために、その炭素会計の論理を整理する必要がある(この技術は多くの異なる形態のバイオマスを使用できるが、ここでは樹木について話していると仮定しよう)。
樹木が成長するとき、大気中から二酸化炭素を吸収する。これらの樹木は伐採され、紙の製造などの意図された目的に使用される。残余物質は、その後処理され、燃焼されてエネルギーになるか、あるいは、廃棄物になるかもしれない。
このサイクルは、理論的にはカーボンニュートラルである。バイオマスの燃焼による排出量は、植物の成長中に大気から除去された量によって相殺される(バイオマスにするために樹木を伐採した後、新たに植林すると仮定している)。
では、バイオマスを燃焼する施設に炭素除去装置が追加され、排出量を回収すると想像してみよう。サイクルが論理的に以前はカーボンニュートラルだったとすれば、今度はカーボンネガティブになる。実質的に、排出量が大気から除去される。すばらしい響きだ。文句なしだ。
しかし、この計算にはいくつかの問題がある。1つは、木材の伐採、輸送、処理中に生産される可能性のある排出量を除外していることだ。樹木を植えたり作物を育てたりするために土地を開拓する必要がある場合、その転換も結果的に二酸化炭素を放出する可能性がある。
炭素計算の問題は、炭素オフセットに関するテンプル編集者の記事を読んだことがあれば、少し馴染みがあるかもしれない。炭素オフセットは、人々が他者の排出回避に対して支払うプログラムである。特に、プロパブリカ(ProPublica)のリサ・ソングと共同で実施した2021年の調査では、このいわゆる解決策が実際には数百万トンの二酸化炭素を大気中に追加していることが明らかになった。
炭素回収は汚染施設を定着させる可能性がある
BECCSの大きな利点の1つは、既存の施設に追加できることである。大気から直接炭素を回収する施設と比べて、建設費用が少なくて済み、コストを抑えられる。そのため、BECCSは現在、直接大気回収や他の形態の炭素除去よりもはるかに安価である。
しかし、既存の設備を稼働し続けることは、長期的には排出量や地域コミュニティにとって良いことではないかもしれない。
これらの施設が放出する汚染物質は二酸化炭素だけではない。バイオマスやバイオ燃料の燃焼は、粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素など、人間の健康に害を与える排出物を放出する可能性がある。炭素回収装置は二酸化硫黄などの汚染物質の一部を捕捉するかもしれないが、すべてではない。
廃棄物が他の用途に使用されないという仮定は誤っているかもしれない
廃棄物を使用するのは素晴らしく聞こえるが、テンプル編集者が以前の記事に書いたように、ここには大きな但し書きが潜んでいる。
しかし、廃棄物について浮上する重要な問題は次のとおりである。それは他の方法で燃焼されたり分解されたりしていたのか、それとも炭素を大気から遠ざける他の方法で使用されていた可能性があるのか?
バイオマスは、プラスチック、建築材料、さらには作物がより多くの栄養素を得るのに役立つ土壌添加剤の製造など、他の用途に使用できる。したがって、BECCSかゼロかという仮定は欠陥がある。
さらに、廃棄物が価値のあるものになり始めると奇妙なことが起こる。廃棄物をより多く生産するインセンティブが生まれるのだ。一部の専門家は、企業がBECCSでより多くの材料を作るために、必要以上に多くの樹木を伐採したり、より多くの森林を開拓したりする可能性があることを懸念している。
これらの廃棄物問題は、持続可能な航空燃料をめぐる議論を思い起こさせる。これらの代替燃料は、作物廃棄物や使用済み食用油を含む膨大な範囲の材料から作ることができる。しかし、これらのクリーン燃料への需要が急増するにつれて、事態は少し奇妙になってきた。穀物から新たに作った油を使用済み食用油と偽装しようとする詐欺の報告さえある。
BECCSは潜在的に有用な技術である。だが、気候技術の多くのものと同様に、すぐに複雑になり得る。
テンプル編集者は何年もの間、炭素オフセットと炭素除去について記事を書いてきた。先日この件について話したとき、彼はこう言った。「単に排出量を削減して、いじくり回すのをやめればいいんです」。
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している
- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者
- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。