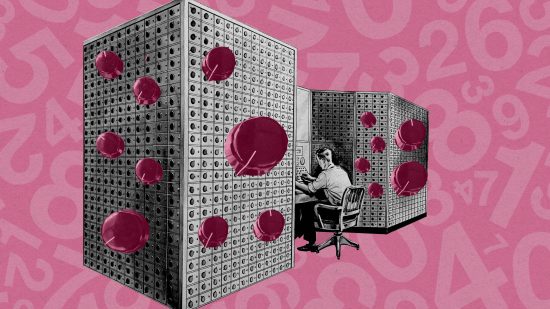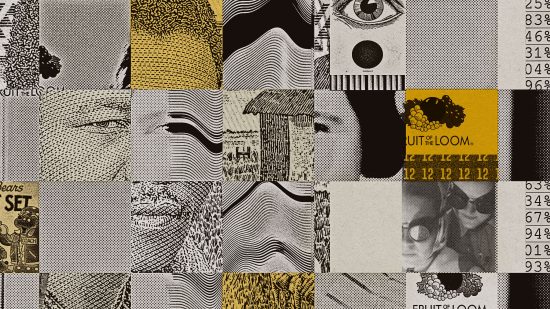シリコンバレーか北京か——米中AI覇権の行方をFT・本誌記者が考察
最先端技術で先行する米国か、大規模実装を進める中国か。「スピードは覇権ではない」——フィナンシャル・タイムズとMITテクノロジーレビューの記者が、AI覇権争いの新たな視点を提示する。 by Caiwei Chen2025.11.04
- この記事の3つのポイント
-
- FTとMITテクノロジーレビューによる生成AI革命による世界のパワーバランス変化を検証する共同企画
- 中国がAI論文引用数と特許で米国を上回り、効率的なオープンソースモデル開発と社会全体への迅速な導入で優位性を構築
- 半導体制裁が中国の制約要因となる一方、AI覇権の定義や技術展開方法論の違いが今後の競争構図を左右する可能性
「ステート・オブ・AI(The State of AI)」は、AIが世界の力関係をどのように再構築しているかを検証する、フィナンシャル・タイムズとMITテクノロジーレビューの共同企画である。6週間にわたり、両誌の執筆陣が、生成AI革命が世界のパワーバランスをどう変えているかという一側面について議論する。
第1回は、フィナンシャル・タイムズのテクノロジー・コラムニスト兼イノベーション編集者のジョン・ソーンヒルと、MITテクノロジーレビューの中国担当記者であるチェン・ツァイウェイが、技術的覇権をめぐるシリコンバレーと北京の争いについて考察する。
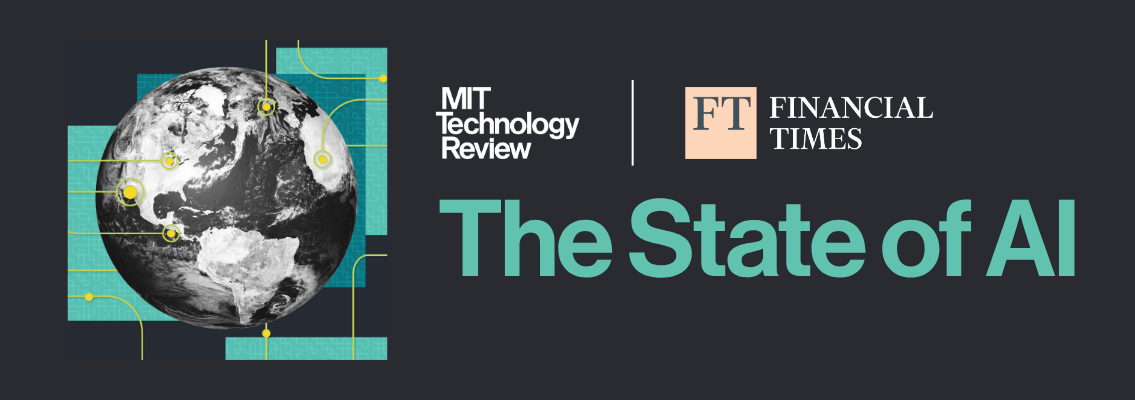
ジョン・ソーンヒル(フィナンシャル・タイムズ)の見解
海外から見ると、中国が21世紀のAI超大国として台頭するのは時間の問題のように思えます。
西側諸国ではまず、米国の半導体技術における大きな優位性、最先端のAI研究、データセンターへの莫大な投資に注目しがちです。伝説的投資家のウォーレン・バフェットはかつて「米国に逆らって賭けるな」と警告しました。2世紀以上にわたり、「人間の潜在力を解き放つインキュベーター」として米国に匹敵する国はなかったという彼の指摘は正しい。
ですが現在の中国は、テクノロジー分野における「殺人」に等しい行動をとるための手段、動機、機会をすべて備えています。AIを最大限に開発・展開するために社会全体のリソースを動員するという点では、中国に対しても軽率に賭けない方が良いかもしれません。
データはこの傾向を如実に示しています。AI論文と特許においては中国がリードしており、スタンフォード大学の人間中心のAI研究所(Human-Centered AI Institute)がまとめた「AIインデックス・レポート2025」によれば、2023年時点で中国は全引用数の22.6%を占め、欧州の20.9%、米国の13%を上回っています。また、AI特許においても2023年時点で中国が69.7%を占めている状況です。もちろん、最も引用された上位100本の論文では米国が引き続き優位を保っていますが(2023年は50本に対して中国は34本)、そのシェアは着実に減少しています。
同様に、米国は最高レベルのAI研究人材で中国を上回っていますが、その差は縮まっています。米大統領経済諮問委員会(CEA)の報告によると、2019年には世界のトップAI研究者の59%が米国で働いていたのに対し、中国は11%でした。しかし2022年にはその数字は42%と28%になっています。
今後、トランプ政権の外国人H-1Bビザ保有者への制限強化により、米国にいる中国系AI研究者がより多く帰国する可能性が高い。人材バランスはさらに中国に有利に動く可能性があります。
技術そのものに関しては、2024年に米国の機関が世界で最も注目すべきAIモデル40個を生み出したのに対し、中国は15個でした。しかし中国の研究者は、限られたリソースでより多くの成果を出す術を学んでおり、オープンソースのDeepSeek(ディープシーク)-V3やアリババ(Alibaba)のQwen(クウェン) 2.5-Maxを含む最先端の大規模言語モデルは、アルゴリズム効率の面で米国の最高峰モデルを上回っています。
中国が今後本当に優位性を発揮する可能性があるのは、こうしたオープンソース・モデルの応用分野かもしれません。エアストリート・キャピタル(Air Street Capital)の最新レポートによると、中国はAIモデルの月間ダウンロード数で米国を追い抜いています。AI対応のフィンテック、eコマース、物流において、中国はすでに米国を上回っているのです。
おそらく最も興味深く、そして将来的に最も生産的となる可能性のあるAI応用分野は、ハードウェア、特にドローンや産業用ロボットの分野かもしれません。身体性を持つAI(embodied AI)へと研究が進む中で、先進製造業における中国の強みがより際立つはずです。
テクノロジー・アナリストで、『Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future(猛烈な勢い:中国の未来を創造する探求)』(未邦訳)の著者であるダン・ワンは、製造プロセスに関する知見の構築において中国の「工学国家」としての強みを的確に指摘しています。ただし同時に、その工学的思考を社会領域に適用することの有害な影響についても言及しています。「中国はあらゆる側面で技術的に強くなり、経済も活性化している」と彼は私に語りました。「しかし、抑圧の存在は非常に現実的であり、その傾向はあらゆる側面で悪化している」とも話しています。
チェンさん、中国のAIにおける「夢」の強みと弱みについて、あなたの見解をぜひ聞かせてもらえますか。中国の「工学的社会統制」は、同国の技術的野心にどの程度の影響を及ぼすと思いますか。
チェン・ツァイウェイ(MITテクノロジーレビュー)の回答
こんにちは、ジョン。
米国が最先端研究とインフラにおいて明確なリードを保っているというあなたの指摘は正しい。しかし、AIで「勝つ」ということは、実に多様な意味を持ち得るものです。ジェフリー・ディンは著書『Technology and the Rise of Great Powers(技術と大国の台頭)』(未邦訳)の中で、直感に反する見解を示しています。すなわち、AIのような汎用技術においては、長期的な優位性はしばしば、技術が社会全体にどれほど広範かつ深く浸透するかにかかっているというものです。そしてこの点で、中国はその競争において有利な位置にいます(ただし「殺人」という表現はやや過激かもしれません)。
半導体は中国にとって依然として最大のボトルネックです。輸出規制により、最先端のGPUへのアクセスは大幅に制限されており、購入者はグレーマーケットに流れ、研究機関は禁輸対象となったエヌビディア(Nvidia)の在庫をリサイクルまたは修理せざるを得ない状況にあります。国内の半導体開発プログラムが拡大しているとはいえ、最上位の性能におけるギャップは依然として残っています。
しかし、これらの制約が逆に、中国企業を異なる戦略へと向かわせています。計算資源の共有、効率性の最適化、そしてオープンウェイト・モデルの公開です。たとえば、DeepSeek-V3の訓練にはわずか260万GPU時間しか使われていません。これは米国の同等モデルに比べてはるかに少ない。アリババのQwenシリーズは現在、世界で最もダウンロードされているオープンウェイト・モデルの一つとなっており、ジプー(智谱:Zhipu)やミニマックス(Minimax)のような企業も、競争力あるマルチモーダルおよび動画モデルの開発を進めています。
中国の産業政策によって、新しいモデルは研究段階から実装段階まで迅速に移行できます。地方政府や大手企業はすでに、行政、物流、金融の現場で推論モデルを導入しています。
教育も中国の優位性の一つです。主要大学ではAIリテラシー教育がカリキュラムに組み込まれ、労働市場がそれを求める前に学生たちがスキルを身につけられるようになっています。中国教育部はまた、すべての学齢期の子どもにAI教育を取り入れる計画を発表しています。「工学国家」という表現が中国と新技術の関係性を正確に言い表しているかは分かりませんが、数十年にわたるインフラ整備とトップダウンの政策調整により、中国の体制は大規模導入を驚くほど効果的に進めています。他国に見られるような社会的抵抗も非常に少ない。この大規模導入は、当然ながら、迅速な反復改善を可能にしています。
スタンフォード大学のAIインデックス・レポート2025によると、中国の回答者は世界で最もAIの未来に楽観的であり、その楽観度は米国や英国を大きく上回っています。パンデミック以降、中国の経済成長が20年以上ぶりに減速していることを考えると、これは注目に値するものです。政府や産業界の多くは今、AIを次の成長の起爆剤とみなしています。楽観主義は強力な推進力となり得るが、それが経済の減速期を乗り越えて持続できるかどうかは、依然として未知数です。
社会統制は引き続き状況の一部ですが、異なる種類の野心が新たに形成されつつあります。新世代の中国人AI起業家たちは、私が見てきた中で最もグローバル志向であり、シリコンバレーのハッカソンとドバイのピッチイベントの間を自在に行き来しています。多くは英語と世界のベンチャーキャピタルのリズムに精通しており、前の世代が「中国」というラベルの重さに苦しんでいたのに対し、彼らは最初から静かに多国籍企業を築いています。
米国は依然としてスピードと実験性では先行しているかもしれませんが、中国はAIが国内外の日常生活の中にどのように組み込まれていくかを方向づける立場にあるかもしれません。スピードは重要だが、それは覇権と同義ではありません。
ジョン・ソーンヒル(フィナンシャル・タイムズ)の返答
「スピードは覇権ではない」というあなたの指摘はまさにその通りです(そして確かに「殺人」という表現は強すぎたかもしれません)。また、中国のオープンウェイト・モデルにおける強みと、米国がプロプライエタリ(独自)モデルを好む傾向の違いを強調してくれた点も重要です。これは、単に2つの異なる国家の経済モデルの対立ではなく、技術をいかに展開するかという2つの異なる方法論の衝突でもあります。
オープンAI(OpenAI)のサム・アルトマン最高経営責任者でさえ、今年初めにこう認めています。「我々はここで歴史の間違った側にいた。異なるオープンソース戦略を模索する必要がある」と。これは今後、非常に注目すべきサブプロットになるでしょう。果たして、誰が正しい判断を下したのか?
MITテクノロジーレビューの関連記事
- 実世界での使用に関しては、AI搭載のおもちゃとコンパニオン・デバイスが中国で勢いを増している。
- 中国でかつて狂乱的だったデータセンター建設は壁にぶつかっている。制裁とAI需要が変化する中、利害関係者がそれをどのように解決しているかを現地で見た。
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している
- ツァイウェイ・チェン [Caiwei Chen]米国版 中国担当記者
- MITテクノロジーレビューの中国担当記者として、グローバルなテクノロジー業界における中国に関するあらゆるトピックを取材。これまで、ワイアード(Wired)、プロトコル(Protocol)、サウスチャイナ・モーニング・ポスト (South China Morning Post)、レスト・オブ・ワールド(Rest of World )などのメディアで、テクノロジー、インターネット、文化に関する記事を執筆してきた。ニューヨークのブルックリンを拠点に活動している。