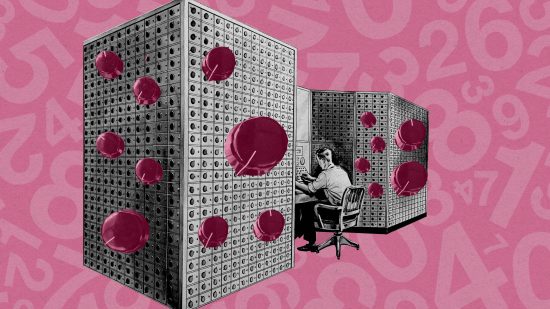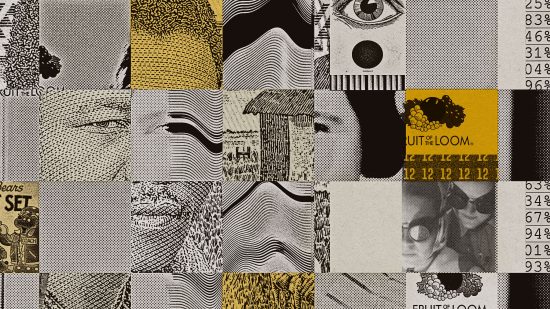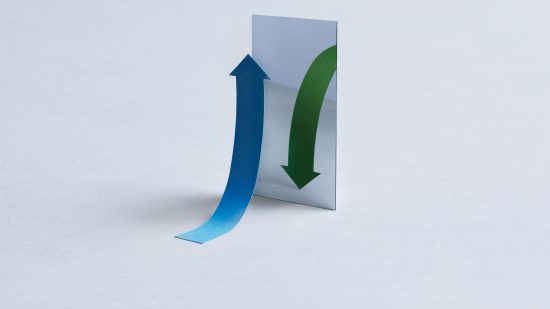ルイス・ロビン敬:テクノロジーと「仲間感」で目指す循環型社会
Social Innovation Japan代表理事のルイス・ロビン敬は、プラスチックごみ削減をテーマに始めた「mymizu」プラットフォームを世界に広げ、人々が環境問題に取り組むマインドセットを変えようとしている。 by Yasuhiro Hatabe2025.06.10
海洋プラスチックごみ問題の深刻化や気候変動への関心が高まっているが、地球環境の保全という大きな課題に対して個人レベルでいかに取り組むかは悩ましい問題だ。一般社団法人Social Innovation Japanの代表理事であるルイス・ロビン敬は、マイボトルへの無料給水スポットを共有するプラットフォーム「mymizu」を立ち上げ、2020年に「Innovators Under 35 Japan(35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれた。
社会インフラとしての新たな役割
それから約5年が経過し、mymizuを取り巻く環境は大きく変化している。「年々夏が暑くなり、気候変動を一般の人も実感するようになった」とルイスが語るように、社会全体の環境意識の高まりとともに、mymizuの役割も変化しつつある。
現在、mymizuアプリのダウンロード数は40万件を突破し、世界20万カ所以上の給水スポットが登録されている。国内では47都道府県すべて、合計1万3000カ所の給水スポットが設置され、全国展開を果たした。

都市部から全国、海外にも認知広がる
「2019年のリリース時はプラスチックのゴミを減らすことがメインの目標でした。この5年間で、mymizuは熱中症対策や夏の異常な暑さに対応しうる社会的インフラでもあることに気づきました」とルイスは話す。2021年からは、神戸市と共に熱中症対策としてこまめな水分補給を呼びかけるキャンペーンを実施するなど、公衆衛生の観点からの取り組みも拡大している。
mymizuの利用は現在、東京や大阪、名古屋、神戸といった都市部が中心となっている。より幅広い地域でmymizuを知ってもらうため、2024年4月に「mymizu自治体アライアンス」を立ち上げ、地方自治体との連携を進めているところだ。現在は静岡県御前崎市、長野県白馬村など11自治体が参加している。名古屋市では「mymizuモニター事業」として、市民が一定期間マイボトルを使ってプラスチックごみを減らすゲーミフィケーション・キャンペーンも実施した。「楽しくゲーム化しながら、プラごみ対策に取り組んでいます」。
インバウンド観光客の利用も大きく拡大している。「サステイナブルな観光に興味を持つ観光客が多く、観光庁もmymizuを推してくれています」。日本で体験した外国人が帰国後も使い続けるケースが多く、現在50カ国で活用されているという。台湾では、デジタル担当相を務めたオードリー・タンがmymizuに注目し、メディアやイベントで言及するなどして認知が広がりつつある。

20カ国での活動経験が導いた水への問題意識
ルイスの活動の原点は、多様な国際経験にある。エジンバラ大学で国際ビジネス学修士課程を修了後、東日本大震災をきっかけに日本へ戻り、ボランティア活動に取り組んだ。国際NGOでは6年間の人道支援活動をネパール、モザンビーク、バヌアツ、ハイチなど20カ国以上で展開。その後は世界銀行でコンサルタントとして2年半働き、2017年にSocial Innovation Japanを設立、2019年にmymizuをローンチした。
日本の水道水は世界的に見ても極めて質が高い。「こんなにおいしく安全な水がどこでも飲めるのは、世界的に見ても珍しいんです」とルイスが語るように、高品質な水道水インフラが整備されているにもかかわらず、大量のペットボトル水が消費されている現状への疑問が、mymizu誕生のきっかけとなった。
「仲間感」で深刻な課題にも楽しく取り組む
mymizuの最大の特徴は、単なるアプリではなく、ユーザーと一緒に作る共創型のプラットフォームであることだ。ユーザーが新たな給水スポットを投稿でき、削減できたペットボトル本数やCO2排出量が可視化される。Webアプリはオープンソース化され、ハッカソンを通じて新機能が開発されている。
企業との連携も積極的に進めている。ナイキとの「Nike Run Club×mymizu」キャンペーンでは、Nike Run Clubに記録された走行距離に応じて東京に給水スポットを設置するゲーミフィケーション要素を取り入れた取り組みを実施した。
ルイスが活動において最も重視するのは「仲間感」だという。「環境問題のような深刻な課題に一人で取り組むのは難しいですが、仲間と取り組めば継続できます」と語る。この哲学は、mymizuの設計思想にも深く反映されている。
「mymizuのステッカーを貼ってくれているカフェが他のmymizuのポイントを見るとすごくうれしくなる。そういう『みんなでやっている』感覚はすごく貴重で大事だと思います」とルイスは語る。この「仲間感」こそが、mymizuコミュニティの持続的な成長を支えている。
テクノロジー×コミュニティのインパクト
「テクノロジーは社会問題、環境問題を解決するために必須ですが、それにプラスして、コミュニティがより大事。技術開発だけでは問題解決にならず、人々やコミュニティと掛け合わせることで、より大きなインパクトを生み出せると思います」。
mymizuは「誰でも参加できる」ことが特徴で、「子どもからお年寄りまで誰でも使える社会的インフラ」として機能している。「環境問題は非常に幅広く、どこから手をつけるか分からない、あるいは漠然とした不安を感じている人が多くいます。マイボトルを持つという簡単で楽しいライフスタイルの変化を通じて、『私にもできる』と実感してもらい、それがより大きなアクションへと繋がっていく。みんなで一緒にアクションを起こすことに繋げたい」とルイスは語る。
女性起業家支援という新たな挑戦
ルイス率いるSocial Innovation Japanは、新たな挑戦として、女性起業家支援プログラム「ヘレナパワーズ」も手がけている。2025年3月の国際女性デーに、ヘレナ ルビンスタイン(ロレアルグループ)と共同でローンチした社会起業家育成プログラムだ。
「mymizuを立ち上げた理由は、社会問題や環境問題をみんなで一緒に楽しく解決できるような仕組みを作って、人をエンパワーすることでした」とルイスは語る。mymizuで5年半の経験を積み、「今度は女性起業家を支援したい、別の形でも人をエンパワーしていきたい」という思いから生まれた取り組みだという。
世界への挑戦と新たな可能性
「私の夢の一つは、mymizuが本当に世界中に活用できるようになること」とルイスは言う。現在のmymizuモデルは水道水が飲める国向けだが、「水道水飲めない国々でも何かできないか」と考えている。
この課題に向けて、東京大学公共政策大学院(GraSPP)で2021年から毎年開講される「テクノロジーを活用して社会問題を解決する」コースにおいて、ルイスは講師の一部を担当し、大学院生たちがエチオピア、インド、タイでのmymizu応用モデルをリサーチしている。ウォーターキオスク(個人の水販売店)との連携やゲーム化など、多様な提案が生まれているという。
こうしたマインドセット変革こそが、ルイスが目指すイノベーションだ。テクノロジーと社会的ムーブメントの力を合わせて、使い捨て文化から循環型社会へ。この転換を成し遂げるのは、「仲間感」を大切にするコミュニティだ。
◆
この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。
- 人気の記事ランキング
-
- America’s new dietary guidelines ignore decades of scientific research 「ステーキとバターを食べよ」米国の新食事ガイドラインが波紋
- This company is developing gene therapies for muscle growth, erectile dysfunction, and “radical longevity” まず筋肉増強、勃起不全・薄毛も——「長寿」治療謳う企業が試験
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- Meet the man hunting the spies in your smartphone 20年間、独裁国家を追った研究者は今、米国を監視している
| タグ |
|---|
- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者
- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。