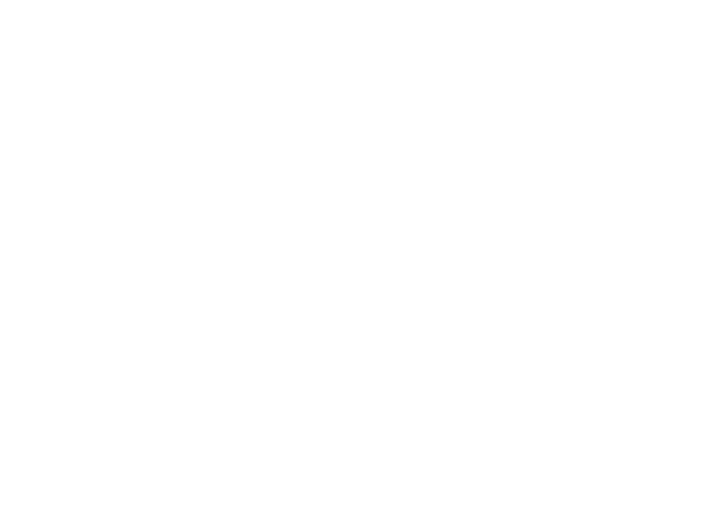世界では動植物約100万種が絶滅の危機にある。生物多様性の保全は地球規模の不可逆的な課題であるにもかかわらず、2010年に設定された2020年までの世界目標「愛知ターゲット」は、全体の1割しか達成されていない。最も解決から遠い社会課題の一つだと言える。
藤木庄五郎は、生物多様性の保全が進まない理由を、その取り組みが「お金を生まないから」だと考えた。2017年に京都大学大学院農学研究科で博士号を取得した後、バイオームを起業し、生物多様性保全とビジネスの両立に挑んでいる。京都大学在学中は、樹木群集のパターンと衛星画像の分光反射特性を組み合わせて生物多様性を広域可視化する技術開発に従事した。熱帯ボルネオ島のジャングルで3年以上かけて調査した際、商業伐採によって360度地平線まで更地と化した「元」熱帯雨林の現場を目の当たりにし、「生物多様性の保全は経済の力でしか解決し得ない」と確信する。
課題解決には、生物多様性をビッグデータとして収集し、誰でも利用可能な生物データプラットフォームをつくることが不可欠だと藤木は考える。生物データ収集のアプローチとして、世界中に存在する40億台以上のスマートフォン端末を生物の観測拠点にするアイデアを発案。スマホで撮影した画像と位置情報、日時情報から生物種の名前を自動識別する人工知能(AI)技術を開発した。2019年に国内向けにリリースした「Biome(バイオーム)」は、「いきものコレクション・アプリ」をうたい、ゲーミフィケーションやSNS の要素を積極的に取り入れたものだ。2021年11月現在約39万人に利用され、約200万件の生物分布データ収集に成功している。
資金集めが難しい領域のビジネスであるにもかかわらず、ベンチャー・キャピタルから1億円以上の資金調達に成功。しかしすでに、データ・プラットフォームからの売上で自走できる体制を構築済みだ。IPO(新規公開株)を目指し、国外での普及や新サービス開発などの事業拡大を進めている。
(畑邊康浩)
- 人気の記事ランキング
-
- What’s next for Chinese open-source AI ディープシーク騒動から1年 中国のオープンモデルが 世界の開発者を席巻している
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- EVs could be cheaper to own than gas cars in Africa by 2040 アフリカでEVがガソリン車より安くなる日——鍵は「太陽光オフグリッド」
- RFK Jr. follows a carnivore diet. That doesn’t mean you should. 「肉か発酵食品しか食べない」米保健長官が目指す「健康な米国」
- Why EVs are gaining ground in Africa アフリカ初のバッテリー工場も建設中、「次のEV市場」は立ち上がるか?