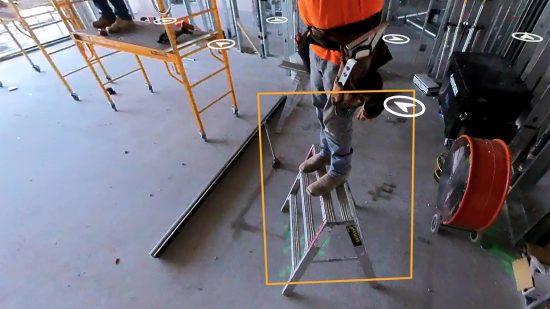フェイスブックで流通した虚偽ニュースはトランプ当選に貢献したか?
フェイスブックにメディア企業になるつもりがなくても、でたらめなニュースを放置してよいことにはならない。 by Jamie Condliffe2016.11.15
2016年の大統領選挙は、今まで以上にソーシャルメディア上で展開されたともいえる。そして今、嘘の投票結果のニュースを流したとしてフェイスブックは有権者の反感をかっている。有権者の主張が正しいか否かは別として、フェイスブックはこの問題に対応する必要がある。
フェイスブックを批判している側の主張では、不正確あるいは誤解を招くようなニュースを広めることで、フェイスブックが有権者をドナルド・トランプを大統領に選ぶように洗脳した。多くの人は、自分たちの信念がソーシャルネットワークの「エコー・チャンバー効果」(同じような立場の情報にばかり接しやすくなってしまうメディア環境)によるとは気がつかずにトランプを支持した、というのだ。
真偽不明の情報を流通させる ソーシャルメディアの負の側面がトランプに恩恵を与えたのは確かだ。カリフォルニア大学バークレー校ジャーナリズム大学院のエド・ワッサーマン学長は「トランプは自らのメッセージを、通常の内容確認を経ずに、とても影響力のある方法で発信できたのです。特に何の根拠もない一部のメディアグループが影響力を発揮し、根拠があるはずのメディアグループはほとんど人々に影響を与えませんでした」とブルームバーグに述べた。

先週末、トランプ自身もソーシャルメディアが自身の選挙運動の中心だったと説明した。「私がフェイスブック、ツイッター、インスタグラム等のフォロワー数で勢力があった事実は、各地での選挙戦の勝利に寄与していると思います。しかも選挙戦の相手は私よりも多額のお金を投じています」と、トランプは日曜日に放送されたCBSの番組『60ミニッツ』で述べた。
問題は、でっち上げのニュースがトランプ有利の選挙結果に一役買っているのではないか、だ。たとえば、ヒラリー・クリントンが武器売買に関わっているとか、ドナルド・トランプがローマ法王の承認を受けた事実はない。しかし人々はその種の話を読み、その中の多くはその話を信じただろう、とワイヤードは指摘している。
しかし、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOは、選挙に影響を与えていない、と断固として主張している。この見解は すでに二度表明されている。「フェイスブックの架空のニュースが選挙に影響を与えたなんて、まともな考えではありません」と先週ザッカーバーグCEOは主張した。さらに先週末に掲載された長文によると「皆さんの目にする99%以上のフェイスブックのコンテンツは全て確認済みです。したがって、書かれている内容が偽りで、それが選挙結果を左右したというのは極めてありえないことです」と述べた。
この種のニュースに影響力があるのか、評論家は我先に正しい答えを出そうとしている。ニューヨーク誌はトランプがフェイスブックの虚偽ニュースで勝利したと主張する。オンラインメディアのリコードは「大統領選挙の結果をフェイスブックのせいにするなんてバカなこと」だという記事を掲載した。
どちらも正しくない。
掲載されたニュースに意見を左右される人がいるのは否めない事実だが、人々がフェイスブック以外のメディアからも情報を得ているのも事実だ。現実的にはフェイスブックは単独でドナルド・トランプに勝利をもたらしてはいない。
しかし、今回の騒動で、ある一点は明確になった。フェイスブックは偽造ニュース問題を解決するべきだ。フェイスブックはメディア企業ではないし、これからもそうならないとザッカーバーグCEOはいうが、虚偽のコンテンツを配信し続ける限り、ザッカーバーグCEOの主張は受け入れがたい。
インターセプト誌の記事でサム・ビドル記者はこの状況を上手くまとめている。
トランプの勝利が完全にフェイスブックのせいかどうかはどうでもいいことだ。しかし、現在蔓延している意図的な誤報や事実無根の混乱の一端をフェイスブックが担っていることに関して、私たちはフェイスブックに少なくとも説明を要求するべきだ。
幸いなことにニューヨーク・タイムズ紙はフェイスブックの幹部数名が、自社の 影響力について懸念していると書いている。ザッカーバーグCEOは、フェイスブックは「今後も偽造ニュースを遮断する努力を続ける」と述べたが、その後「事実を確認する手順は複雑なので、慎重に進めたいと思います」と、後ろ向きな発言に転じた。
もちろんザッカーバーグCEOの言い分は正しい。しかし、10 億人以上がニュースや情報の取得に利用している以上、そもそもシンプルであるはずがない。マーク、今こそ責任を果たす時だ。
(関連記事:New York Times, The Intercept, Bloomberg, “Facebook Tweaks Its News Feed Algorithm, and the Winner Is: Facebook”)
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
| タグ | |
|---|---|
| クレジット | Photograph by AFP | Getty |
- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長
- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。