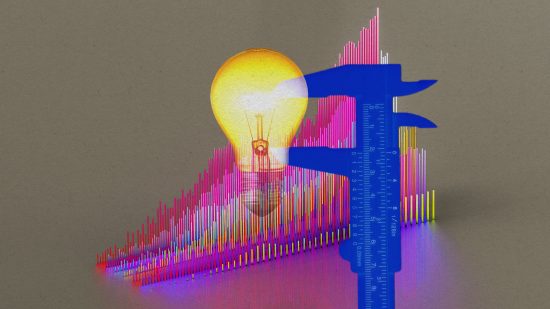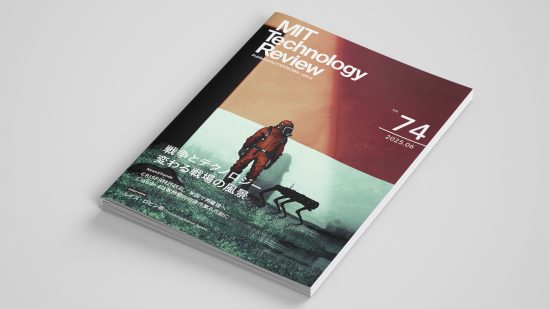「外出自粛中」でもみんなで映画を楽しむ方法
新型コロナウィルス対策として社会距離戦略の実践が求められている。だが、それでも人と交流したいのが人間だ。インスタグラムやネットフリックスの共同視聴はエンターテイメントのスタイルを変える可能性がある。 by Tanya Basu2020.04.01
インスタグラムが、「Co-watching(コ・ウォッチング、共同視聴)」機能を導入すると発表した。少なくともこれから数週間、この機能を使って他人と交流することになるだろう。
インスタグラムのCo-watching機能はその名が示す通り、友人と一緒に画像や映像を見る機能だ。インスタグラムの場合、「Direct(ダイレクト)」の右上、情報アイコンの隣にあるビデオチャット・アイコンをタップして、友人を呼び出す。すると画面が立ち上がり、呼び出していることを他の参加者に知らせる。全員揃ったら、ビデオチャットの左下にあるカメラ・アイコンをタップすることで、保存または「いいね!」がしてあったり、おすすめしたりしている写真・映像を一緒に見られる。
インスタグラムだけではない。共同視聴は大流行している。画面を共有することで、友人や家族と離れていても一緒に映画を鑑賞でき、社会距離戦略を実践していても同じ空間で過ごす疑似体験ができるからだ。
共同視聴にはいくつかの方法がある。
ネットフリックス・パーティ(Netflix Party)
グーグル・クロム(Chrome)の無料拡張機能で、大量にダウンロードされている。利用には視聴者ごとにネットフリックスのアカウントが必要だ。ダウンロード後、クロムからネットフリックスにアクセスするとネットフリックス・パーティ拡張機能が表示される。見たい映画を選んで拡張機能をクリックすれば、グループ内で選択した映画が共有される。グループチャット欄が表示された状態で映画が始まり、視聴者が文字を入力したり、チャットしたりできる。期せずして感心させられたのは、ビデオ・チャットや音声チャットの機能がないため、映画などの大事な場面を邪魔するような視聴者側の音や映像に煩わされることがなく、静かな環境で映画を視聴できることだ。
メタストリーム(Metastream)
ネットフリックス・パーティとは別の無料拡張機能で、ネットフリックスだけでなくユーチューブなどのストリーミング・メディアにまで選択肢を広げられる(これで、猫の映像を常時流せる)。フールー(Hulu)や音声ファイル共有サービス「サウンドクラウド(SoundCloud)」、ライブ・ストリーミング配信プラットフォーム「ツイッチ(Twitch)」に対応している。マニアックな話題を深く堀下げるには、レディット(Reddit)もいい。ネットフリックス・パーティ同様、チャット機能のおかげで視聴にじゃまは入らない。ユーチューブの個人的なリストを作りたい場合は、ユーチューブのストリーミングをキュレーションすることもできる。
ディスコード(Discord)
テレビゲームの共同プレイでは、長い間「ディスコード(Discord)」が人気のプラットフォームだ。ユーザーは活発にゲームに出入りしながら、別のこともできる。専用アプリをダウンロードする必要がある。
以前からの方法を利用
クロムの拡張機能に関心がなかったり、ダウンロードするアプリなどをこれ以上増やしたくないと思う人もいるだろう。新しいハイテク経験を必要としない以前からの方法として、「ズーム(Zoom)」や「フェイス・タイム(FaceTime)」などのビデオ通話アプリに、見ている映像を映すという手段もある。そして、一緒に見たい映像を視聴すればよいのだ。画質や音質がそれほど重要でなければ、これが手っ取り早い方法だ。
共同視聴は、エンターテイメントの消費スタイルを変える可能性がある。ツイッチのテレビゲーム・ストリーミングは、映像を見ながら人とつながるという行動に人気があることを証明した。2014年にさかのぼれば、「ネットフリックス・アンド・チル(ネットフリックスを見てくつろぐ)」が一大現象となった際、映像を再生しながら同時にグループ・チャットをしたい人々の間で「ラビット(Rabb.it)」というプラットフォームが人気となった。ラビットはその後姿を消したが、次々と生まれている新しいアプリによって、「映画を一緒に楽しむ」という体験を再現できる。さて、何を見ようか?
(関連記事:新型コロナウイルス感染症に関する記事一覧)
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット
- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差
- ターニャ・バス [Tanya Basu]米国版 「人間とテクノロジー」担当上級記者
- 人間とテクノロジーの交差点を取材する上級記者。前職は、デイリー・ビースト(The Daily Beast)とインバース(Inverse)の科学編集者。健康と心理学に関する報道に従事していた。