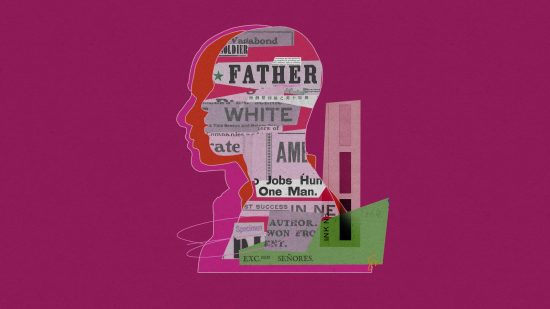ギャレス・エドワーズ監督、最新作でAI生成音楽に挑んで得た教訓
映画「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー」の監督であるギャレス・エドワーズは、最新作『ザ・クリエイター/創造者』のサウンドトラックをAIに作らせようと考えた。AIが作った楽曲は結悪くなかったが、最終的には採用を見送ったという。 by Melissa Heikkilä2023.09.26
『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(Rogue One: A Star Wars Story)』を監督したギャレス・エドワーズは、人工知能(AI)を題材にした次回作『ザ・クリエイター/創造者(The Creator)』(10月公開予定)のサウンドトラックについて考えていたとき、AIを使って作曲してみようと決めた。そして実際、「かなり上出来」な結果を得られたという。
「誰にも言わなければもっといいだろうなと思っていました。AIを使ってサウンドトラックを作りつつ、それをまるで誰かが作ったかのように秘密にしておいて、すべてが終わったら、『ははは、実はAIだったんだ』と種明かしたらいいんじゃないか、ってね」と、エドワーズ監督はMITテクノロジーレビューの公開インタビューで語った。
エドワーズ監督はとあるAI音楽会社に、AIを使ってオスカー受賞作曲家であるハンス・ジマー風のサウンドトラックを作るように依頼した。
AIシステムが生成した楽曲は「10点満点中7点」くらいの出来だったと、エドワーズ監督は言う。
「ただ頭の片隅では、『でも、ハンス・ジマー風にする理由は、10点満点中10点を取るためなんだよな』と考えていました」と、エドワーズ監督は付け加えた。
結局、自分の映画のサウンドトラックに現実の生身の人間であるハンス・ジマーを起用したエドワーズ監督は、ジマーにAIが生成した楽曲を聴かせたという。ジマーはそれをおもしろがったと、エドワーズは話した(ジマーとは連絡がつかず、コメントは得られなかった)。
エドワーズ監督の実験は、現在のハリウッドが直面している大きな戦いの1つにおける、中心的な問題について物語っている。アーティストやクリエイターたちは、生成AI(ジェネレーティブAI)をめぐりいきり立っている。ハリウッドでは現在、より公平な労働条件と映画業界における生成AIの使用をめぐって、俳優と脚本家がストライキを起こしており、膠着状態にある。また、作家やアーティストからも、テック企業が見境なくWebをスクレイピングして画像を取得することで知的財産を盗んでいるとして、猛反発が出ている。コメディアンで作家のサラ・シルバーマンなど、著名なアーティストたちは、AI企業を著作権侵害で訴えた。
音楽生成AIは、まだ黎明期にある。そのことが、エドワーズ監督が得た結果を説明するかもしれないと、生成AIの専門家ヘンリー・アイダーは言う。
「私の経験では、非常にシンプルなAI音楽の中には、人間が作曲したかのように聴こえるものがあります。AIが生成した曲と人間が作った曲の違いを見分けるのは困難です」と、アイダーは話す。
しかし、ハンス・ジマー風のより長い曲は、ピアノだけを使った単純なメロディーよりも、生成するのがかなり複雑であると、アイダーは付け加える。AIシステムが生成できる曲は訓練データの中にあるものに制限されるのに対し、人間であるジマーには想像力があり、彼を取り巻く世界全体からインスピレーションを得る。
極めて重要なこととしてエドワーズ監督が挙げたのは、AIシステムには優れた芸術作品を創造するための基本的かつ重大なスキルである「センス」が欠けているという点だ。AIは、人間が何を良い、あるいは悪いと見なすのか、まだ理解していない。この理由からエドワーズ監督は、クリエーターはAIを恐れるのではなく、AIを使うべきだと考えている。「AIが台頭していることは、誰もが十分に認識しています。AIはツールです」と、エドワーズ監督は言う。「これからも大丈夫な人は、このブレークスルーが起こっていることを否定せず、それを受け入れ、学び、ツールとして使おうとする人たちです」。
エドワーズ監督は、今日のAIブームと写真編集ソフトウェア「フォトショップ」の発明との間の共通点を引き合いに出した。
フォトショップが登場したとき、世間ではこのソフトウェアが「冒涜的だ」という議論があったと、エドワーズ監督は言う。
「私たちは最終的に、その段階を乗り越えました。今、フォトショップは、非常に多くの人々に対し、芸術的な作品を作り出す機会を与えています。(中略)もう後戻りはしたくありません」と、エドワーズ監督は語った。
エドワーズ監督は、カメラの発明や『ジュラシック・パーク』のデジタル視覚効果と同じように、AIは映画業界に地殻変動をもたらすだろうと言う。「AIもそうした変化の1つに過ぎないことを願っています」。
- 人気の記事ランキング
-
- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗
- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア
- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- メリッサ・ヘイッキラ [Melissa Heikkilä]米国版 AI担当上級記者
- MITテクノロジーレビューの上級記者として、人工知能とそれがどのように社会を変えていくかを取材している。MITテクノロジーレビュー入社以前は『ポリティコ(POLITICO)』でAI政策や政治関連の記事を執筆していた。英エコノミスト誌での勤務、ニュースキャスターとしての経験も持つ。2020年にフォーブス誌の「30 Under 30」(欧州メディア部門)に選出された。