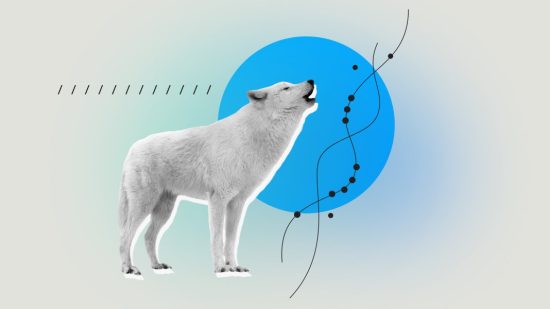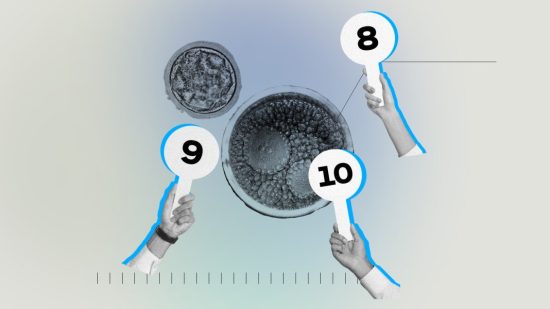進む創薬革命、
「真のAI生成薬」治験へ
人工知能(AI)を活用して新薬開発をスピードアップすることを掲げる企業が急増。そのうちの1社であるインシリコ・メディシンは、致命的な胚の疾患の治療薬において、ヒトを対象とした第2相臨床試験まで初めて進み「真のAI創薬」を実現したと主張している。 by Antonio Regalado2024.03.25
プログラマー兼物理学者のアレックス・ザボロンコフ博士は、10年以上にわたって人工知能(AI)の活用法を追求してきた。2016年には、AIを使って人を見た目でランク付けしたり、猫の写真を選別したりした。
ザボロンコフ博士が創業し、最高経営責任者(CEO)を務めるインシリコ・メディシン(Insilico Medicine)は、死をもたらす肺疾患の治療薬の開発において、ヒトを対象とした臨床試験段階まで初めて進んだ「真にAIで生成した薬」を実現したという。
ザボロンコフCEOによると、同社の新薬候補が特別なのは、AIソフトウェアが、細胞内で相互作用する標的の選択を支援しただけでなく、新薬候補の分子構造の決定も支援したからだという。
AIというと一般的に、絵を描いたり質問に答えたりすることができるものが多い。しかし、AIに悪性疾患の治療法を考え出させる取り組みも増えている。AIチップやサーバーを販売するエヌビディア(Nvidia)のジェンスン・フアン社長が昨年12月に、AIによる「次の驚異的な変革」が起こるのは「デジタル生物学」分野だと主張したのはそのためかもしれない。
「史上最大規模の変革となるでしょう」とフアン社長は語った。「人類史上初めて、生物学は科学ではなく、工学となる機会を得たのです」。
AIに期待されているのは、研究者だけでは考えつかなかったような新しい治療法を、AIソフトウェアが示してくれることだ。チャットボットが期末レポートの概要を示してくれるように、AIは、薬剤の標的やその薬剤のおおまかな設計を提案することで、新しい治療法を発見するための初期段階をスピードアップできるかもしれない。
ザボロンコフCEOは、インシリコの新薬候補の発見段階で両方のアプローチが使われたと言い、その新薬候補の開発の急速な進展(新薬候補の化合物の合成と動物実験の完了までに要した期間は18カ月)は、AIが創薬をスピードアップできることを実証していると述べた。「もちろん、AIのおかげです」。
AI創薬企業の急増
10年ほど前からバイオテクノロジー業界では、AIを活用して新薬開発をスピードアップすることを約束するスタートアップ企業が急増した。リカージョン・ファーマシューティカル(Recursion Pharmaceuticals)や、最近ではグーグル・ディープマインド(Google DeepMind)部門からスピンアウトしたアイソモーフィック・ラボ(Isomorphic Labs)などがそうだ。
ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)によると、AI関連の大げさな宣伝に押され、このような企業は2012年から2022年の間に約180億ドルを調達した。インシリコは株式非公開のままで台湾と中国で事業を展開しており、未公開株式投資会社のウォーバーグ・ピンカス(Warburg Pincus)やフェイスブックの共同創業者エドゥアルド・サベリンなどから4億ドル以上の資金提供を受けている。
しかし、こうした企業が解決しようとしている問題は古くからあるものだ。最近の報告書によると、世界のトップ製薬企業は、1つの新薬を市場投入するまでに、研究開発に60億ドルを費やしていると推定されている。その理由の1つは、ほとんどの新薬候補が失敗に終わっていることである。加えて、新薬開発プロセスには通常、最低10年はかかる。
AIが本当に新薬開発を効率化できるかどうかは、まだはっきりしない。BCGが2022年に実施した別の調査では、「AIネイティブ」のバイオテクノロジー企業(AIが研究の中心であるとする企業)は、新薬のアイデアを「目を見張るほど」次々と打ち出し、開発を進めているという結果が出ている。BCGによると、細胞や動物で試験された化学物質の候補は160種類、さらに15種類がヒト臨床試験の初期段階にあるという。
この数の多さは、コンピューターが生成した医薬品が一般的になる可能性を示唆している。BCGは、「AIを活用した創薬への最大の期待は、スケジュールの加速である」と表明しているにもかかわ …
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?