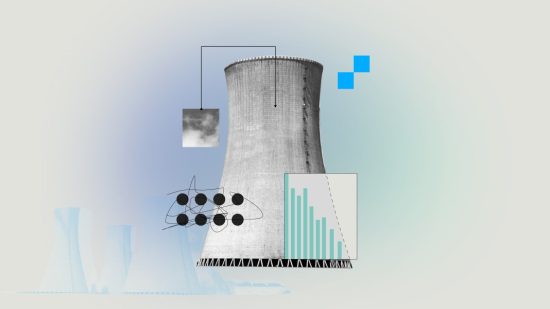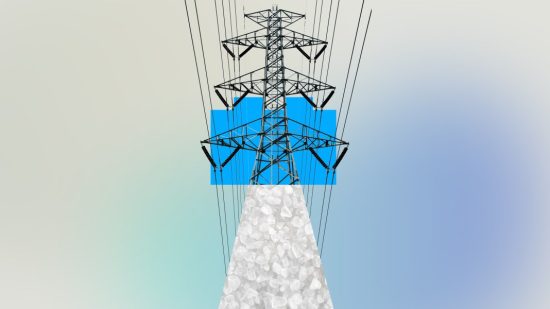気候対策骨抜きに? 米環境庁、温室効果ガス規制見直しを検討
トランプ政権は、環境保護庁(EPA)が温室効果ガス排出を規制することを可能にする規則の撤廃を検討している。この目論見が通れば、米国は気候変動に対処しようとする法的手段を一切持たなくなる可能性がある。 by Casey Crownhart2025.08.05
- この記事の3つのポイント
-
- 米国EPA長官が温室効果ガス規制の根拠となる2009年危険性認定の見直しを指示
- 大気浄化法が地球規模気候変動への権限を与えていないと主張し、規制撤回を提案
- 米国が気候変動に対処する法的手段を失う可能性があると専門家は警告
米国連邦政府が気候変動を規制するのを可能にする仕組みが、廃止の危機に瀕している。
7月29日、米国環境保護庁(EPA)のリー・ゼルディン長官は、同庁が危険性認定、すなわち米国の温室効果ガス規制を支える本質的な柱である2009年の規則について存続の可否を検討していると発表した。
これは曖昧な法的状況のように聞こえるかもしれないが、米国の気候政策にとって実に重大な問題である。それでは身を引き締めて、この規則が現在何を述べているのか、提案された変更がどのようなものか、そしてそれが全体として何を意味するのかを見ていこう。
背景を説明するために、1970年の「大気浄化法(Clean Air Act)」まで遡る必要がある。この法律は本質的に環境保護庁に大気汚染を規制する権限を与えたものである(あきらめずに最後まで読んでほしい。簡潔にまとめ、法的な細かい話には深入りしないことを約束する)。
この法律とその修正法では、鉛や二酸化硫黄を含む一部の汚染物質が明示的に指定されていた。しかし、有害であることが判明した新たな汚染物質についても、環境保護庁による規制を義務付けていた。1990年代後期から2000年代前期にかけて、環境団体や各州は、温室効果ガス汚染も対象に含めるよう同機関に求め始めた。
2007年、最高裁判所は温室効果ガスが大気浄化法の下で大気汚染物質に該当するとの判決を下し、環境保護庁は温室効果ガスが公衆衛生に危険をもたらすかどうかを調査すべきであるとした。2009年、新たに誕生したオバマ政権は科学的根拠を検討し、温室効果ガスは気候変動を引き起こすため公衆衛生に脅威をもたらすとの判断を下した。これが危険性認定であり、この判断により同庁が温室効果ガスを規制する規則を制定することが可能になった。
元の訴訟と議論は具体的に自動車と排気管からの排出物に関するものであったが、この判決は最終的に環境保護庁が発電所や工場に関する規則も設定することを可能にするために使用された。これは本質的に米国における気候規制を支えるものである。
現在に至り、トランプ政権は危険性認定を覆そうとしている。7月29日に発表された規則案において、環境保護庁は、大気浄化法は実際のところ、地球規模の気候変動に対処するための排出基準を設定する権限を同庁に与えていないと主張している。ゼルディン長官は、公式発表に先立って保守系政治ユーモアポッドキャスト「ルースレス(Ruthless)」に出演し、この提案を「米国史上最大の規制緩和措置」と呼んだ。
トランプ政権はすでにこの規則に依存する気候規制を弱体化させる動きを見せていた。しかし、今回の動きはスタンフォード大学の環境法教授であるデボラ・シバスが言うところの「環境保護庁の気候政策の基本的な構成要素」を直接、標的にするものである。
提案された規則はパブリックコメントにかけられ、その後、同庁はそのフィードバックを受けて最終版を策定する。ほぼ確実に法的異議申し立てを受け、最高裁判所まで持ち込まれる可能性が高い。
ここで注目すべき点は、環境保護庁が提案した規則撤回において、気候変動の科学を攻撃することに焦点を当てるのではなく、主に法的論拠を展開していることである。そう述べるのは、ボストン大学の法学准教授であるマディソン・コンドンだ。このプロセス全体には時間がかかるものの、最終的に最高裁判所が規則撤回を支持することが容易になる可能性があるとコンドン准教授は言う。
危険性認定が取り下げられれば、広範囲にわたる波及効果をもたらすであろう。「私たちは数年後、気候変動に対処しようとする法的手段を一切持たない状況に陥る可能性があります」とシバス教授は述べる。
少し立ち止まって考えてみると、単一の規則が排出規制の中心となるこのような状況に至ったことは驚くべきことである。米国の気候政策はガムテープと夢で何とか持ちこたえているような状況だ。議会は、いつかの時点で、環境保護庁が直接的に温室効果ガス排出を規制できるようにする法律を可決できたはずである(最も近づいたのは2009年の法案で、下院を通過したが上院は通らなかった)。しかし、現実はこうなのだ。
この動きは、正確には驚くべきことではない。トランプ政権は、あらゆる手段で気候政策を攻撃していることを非常に明確にしている。しかし、私にとって最も印象的なのは、この問題に関して、私たちがもはや共通の現実の中で行動していないということである。
上級官僚らは気候変動が現実であることを認める傾向がある。だが、しばしば「しかし」に続いて気候変動否定論の定番の論点が語られる(より馬鹿げた例の一つは、二酸化炭素は植物の成長を助けるため実際には良いものであるという主張である)。
気候変動は現実であり、脅威である。そして米国は世界のどの国よりも多くの温室効果ガスを大気中に排出している。政府が何らかの対策を講じることを期待するのには、論争の余地はない。
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか
- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?
- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者
- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。