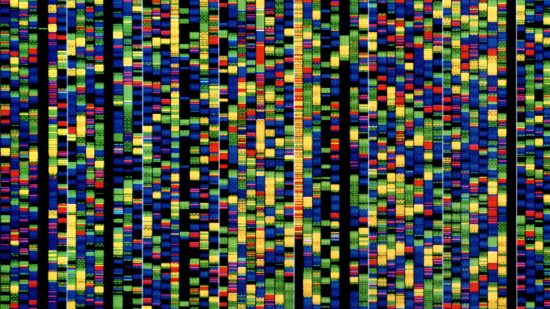脳インターフェイス、利用者の同意どう得る? 難しい倫理的問題
脳コンピューター・インターフェイスは、全身麻痺などでコミュニケーション能力を失った人々への福音となる可能性がある。しかし、コミュニケーションを取る方法がまったくない人たちが、調査研究に参加することは倫理的な観点から難しい。 by Cassandra Willyard2023.08.31
この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。
ちょっとワクワクする新しい研究を先日の記事で取り上げた。話す能力を失った人々が脳コンピューター・インターフェイスを使って声を取り戻したことを、2つの研究チームが報告したのだ。それぞれのチームは異なる種類のインプラントを用い、脳が発する電気信号をとらえ、それらの信号をコンピューターを使って音声に変換した。
1つ目の研究に参加したパット・ベネットは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患った結果、話す能力を失った。ルー・ゲーリッグ病とも呼ばれるALSは、全身の神経を侵す破壊的な病気である。最終的には完全麻痺に近い状態になり、思考や論理的な判断はできても、コミュニケーションをとる手段がほとんどなくなってしまう。
もう1つの研究に関わった47歳の女性アン・ジョンソンは、脳幹卒中を発症した結果、麻痺状態になって声を失い、話すことも文字をタイプすることもできなくなってしまった。
この2人の女性は、脳インプラントがなくてもコミュニケーションをとることができる。ベネットはコンピューターを使って文字をタイプする。ジョンソンは視線追跡装置を使って、コンピューター画面上の文字を選択する。あるいは、しばしば夫の助けを借り、文字盤を使って単語を綴る。どちらの方法もスピードが遅く、1分間に14語か15語程度が限界だが、目的は果たせている。
そのようにコミュニケーションをとる能力があったため、2人は臨床試験への参加に同意することができた。しかし、コミュニケーションをとるのがもっと困難な場合、どのようにして同意すればよいのだろうか。この記事では、脳インプラントのようなテクノロジーを最も必要としているのに、自分の考えや感情を知らせる能力がほとんどない人々を対象とする科学研究における、コミュニケーションと同意の倫理問題について見てみよう。
この種の研究から特に恩恵を受ける立場にある人々は、ロックイン症候群(LIS)患者だ。彼らは意識はあるが、ほとんど全身が麻痺しており、動くことも話すこともできない。一部には、視線追跡装置やまばたき、筋収縮を使ってコミュニケーションをとれる患者もいる。
たとえば、ジャン・ドミニク・ボービーは脳幹卒中を患い、左目のまばたきでしかコミュニケーションがとれなかった。それでもボービーは、1冊の本を書くことに成功した。心の中で文章を組み立ててから、アシスタントにアルファベットを繰り返し読み上げてもらい、一度に一文字ずつ指示したのである。
しかし、そのような種類のコミュニケーションでは、患者も手助けする者も疲れ切ってしまう。また、患者のプライバシーを奪うことにもなる。「質問してくれる他人に、全面的に依存しなければなりません」と、オランダの大学医療センターユトレヒト脳センターの神経科学者、ニック・ラムゼイ教授は言う。「したいことはすべて、プライベートになりません。家族とコミュニケーションをとりたいときでさえも、常に他の誰かがいるのです」。
脳が発する電気信号をリアルタイムでテキストや音声に変換する脳コンピューター・インターフェイスは、そのようなプライバシーを回復させ、患者に自分の言葉で会話する機会を与えるだろう。しかし、臨床試験の一環として脳インプラントの設置を研究者に許可するかどうかは、軽々しく決定されるべきではない。脳神経外科手術やインプラントの設置には、発作や出血、感染症などのリスクが伴う。また、多くの臨床試験において、インプラントは永久に使えるようには設計されていない。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の神経外科医、エドワード・チャンらの研究チームは、研究への参加希望者に対し、そのことをはっきり伝えることにしている。「これは期間限定の試行です」と、チャン医師は言う。「参加者には、何年か後にインプラントを取り外す可能性があることを、十分に説明しています」 。
治験参加者から確実にインフォームドコンセントをとることは常に重要だが、コミュニケーションが困難な場合、そのプロセスは厄介なものとなる。
ラムゼイ教授の研究グループは、何年も前からALS患者と協力して研究をしてきた。同教授らのように、コミュニケーション能力が極端に制限されている患者と協力している研究チームは、数少ない。2016年にラムゼイ教授らのチームは、あるシステムの開発に成功したことを報告した。そのシステムを使い、ALSの女性は心に思うだけでマウスのクリック操作ができるようになったという。この女性は、研究が終了するまでに、1分間で3文字を選択できるようになった。「その患者は7年間このシステムを使っています。他の手段がもう使えなくなった後は、昼夜を問わずこのシステムを使ってコミュニケーションをとりました」と、ラムゼイ教授は言う。現在、同教授らのチームは、他の患者と協力して、脳の活動を音声に変換することを試みている。
同意のプロセスは「かなり複雑な手順」だと、ラムゼイ教授は言う。研究チームはまず、研究の詳細を何度も説明する。その後、20問の簡単なイエス・ノー形式の質問をし、参加希望者が研究に伴う影響を理解していることを確認する。間違えることができる質問の数には、上限が設けられている。これらの手順はすべて、法的保護者と独立したオブザーバーの立会いのもとで実施され、すべての手順がビデオに録画されると、ラムゼイ教授は話す。このプロセスにかかる時間は4時間ほどだ。ただし、これとは別に、患者が自分の決断について熟考するための時間が数週間必要となる。
介護やコミュニケーションを他人に依存している人たちは、特に弱い立場にある。ある研究論文の指摘によれば、同意に対する患者の願望は、その決断が家族や介護者に及ぼすかもしれない結果に影響される可能性があるという。「埋め込み可能なBCI(脳コンピューター・インターフェイス)の治験や治療によって、他者に対する依存の性質や程度が改善される見通しがある場合、(ALS患者は)BCIを希望する義務があると感じるかもしれません。この義務感の性質によっては、BCIを埋め込むという決断の自発性に疑いが生じる可能性があります」。
ラムゼイ教授の研究グループは、完全にロックイン(目を含め全身が麻痺)していて、自発的な動きや音でコミュニケーションをとることができない患者を、研究協力の対象から除外している。しかし、同教授によれば、fMRIスキャナーの助けを借りることで、同意をとれる可能性があるという。「それには、単語を読む、数字を逆に数える、といったような、簡単な作業をしてもらう必要があります」と、ラムゼイ教授は話す。「眠っていなければ誰でもできる簡単な作業です」。もし、対象者がそのような作業をしていないことがデータからわかれば、研究者たちは、「この人は指示に従うことができないか、あるいは参加を希望しておらず、わざとその作業をしないことで意思を伝えているのだろう」と推測できる。
しかし、それはまだ理論上の話だ。ロックイン症候群の最も極端な症状を持つ人々に脳インプラントを埋め込むことは、一般的にひんしゅくを買うと、ラムゼイ教授は言う。
「自己表現ができない人をBCIの研究に関わらせることに対しては、明確な法的・倫理的ルールがあります」と、ラムゼイ教授は話す。「たとえ法的保護者の同意があるとしても、完全なロックイン症候群の人への脳インプラントを正当化するのは、非常に困難です」。昨年発表された研究報告によれば、完全にロックイン状態となった男性が、脳インプラントの助けを借りて、特定のトーンに合わせ脳の活動を変化させることでコミュニケーションをとることができたという。しかし、このケースでは、男性がコミュニケーション能力を完全に失う前に、治療行為に対する同意をとっていた。
少なくとも今のところ、すでにロックイン状態にある人々は、どうすることもできない。そういう人たちがコミュニケーションをとるための唯一の希望が脳コンピューター・インターフェイスかもしれないが、参加したい意思を伝えることができないため、研究対象から除外されている。技術が進歩し、新しい治療法が生み出されれば、そのような人々の一部は声を取り戻せるかもしれない。だからこそ、彼らがインフォームドコンセントを与えるための倫理的な方法を見つけることは、追求する価値のある目標なのである。実際、そうすることは道徳的要請であるという科学者もいる。
MITテクノロジーレビューの関連記事
研究者たちは研究参加者に与えた脳インプラントを、その人が望んでいないのに取り外してしまうこともある。本誌のジェシカ・ヘンゼロー記者が、脳インプラントを失う感覚について、そしてそのような事態から研究参加者を守るための新たな法律の必要性について報告している。
起業家たちは大衆向けの脳インプラントを望んでいるが、科学者の多くは、最も必要としている人たちが確実にインプラントを手に入れられることを望んでいる。2021年にアントニオ・レガラード編集者が、脳コンピューター・インターフェイスの未来を深掘りした。
テクノロジーは、脳を解読する能力をどんどん高めている。ジェシカ・ヘンゼロー記者は今年、脳のプライバシーを守るために考えられる方法を探った。また、フューチャリストの法倫理学者ニタ・ファラハニー教授にインタビューして、『The Battle for Your Brain(脳をめぐる戦い)』(未邦訳)について話を聞いた。
◆
医学・生物工学関連の注目ニュース
FDA(米食品医薬品局)が妊婦用の新たなRSウイルスのワクチンを承認したため、早ければ10月にも接種が可能になるかもしれない(NBCニュース)。
ネイチャー・メディシン(Nature Medicine)に掲載された新たな研究論文によると、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患期間が長かった人は、健康上の問題が2年以上続く可能性があるという。退役軍人省の健康記録に基づくこの研究は、パンデミックの初期にたとえ軽度であっても新型コロナウイルス感染症に罹患した人たちは、当時ウイルスに感染しなかった人たちよりも、2年後に肺の問題や糖尿病などの健康問題を抱えているリスクが高いことを示唆している。 (ワシントンポスト)。
この新しい多くの減量薬の長くて奇妙な歴史の中には、アメリカドクトカゲ(ギラ・モンスター、日本版注:唾液に食物摂取の抑制に伴う体重減少作用などを有する成分がある)も含まれている。それらは効果があるが、科学者たちはまだその理由がわからない。(ニューヨーク・タイムズ)
この秋、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染者数が増えている。しかし専門家たちは、すぐに季節的なパターンに落ち着くとは考えていない。(スタット・ニュース)
- 人気の記事ランキング
-
- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機
- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ
- cassandra.willyard [Cassandra Willyard]米国版
- 現在編集中です。