人工知能(AI)
-
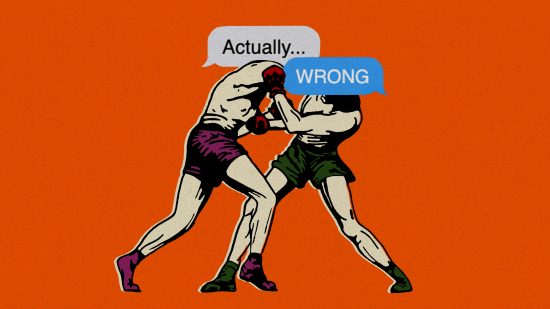
LLMが説得力で人間超え、相手に合わせて議論を調整
-

「顔認識禁止」を回避、体格や髪型で防カメ映像を追跡するAIツール
体格や髪型、服装などの属性を使って複数の防犯カメラ映像に映る人物を追跡できるAIツールが開発され、米国の警察や政府機関で導入が進んでいる。 顔などの生体情報を使わないため、規制を回避できるという。
-
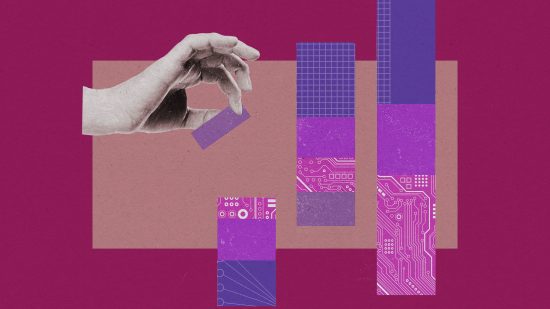
AIの実力、どう測る? 時代遅れのベンチマーク、 信頼できる評価方法とは
-

複数話者の声と位置も識別、多言語通訳のAIヘッドフォン技術
-

脳でタイプ、AIが代筆 ニューラリンクが ALS患者に開いた道
ニューラリンクの脳インプラントを埋め込んだALS患者が、考えるだけでテキストをSNSに入力できるようになった。生成AIの力も借りて、コミュニケーションのスピードアップを実現している。
-

人型ロボット、熱狂と現実にギャップ 繰り返される誇大広告
-

生成AIは建築をどう変えるか? NYC展覧会で見た可能性
-

生成AIが再編する 韓国ウェブコミック産業 作家に残された仕事は?
-

AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景
-
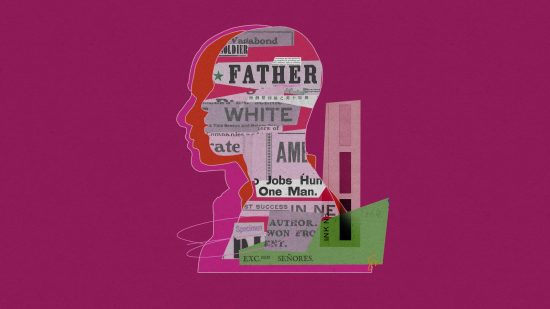
16言語に対応、LLMに潜むバイアスを探るデータセット
-

揺らぐ創造と複製の境界線、 音楽にもAIがやってくる
-

米軍で導入進む「戦場のLLM」、未解決の3つの課題とは?
米軍が軍事情報の分析に大規模言語モデルの導入を進めている。これまでも映像分析などにAIを活用してきたが、今後は重大な意思決定に利用することになるだろう。
-

消費から創造へ、 アーティストたちが模索する 生成AIとの新しい「共創」
-

動き出した「静かな巨人」、中国発のAIモデルが世界に与えた驚き
-

「あなたの声」政策に 米小都市が挑む、AI活用の直接民主主義
-

推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能
-
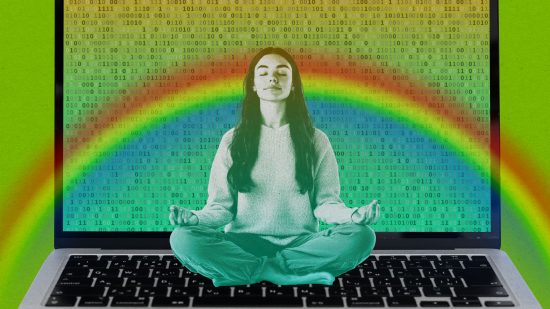
バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
-

軍事インテリジェンスに生成AI、米軍が太平洋演習で効率化を実証
-

大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
-

SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
-

サイバー攻撃を完全自動化、 自律型AIハッカーが やってくる
AIエージェントを使うことで攻撃者は、大規模なシステムをより簡単かつ安価にハッキングできるようになる。AIエージェントが実行した思われるサイバー攻撃もすでに確認されており、広がるのは時間の問題だ。
-

生成AIで驚きのセラピー効果? 訓練データが成否を分ける
-
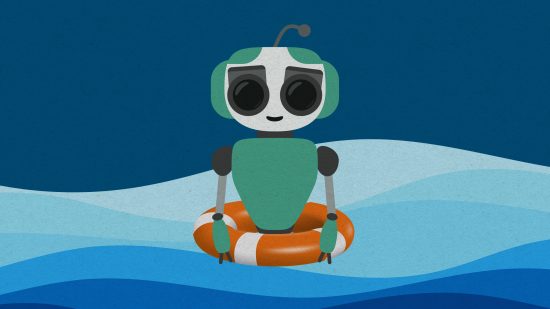
生成AIによる精神疾患治療、初の臨床試験で「人間並み」効果
-

徳井直生:生成AIは究極の消費ツール 創造的に付き合うには
-

今井翔太:予測困難な生成AI技術の進化 急変する世界にどう備えるか
