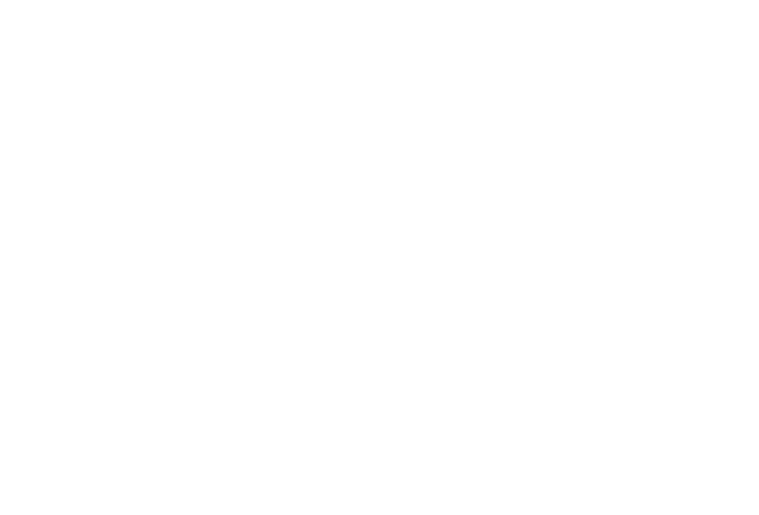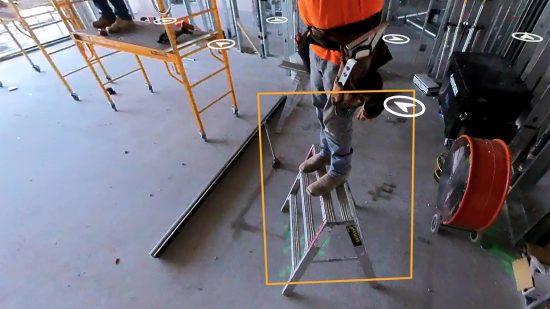「脆弱なコミュニティの支援に技術を活かす」。これが、織井理咲(Lisa Orii)の研究者としてのミッションだ。
2017年に米国ウェルズリー大学に入学し、コンピューターサイエンスと哲学を学んだ織井は、声の特性と社会的バイアスに関する研究を東京大学と共同で実施した。織井が主導したこの研究は、インタラクティブな音声特徴変換などの新しい技術を利用した発話練習が、話者の自己認識に与える影響を調査したものだ。研究では、男性的な低い声で発声すると信頼されやすく、女性的な高い声で話すと批判されやすい、といったジェンダーバイアスの存在が明らかになった。織井らは、バイアスにとらわれない自分らしい話し方を見つけ、練習するためのシステムの設計方法をまとめ、提案した。
研究成果をまとめた論文は2022年5月、ヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)分野のトップ学会において発表された。
織井は現在、ワシントン大学で、グローバルヘルスに関する2つのプロジェクトを進めている。1つは、女性が更年期の経験を堂々と語り共有し合えるための研究だ。更年期の経験・知見を世代間で共有することにより、女性の心身の健康をサポートするツールを提案している。
もう1つは、マラウイ共和国のHIVクリニックに導入する電子カルテに関する研究だ。現地で医療従事者、患者、データ管理者、政府関係者らと話し合い、電子カルテのセキュリティに関する課題を抽出した。正確で安全な医療を実現するために、医療スタッフへの教育プログラムと、患者が個人情報管理の重要性を理解するためのガイドラインの策定を進めている。
これらの研究は脈絡がないように見える。しかし、社会的に弱い立場にある人々が直面する社会的・技術的な困難・不利益を、テクノロジーを用いて軽減しようとする志向で一貫している。
(畑邊康浩)
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法