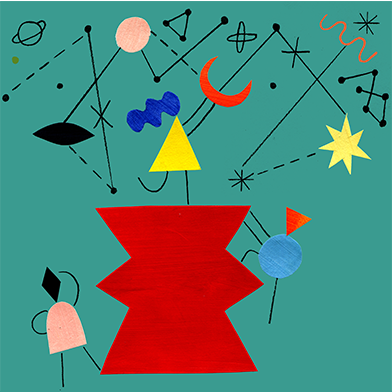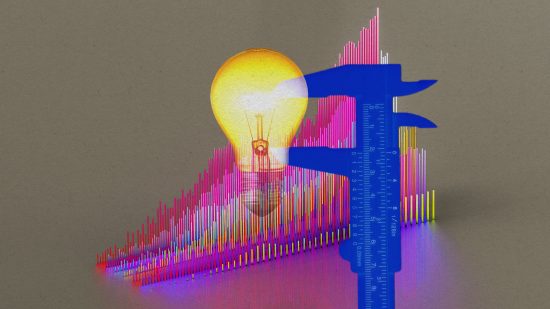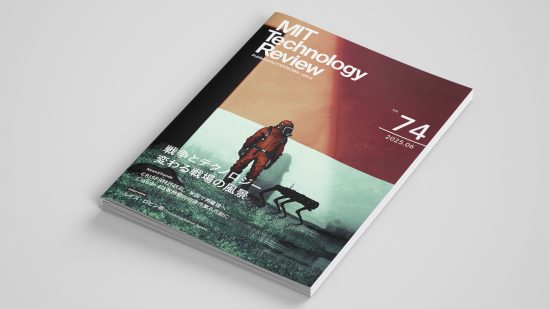化学工学と材料科学が専門のビビアン・フェリー助教授は青緑色のゴム手袋をはめて、透明な液体が入った口紅サイズの試験管を持っている。試験管に紫外線を当てると、中の液体が明るい蛍光オレンジに変わった。液体に浮かぶ非常に小さな結晶がエネルギーの高い青色の波長を吸収し、エネルギーの低い赤色の波長を放出したのだ。
従来の太陽電池は限られた光の波長を吸収するため、ほとんどの太陽エネルギーを逃してしまう。もし太陽電池がもっと多くの光を捕らえられれば、発電量が増え、太陽光発電がもっと安くなる。そこでフェリー助教授は、発光性の結晶に加え、特定の波長を捕らえて太陽電池に光を向けるナノ構造の非常に小さな金属製の鏡に目を付けた。
現在、フェリー助教授はセレン化カドミウムと硫化カドミウムで発光性のナノ結晶を作っているが、カドミウムは有害な金属なので、どちらも理想的とはいえない。しかしフェリー助教授が豊富にある物質で無害化(その後でコストの削減)できれば、このテクノロジーはまだ有望だ。
(エミリー・ソーン)
- 人気の記事ランキング
-
- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?
- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ
- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測
- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット
- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差
| タグ | |
|---|---|
| クレジット | Photo by Hunt and Capture |
| 著者 | MIT Technology Review編集部 [MIT Technology Review Editors] |